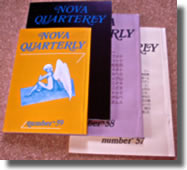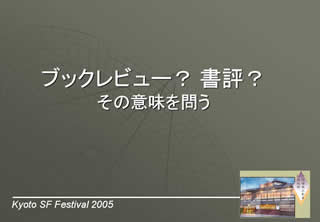![]()
編者が生まれた年、ゴジラが東京湾に上陸し、甚大な被害をもたらした。幸いにも編者は兵庫県にいたため、被害を受けなかった。その詳細については、何度も映画化や記録の出版がされているが、未だに正確なものはない。同じ映画会社が作った作品間で、矛盾があるのは納得のいかないところである。
1968年
最初の大人向けSFを読む。1971年
最初のファンジンを作成。高校生の男女5人で作ったガリ版で、30部程度を印刷。当時最先端だったSF風文芸同人誌だった(と思う)。現存せず。1972年
出版物『チャチャ・ヤング ショート・ショート』(講談社)に最初の作品が掲載される。
 装幀: 山内暲、飯島豊 |
大阪の毎日放送で放送されていた、深夜ラジオ番組「チャチャ・ヤング」(毎日深夜1:30~5:00放送)では、高石ともや、谷村新司らとともに眉村卓(金曜日担当)が番組を担当していた。ピンクフロイド一気オンエアなど、特徴があったが、何といっても、深夜3時過ぎ頃のショート・ショートコンテストが圧巻。大変な人気があり、番組で作ったパンフレット形式の作品集は、4,000部があっというまに捌けてしまったという。投稿者は受験生が中心で、後になるほどレベルが上がっていった。編者はここに投稿していた。左掲は後に講談社から出た傑作選である。 |
1973年
神戸大学SF研でファンジン製作にかかわる。
 |
「れべる烏賊」は神戸大学SF研究会のファンジンだったが、当時はタイプ印刷機の普及も一般的ではなく、弱小同好会では手書きのガリ版/手刷りで100部が精一杯だった。製本代を浮かせるために、製本まで全て手作りである(ここまで手作りは当時でも珍しい)。当時は、ガリ切りの達人でなければ編集はできない。米村秀雄や、大野万紀は字が読みやすかった。編者と水鏡子の作った部分は、文字がかすれて読めなかった。 |
同年『創作研究会』(後に、西秋生や中相作らのグループと分裂)に参加。このグループは、上記「チャチャ・ヤング」から生まれたもので、眉村卓さんの協力を得ていた。
1974年
「サスペンス・マガジン」(久保書店)でSFレビュー欄「SFパトロール」を担当。眉村さんの紹介によるもの。久保書店はQTブックスなど、SFの翻訳シリーズを出すほどの出版社だった。編集者がSF好きだったので、何の関係もない自社雑誌にSF紹介の欄を設けたのである。古くは福島正実も、ペンネームでレビューを書いていた。この雑誌、実は“SM”雑誌だった(もともとの名前を「裏窓」という)。レビューを書いて原稿料をもらったのはこれが最初。資料が散逸していて当時の原稿は(一部を除いて)残っていないが、編者分は74年11月から75年7月にかけて、隔月で5回掲載された。
同年、最初の編集。ネオ・ヌル(筒井康隆主催)「NULL」2号から7号(1977)まで。詳細はInfinite Summerを参照。
同年に『海外SF研究会(KSFA)』にも参画。KSFAの詳細はKSFA小史を参照。1975年
第14回日本SF大会SHINCONにスタッフとして参加。詳細は上記と同様Infinite Summerを参照。1977年
KSFA「ノヴァ・エクスプレス」(月刊海外情報、レビュー誌)の2号から編集に従事。この月刊誌は創刊だけ大野万紀編集だった。これは手書きオフセットから、タイプオフセットになって82年まで続いた。編者がかかわったのは20号(1978)まで。後半は、大森望や古沢嘉通、佐脇洋平らが執筆や運営・発送業務をしていた。
同年「SFセミナー」を主催。これは、東京に精神(?)が引き継がれて定着した。一部の記録に1978年開催とあるが、正しくは1977年10月である。1979年
「SF宝石」のブックレビューを担当。このブックレビューは、途中から「SFアドベンチャー」に移籍するなど、結局13年間も続くことになる。詳細はChecklistを参照。1981年
『SF年鑑』の編集を行う。タイプオフセット3段組230ページもあり、制作費100万を超えた。予算度外視ということで、非難ごうごう。KSFA崩壊危機説も出た(その後完売し、借金も返せましたが)。この『SF年鑑』は、ほぼ同様のスタイルで東京に引き継がれ、86年まで継続された。第1回ファンジン大賞「翻訳紹介部門」受賞。1982年
「ノヴァ・クオータリイ」の編集を行う。
1985年
SFフェスティバル、UNICONにスタッフとして参加。詳細はInfinite Summerを参照。
『最新版SFガイドマップ 入門歴史編』(サンリオ)の編纂に参加。1986年
第25回日本SF大会、DAICON5にスタッフとして参加。詳細は同上。
『最新版SFガイドマップ 作家名鑑編(上下)』(サンリオ)の編纂(安田均、編者の監訳)に参加。

もともとの原書(The Science Fiction Source Book,1984)は、SFの主な作品を解説すると同時に採点してしまうという、お遊びの要素が強い入門書だった。しかし、それを翻訳するとなると簡単にはいかない。あらゆる既訳書を調査し、整合を取る必要も出てくる(インターネット以前の時代だ)。分担共訳だったが、担当した翻訳者のばらつきも大きかった。SF大会の運営と並行して進めたため、管理面での無理もあった。ということもあって、黒丸尚に翻訳がよくないとの批判を浴びる。ただし、翻訳書の記載やリストアップなどをここまでした作家名鑑はあまりない。たとえば、完全を狙った『SFエンサイクロペディア』は、途中で挫折して刊行にまで至っていない。
1987年
この年結婚。前後数年のうちに、しかるべきSF関係者は大半結婚(関西を除く)。1990年
「ノヴァ・クオータリイ」ペーパー版の最終号(60号)を編集。Nova Quarterlyを参照。1992年
この年、Checklistがついに終了。編者のブックレビューは、その後「読書日記」形式で、THATTA(寺尾まさひろ主催)に掲載される。この冊子は、1983年から月刊で刊行されていた会員制ファンジンで、コピー・ホッチキス留めという簡素なもの。会員にはプロが多数参加する特異な形態となっていた。オープンではないため(一切の転載、 記載内容の他言は禁止)、門外不出の記事も飛び交った。というわけだかなんだか、リメイク版『SF入門』(早川書房)の年表にも創刊年が記載されている。1994年
週刊読書人のSFブックレビュー欄を担当(2年間)。Review Archivesを参照。1997年
本HPを開設。製作を始めたのは1月からだが、実際のオープンは8月ごろだった(と思う)。過去(当時、デジタル化されたファイルが残っていた1993年以前まで)に向かって増設した関係で、正確なスタート日付はもはや不明。83年から、13年続いていたペーパー版THATTAが停滞したせいもある(96年11月122号で休刊)。1998年
THATTA ONLINEが開設される。そちらにも寄稿開始。世界公開版なのでうかつなことは書けなくなった。2000年
本HPの記事、Infinite Summerが第19回ファンジン大賞「研究部門」を受賞。2005年
京都SFフェスティバル、「ブックレビュー?書評?その意味を問う」で司会を担当。初期の京フェスではパネル出演も珍しくなかったが、久しぶりに出演した。
2007年
京都SFフェスティバル、「ティプトリー再考」で司会。ティプトリー没後20年という意味で、古いファンが語るべき企画だったかもしれない。

本国の米国だけではなく、日本でもティプトリーには持続的な人気がある。その人気の一端は、数奇な人生そのものにある。ティプトリーの評伝(The Double Life of Alice B. Sheldon)は2007年のヒューゴー賞を受賞。このパネルもそれを踏まえての内容としている。
出演者は、大野万紀/水鏡子/米村秀雄/筆者。世界的な意義と同時に、日本での紹介の変遷を含めてテーマとした。1時間の企画時間では終わらず、合宿企画でも継続された。2008年
京都SFフェスティバル、「眉村卓インタビュー」でインタビュアー。昨年に続いての出演。眉村さん相手なので、やはりオールドファンが適切ということだろう。

日本におけるSF第1世代の大家である眉村卓には、ジュヴナイルSFの系譜と司政官シリーズという大きな柱がある。特に後者は、創元推理文庫での復刊以来再評価の機運が高まっている。DAICON7でも類似企画があったが、今回はそのデビューにまで遡って司政官に至る流れをインタビューした。時間的に苦しい分量になったものの、眉村さんの語りを知ってもらう意義を含めて、若いファンには好評だったようだ。
インタビューなので、出演者は筆者と眉村卓。