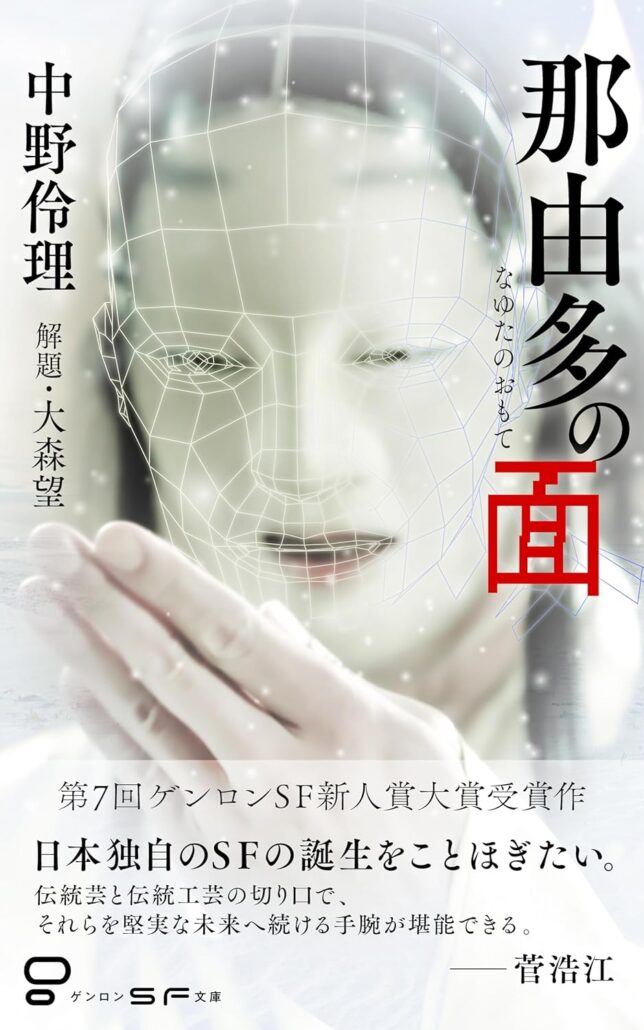
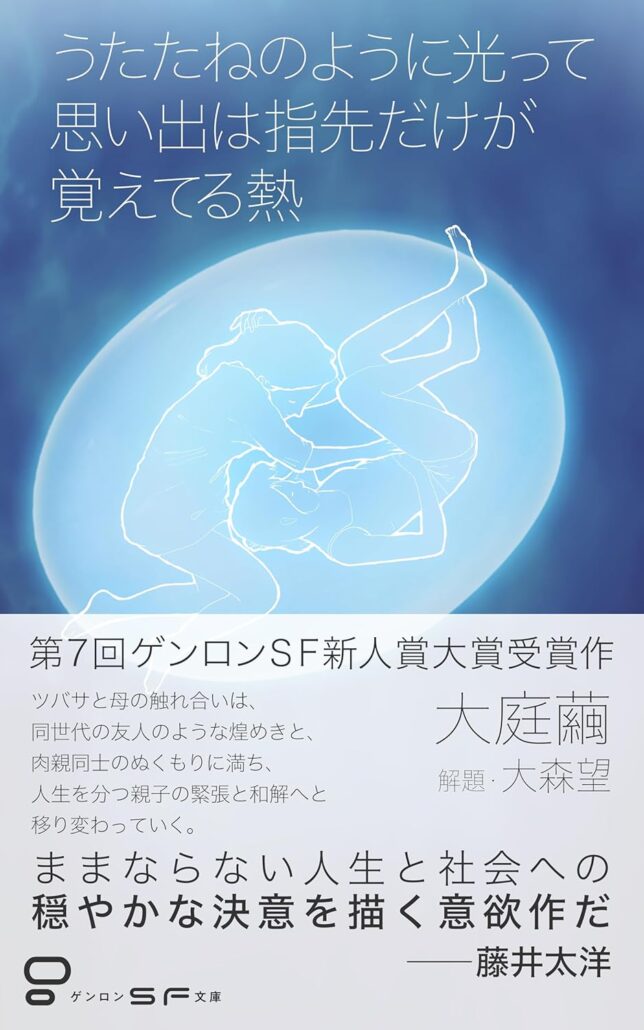
表紙:山本和幸
ゲンロンSF文庫ロゴ:川名潤
2024年の第7回ゲンロンSF新人賞大賞受賞作品(2作同時受賞)である。受賞してからまずゲンロン(17号/18号)に掲載され、その後出版(電子書籍)となるため少々時間がかかっている。伝統工芸である能面の制作とAIを結びつけた作品(父と子)と、昏睡状態の親の記憶との接触を描く物語(母と子)という並びは面白い。
那由多の面:文化財の修復を専門とする大学院生の主人公は、ある日幼い頃に母と離婚した父親の死を知らされる。唯一残されたアトリエには能面の下絵が残されていた。依頼を受けて制作する途上だったのだろうが、その絵には亡くなった母の面影が刻まれていた。
父に代わって面を作ろうとする主人公だが、依頼した能楽師はその要望を無下に拒絶する。曲目と合わないのか、何が問題なのか。表情データから人の感情を測定するセンサーとAI「ペルソナ」の助けを借りながら、主人公は課題に取り組んでいく。
この作品の場合、能という(マニアックな)世界に対する蘊蓄の部分と、AIやセンサー、脳科学に関する部分の融合が気になる。印象として、前者が重く後者がかなり軽い(読み手の興味にもよる)。主人公、父親、母親、能楽師と、人間関係の壁を切り崩すキーがテクノロジーなので、もう少し後者と前者の相似性を(たとえ虚構でも)明確化して良かったのではないか。著者はSF創作講座の常連(第4~7期生)で、伝統芸/工芸テーマを極めているようだ。
うたた寝のように光って思い出は指先だけが覚えている熱:出産を控えた主人公の母親は脳梗塞で入院している。意識はなく症状の改善は期待できない。亡くなってしまうかもしれない。しかし、新しい技術「うたたね」を利用すれば、昏睡状態でも母の記憶に入っていくことができる。母親が自分と同い年だった25年前の記憶に。
母親はホステスをしていた。25歳ではまだ身籠もってもいない。母から主人公は透明な幽霊のようにしか見えないが、眠っているときだけ(ホステスなので昼は寝ている)その体を借りて出歩くことができる。
この作品でも親と子どもを結ぶのはテクノロジーである。記憶へのダイブというかジャックインなのだが、確定した記憶=過去を(映画のように)見せるのではなく、歴史改変が可能なタイムマシンのように作用する。ただし、それはあくまで個人の記憶の範囲に過ぎないので、現実が変わるわけではない。選考会での議論を聞くと、この設定の整合性(解釈)についてさまざまな意見が出ていて面白い。結末が夢なのか現(うつつ)なのかは、注意深く読まないと分かりにくい。
- 『秘伝隠岐七番歌合』『水溶性のダンス』評者のレビュー
