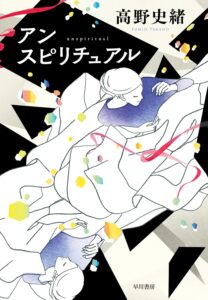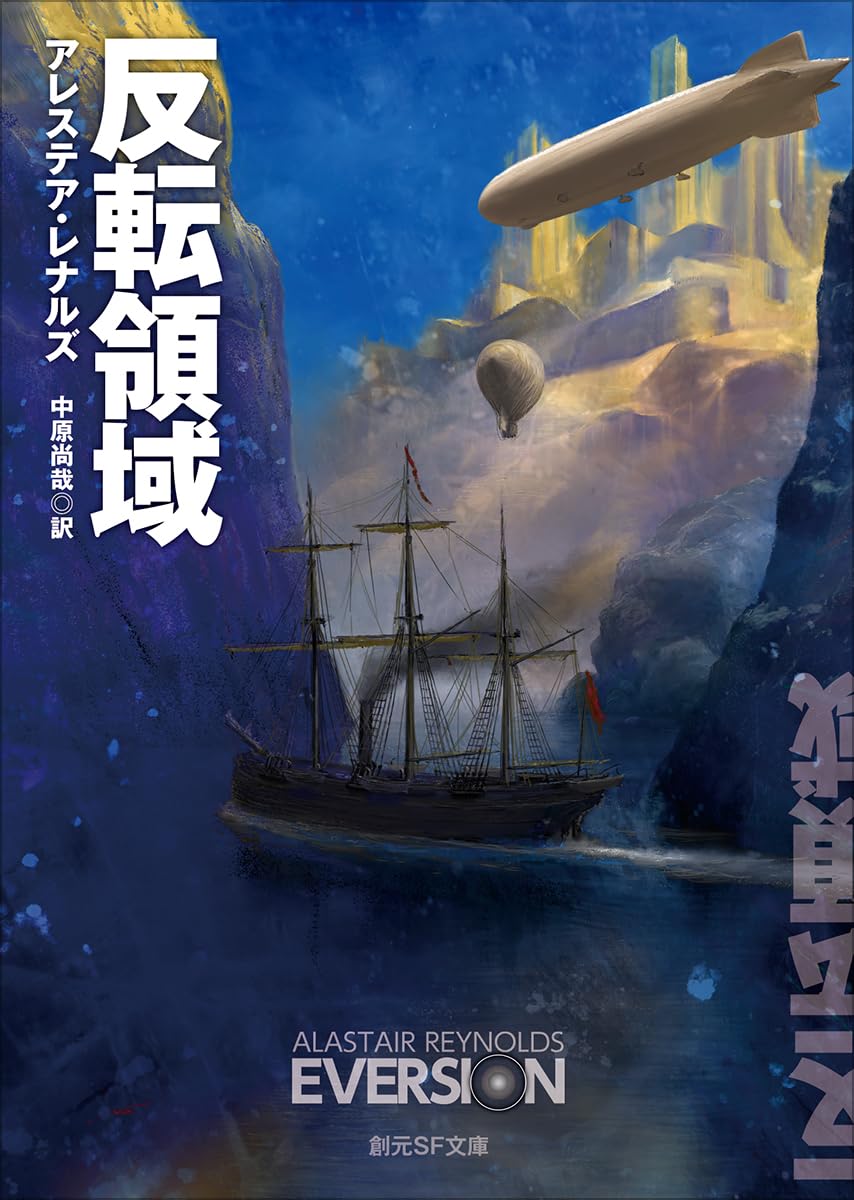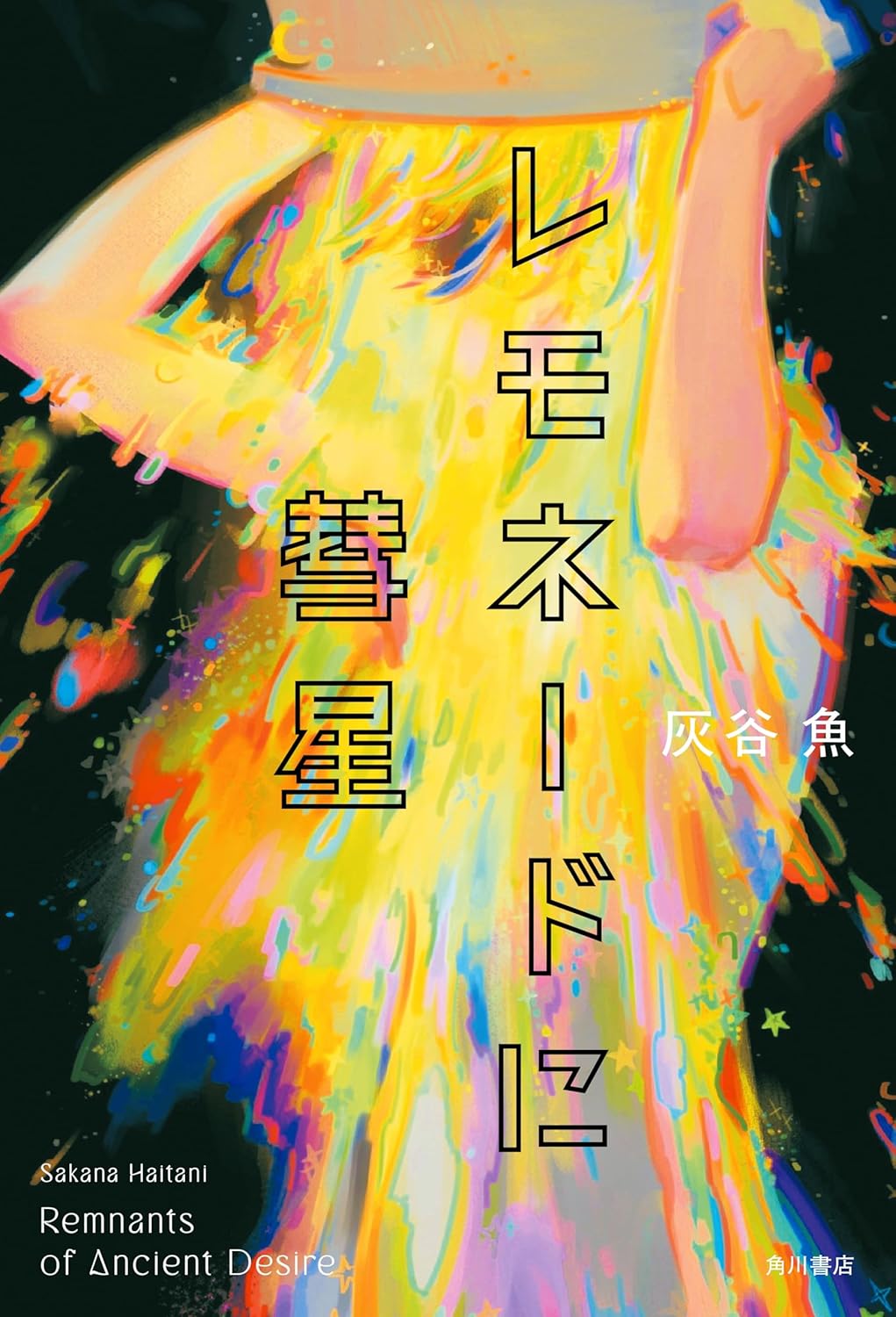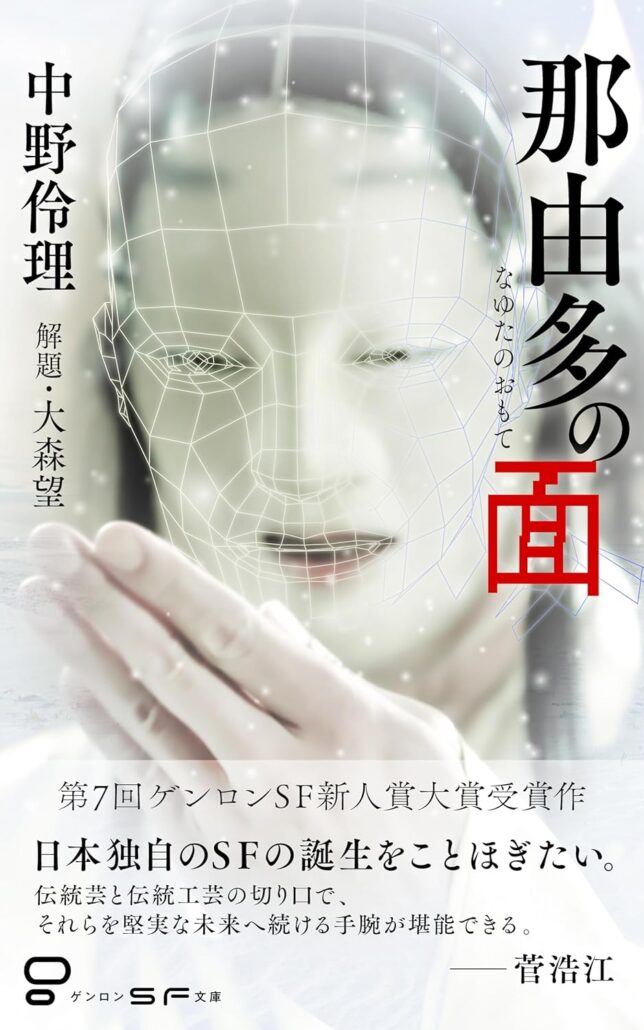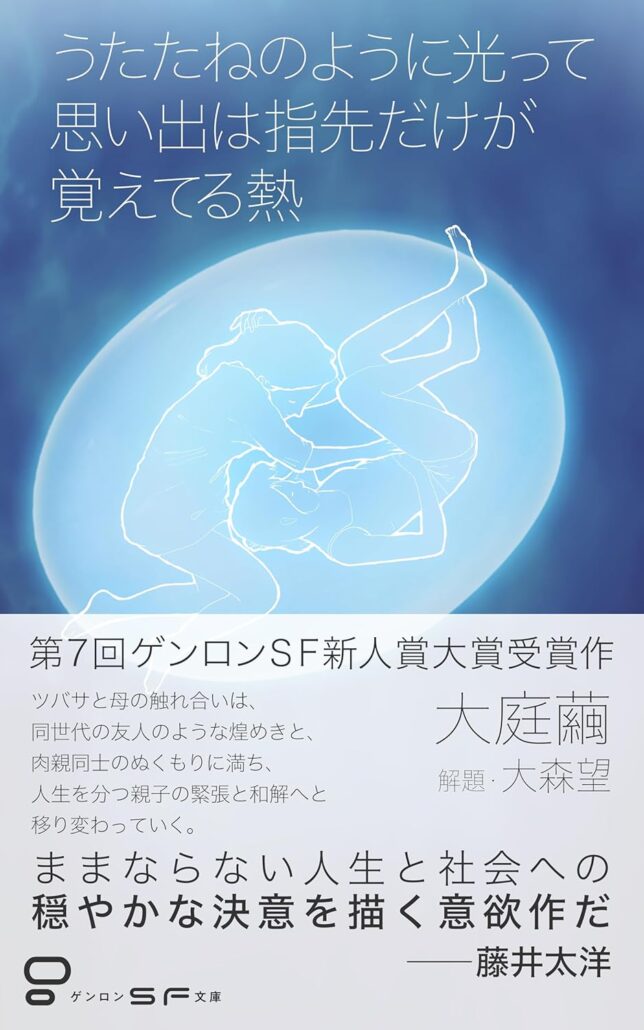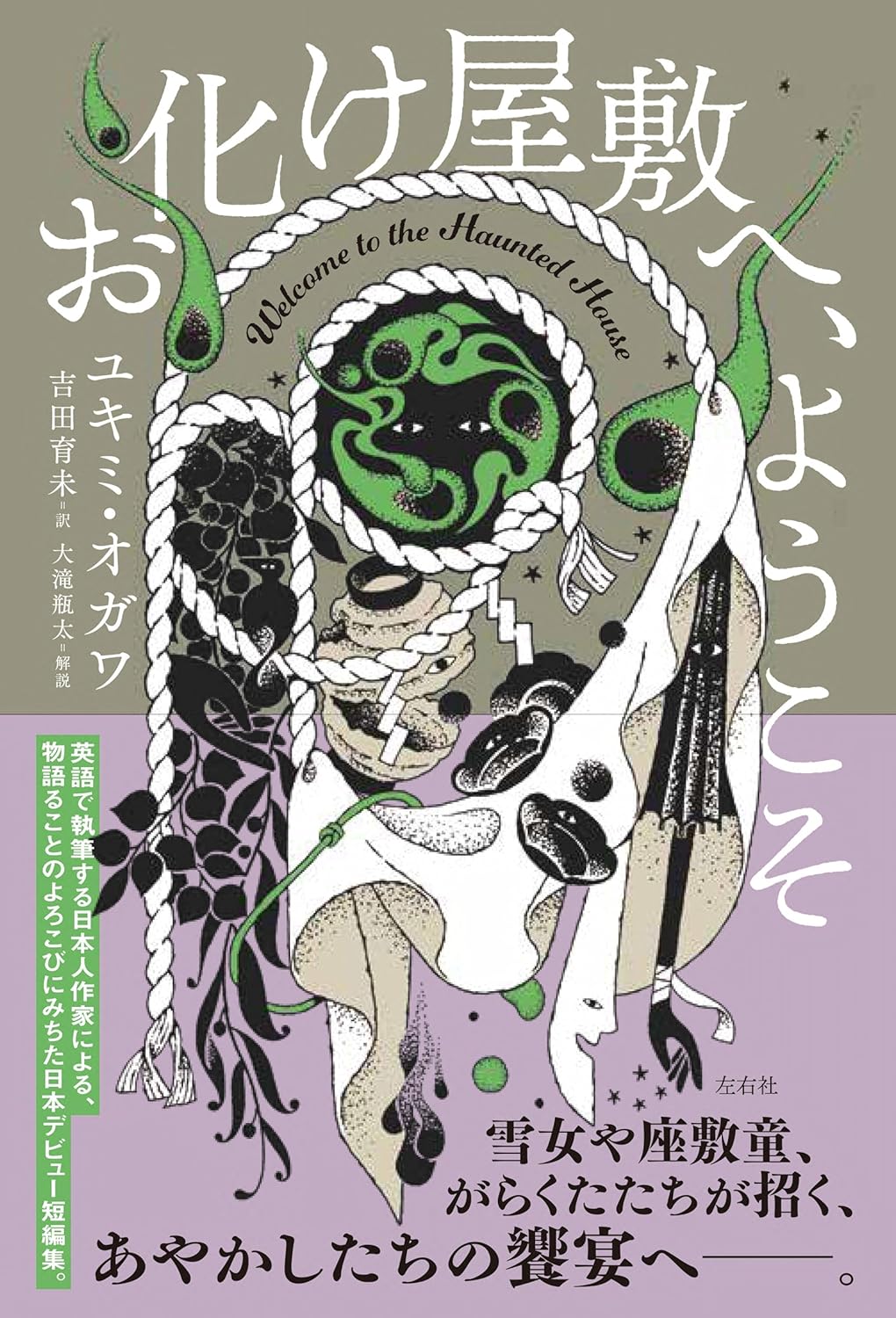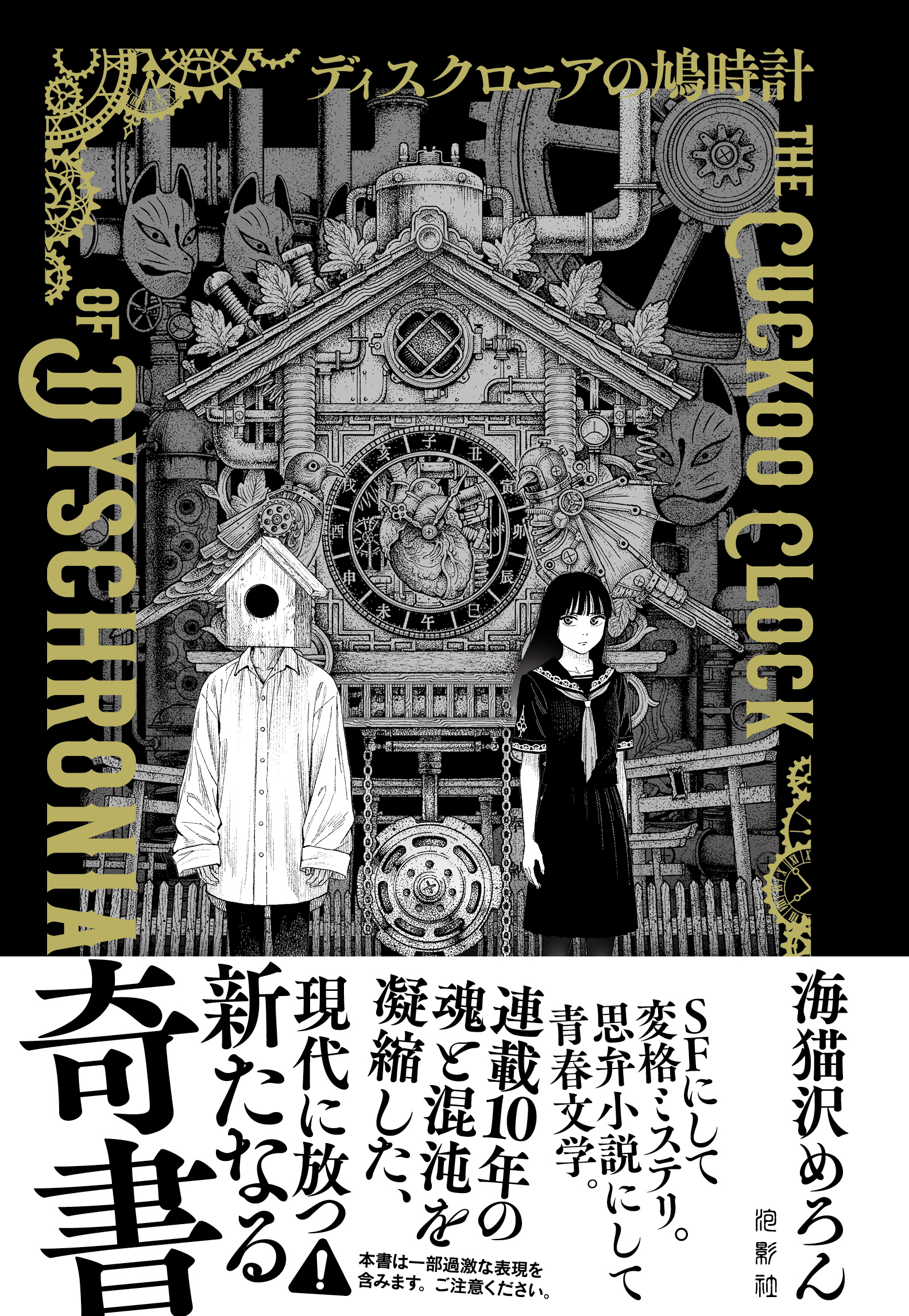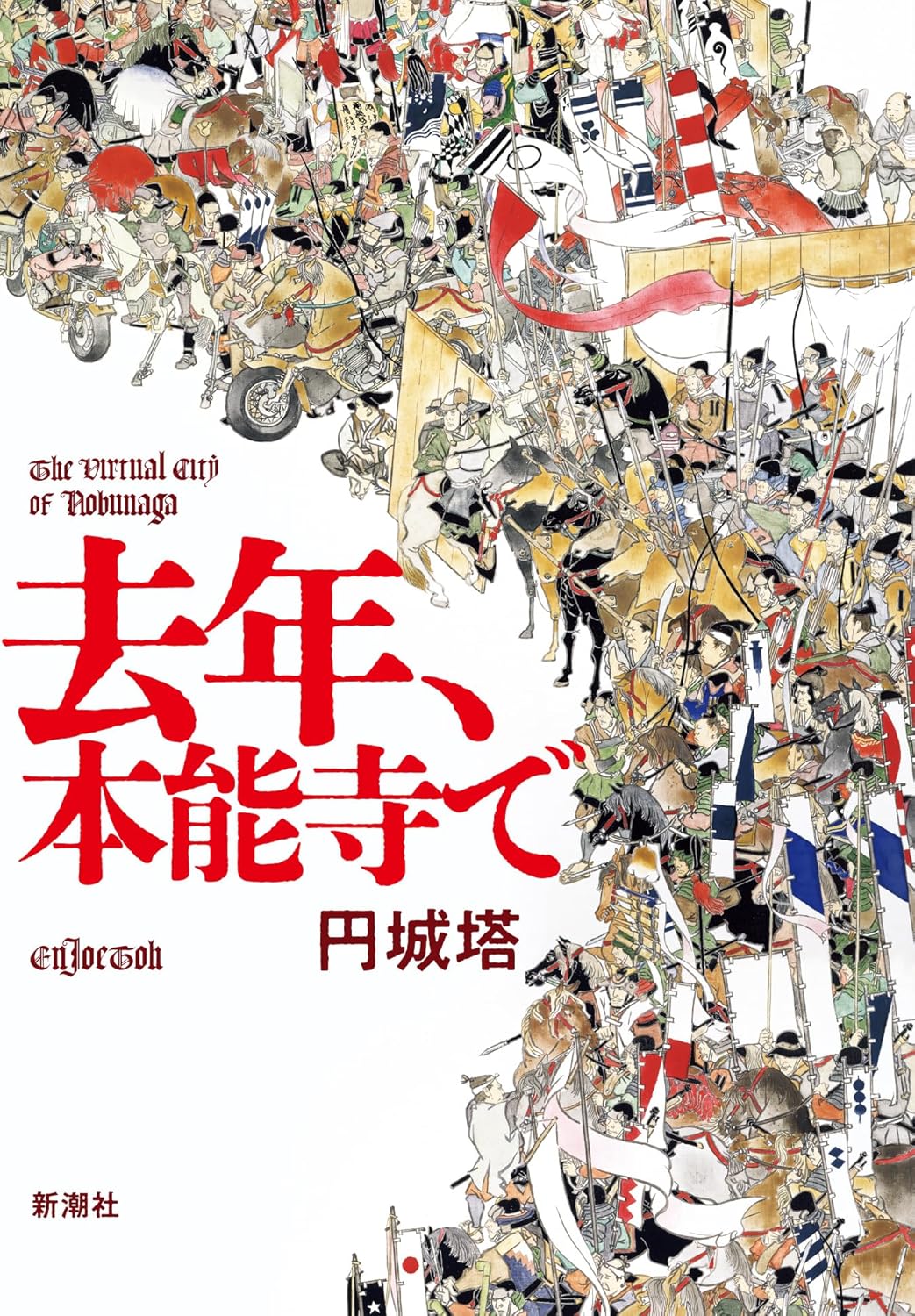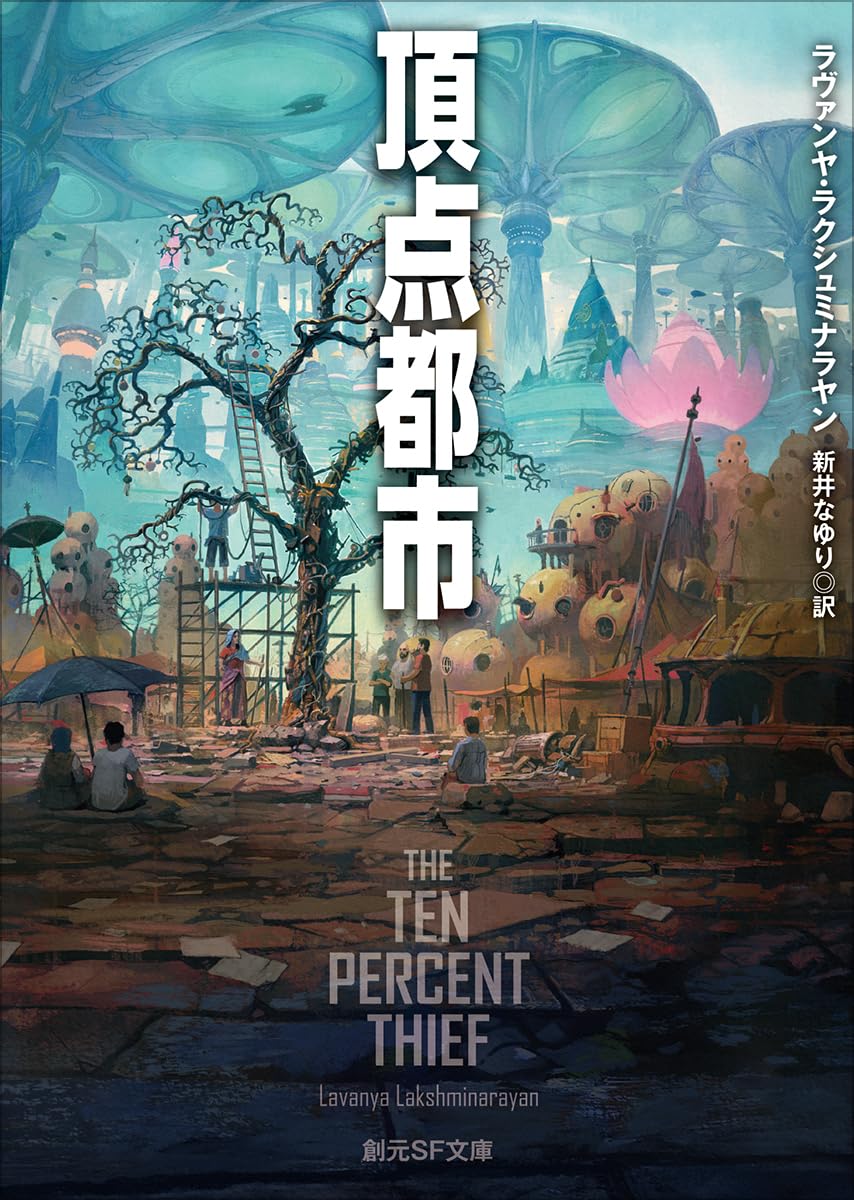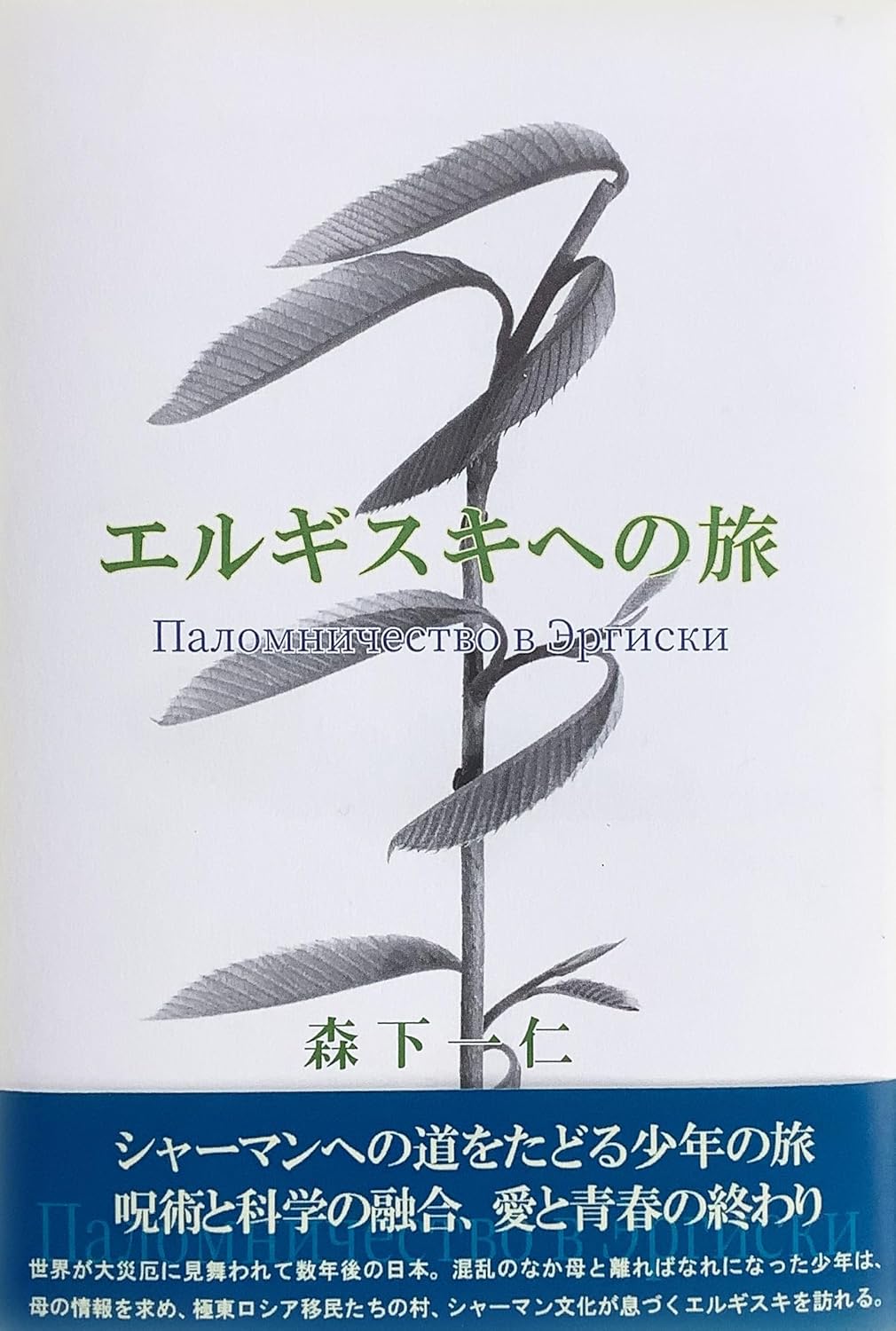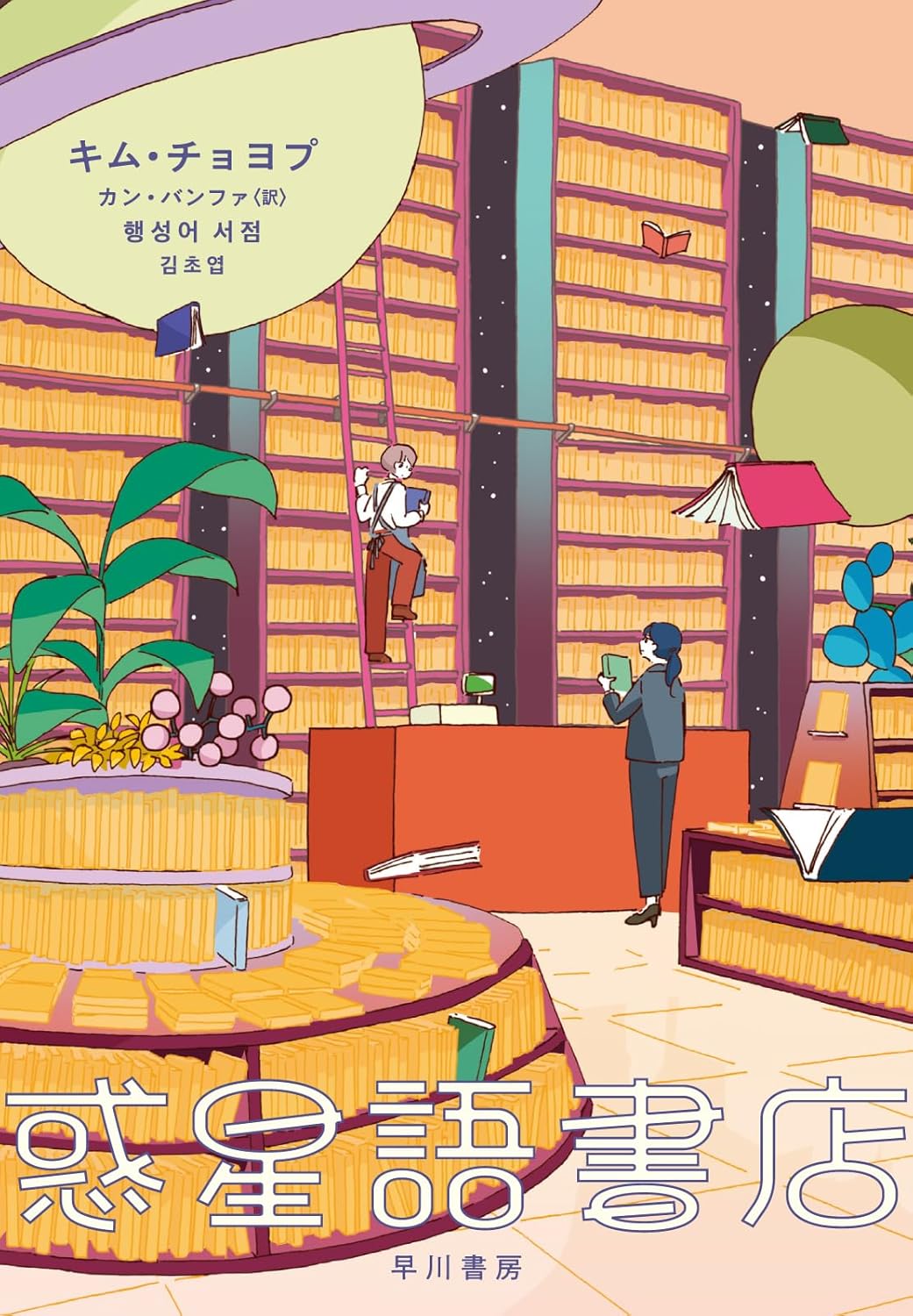『深淵のテレパス』で創元ホラー大賞を受賞しデビュー、朝宮運河選ベストホラー2024や、このホラーがすごい2025年版で国内1位を獲得した著者のシリーズ《あしや超常現象調査》第2弾である。好評のため、一回限りだった創元ホラー大賞も継続が決まっている。
特撮ヒーローとしてもて映やされたが、いまでは冴えない中年俳優の男が実家に帰ってくる。父親が脳梗塞で入院し、空き家になっていたからだ。しかし、住み始めると奇妙な現象が起こり始める。誰も居ないはずなのに、不規則で執拗なラップ音が聞こえる。そして常に感じる誰かの視線、父がつぶやいた「かがみのなかのおんな」。たまりかねた男は、噂に聞く超常現象調査に原因究明を依頼をする。
登場人物は前回の『深淵のテレパス』事件でおなじみ、調査チームの男女2人と、当てにならない超能力者(今回は2人)、元刑事の探偵らと主要メンバーは共通する。ラップ音自体はポルターガイストだろうと推察されるが、その現象を引き起こす人物(不安定な精神状態の少女など)は見当たらない。事件を追いかけるうちに不吉な呪いは拡散し、しだいに犠牲者を産み出していく。
前作から続く特徴は、ホラーを怪談(超自然のもの)で捉えるのではなく「超常現象」という自然現象として捉えようとする姿勢だろう。もちろん、すべてが科学で解明されるわけではないが、因縁以上の物理的な因果関係があるのだ。時間空間ともに予想外の方向にお話は進む。オカルトかサスペンスなのか、どちらともいえない曖昧さ(不安定さ)は、ある種の余韻となって楽しめる。
高野史緖の作家デビュー30周年記念作。この前の長編(連作を除けば)はベストSF2023で国内編1位となった『グラーフ・ツェッペリン あの夏の飛行船』で、並行世界の青春ものだった。本書は、それとは対照的なスピリチュアルをテーマとする異色長編である(もっとも、標題はそれを否定している)。
主人公には他人のオーラが視えた。相手の素性、表面に浮かぶ感情や、健康状態までが一目で分かるのだ。家庭はうまくいっていない。夫は不倫しており、自身もパートをしている新宿の整形外科で若い理学療法士に好意を抱いていた。だが、青年のオーラはまったく視えなかった。やがて、主人公は能力を生かした鑑定士(占い師)になり名を上げていく。
物語では主人公の能力がどこに由来するのか、また理学療法士が何ものなのかが明らかになっていく。著者の既存作品とは異なり、歌舞伎町(近未来?)の風俗描写や、占いなどの(いわゆる)スピ系に大胆に振ったように見えるが、後半の疑似科学に対する扱いなどはSF的な観点を残している。何れにしても新境地の意欲作といえるだろう。