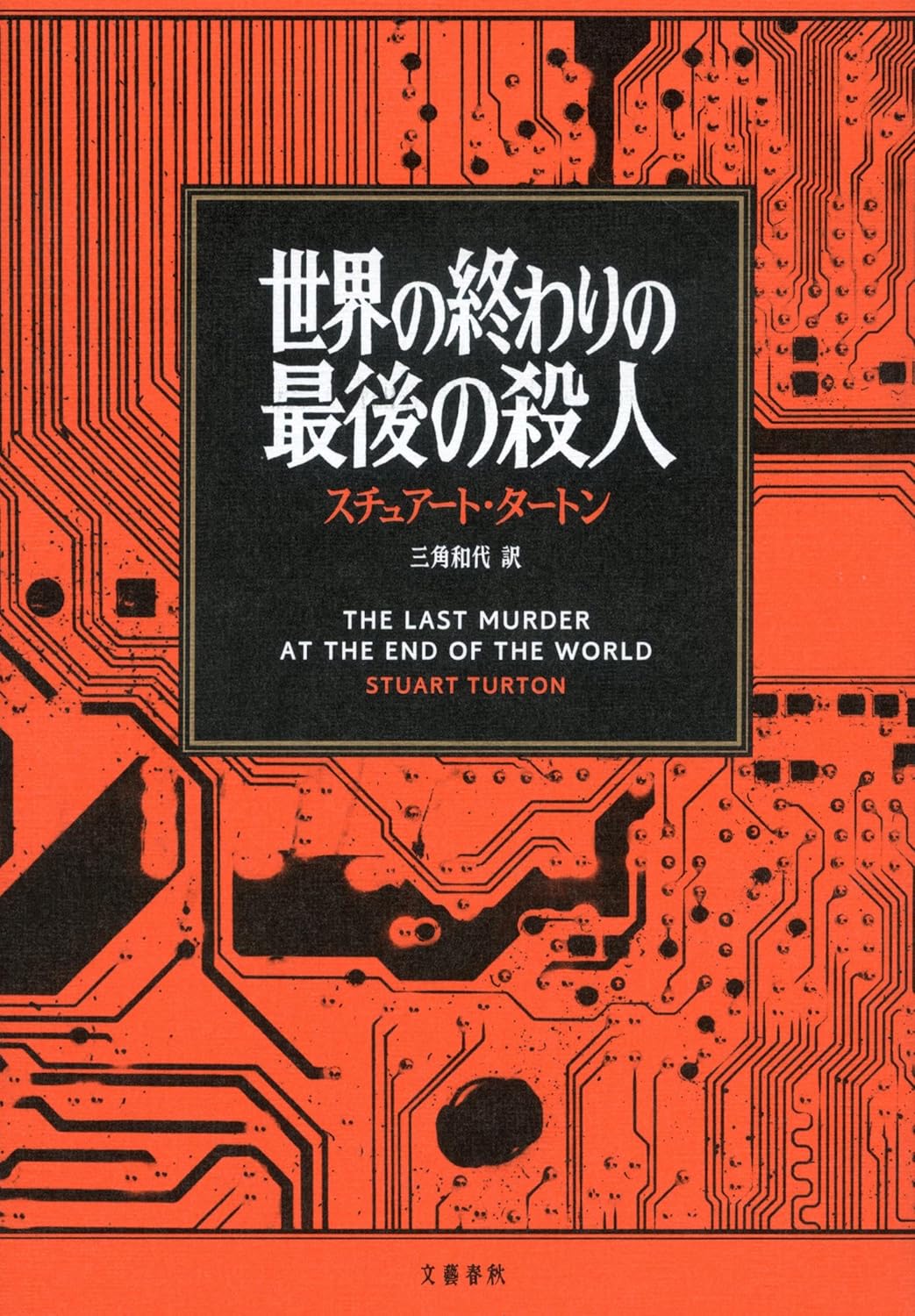
カバー画像:iStock/Getty Images
装幀:城井文平
著者は1980年生まれの英国作家。デビュー作のベストセラー『イヴリン嬢は七回殺される』(2018)は、新奇性のあるタイムループ×殺人事件ものとしてSFやミステリ界隈でも話題になった。本書はタートンの長編3作目にあたり、既訳の『名探偵と海の悪魔』(2021)を含め(広義の)クローズド・サークルもの3部作になるらしい。今回の舞台はアポカリプス後の島なので、確かに閉鎖された環境(第1作=時間の輪、第2作=洋上の船、本書=閉ざされた島)という点で共通する。
ギリシャのどこかを思わせる閉ざされた島、周囲にはバリアが張り巡らされ、死の霧が侵入するのを押しとどめている。世界はその霧によって滅び、百人余りの村人がかろうじて生き残っただけなのだ。村は科学者の長老たちによって支配されている。村人の頭の中には助言者エービイが棲み、仕事や睡眠の時間まで指図をする。そんな秩序が保たれた島で、ありえない殺人事件が発生する。
外見は若いのに村人の何倍も生きる長老たち、頭の中で聞こえる声、コントロールされた村の生活や山中に作られたドーム、このあたりの謎は物語の半ばまでで徐々に明らかにされる。そして、殺人事件の発生により、島の生活は一気に不安定化する。後半は、混乱の中での犯人捜しと犯行動機を探るミステリになる。SF的なガジェットを制約条件として巧く使い、不可解な殺人(=特殊設定)の謎を解きほぐしていくのだ。
ウィンタース『地上最後の刑事』に始まる3部作は、破滅が目前に迫る中でのミステリなのでよく似た設定といえるが、こちらは謎めいた破滅後(ポストアポカリプス)の世界に、たたみ掛けるように第2の破滅が迫ってくる展開が予想外で面白い。
- 『六つの航跡』評者のレビュー
