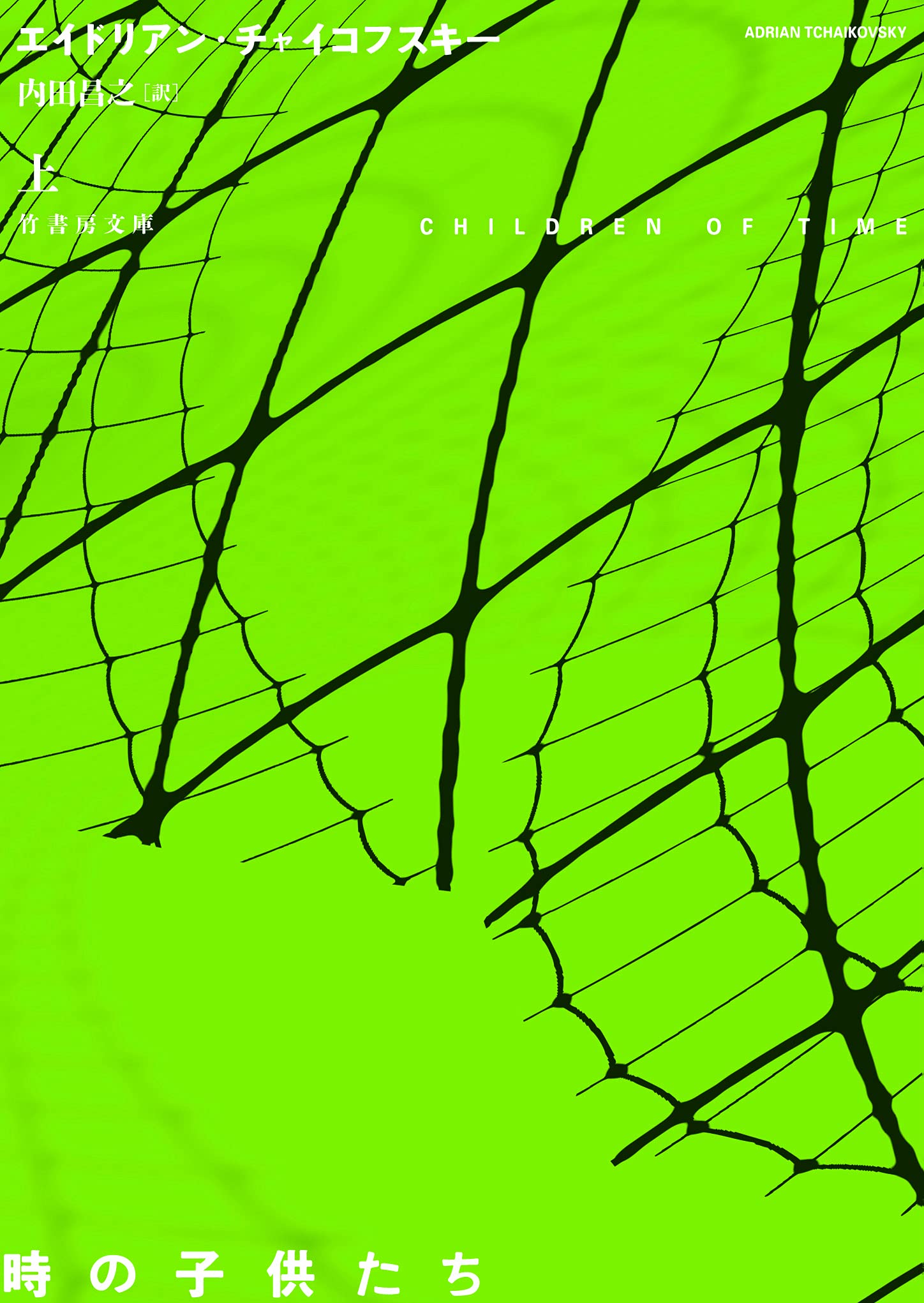
デザイン:坂野公一(well design)
著者は1972年生まれの英国作家。2008年のデビュー後は、主にファンタジイを書いてきた。本書は初のSF作品だが、2016年のアーサー・C・クラーク賞を受賞するなど高い評価を得たものだ。好評を受けて、すでに続刊の Children of Ruin が2019年に出ている(これは同年の英国SF協会賞を受賞している)。
地球は滅亡の危機にある、そう考えた人類は複数の異星をテラフォーミングする計画を立てる。完成までには時間がかかるため、人を送り込むのではなく、動物と知性化を促進するナノウィルスをセットで投入するのだ。だが、非人類を使う計画に異議を唱える過激派により実験ステーションは損傷を受ける。統括する科学者は軌道上で緊急避難的な冷凍睡眠に入り、地上では予期しない動物、蜘蛛たちによる文明が育まれようとしていた。
物語は2つの視点で語られる。1つは、原始的な部族社会から、やがて統一された文明国家へと進化していく蜘蛛たちの視点。言葉や文字ではなく、知識を遺伝子に直接書き込むことで伝承するため、同じ知識を持つ子孫は(世襲のように)同じ名前を持っている。もう1つは、滅んだ文明から脱出した世代宇宙船の人類の一団である。二千年に及ぶ恒星間飛行を冷凍睡眠で切り抜ける。登場人物は断続的に冷凍睡眠を繰り返しているので、二千年+数百年であってもほぼ同じメンバーが支配層になる。ピーター・ワッツ『6600万年の革命』でも登場したが、時間を超越するためSFでは時々使われる仕掛けだ。蜘蛛たちの進化は『竜の卵』的でもある。
お話は、蜘蛛社会と宇宙船の人間という二重の時間の流れで構成されている。人間社会は旧テクノロジーを維持する単独の宇宙船だけという設定なので、急速に進化する蜘蛛族に対して絶対的な優位性はない。登場人物は、(世襲とはいえ)前向きに生きる蜘蛛に対して、(いくら冷凍睡眠しても)次第に老いていく人間たち。となると、非人間であっても(擬人化されていることもあり)前者の方が魅力的だろう。著者は意図的にそうしていると思われる。世代宇宙船やテラフォーミングといった古典的なアイデアに、性差別といった現代的要素を交えたことで、かえって新鮮さを感じる作品になっている。
本書に出てくる蜘蛛は、日本の家の中でもよく見かけるハエトリグモらしい。手足が短くごく小さなクモ(イエバエと同サイズくらい)なのだが、しぐさに何となく愛嬌がある。続編はタコらしい。それにしても英米人はいつからクモやタコの愛好家になったのだろう。
