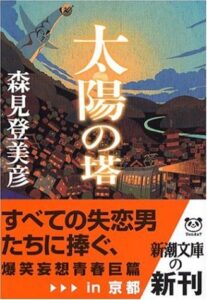今回のシミルボン転載コラムは森見登美彦です。著者のペンネーム「登美彦」は、神武東征軍の奈良盆地侵攻を阻んだとされる古代の豪族「登美長髄彦」(とみのながすねひこ)から採られていますが、著者が育った新興住宅街の地名にもなっています。そういう時間的空間的なギャップは、著者の作品のルーツでもあるようで面白いですね。以下本文。
1979年生。2003年京都大学在学中に書いた『太陽の塔』で第15回日本ファンタジーノベル大賞を受賞しデビュー。以降、自身が体験した京都での学生生活をベースに、誰も見たことのない魔術的京都を描き出す諸作品を発表する。2007年に『夜は短し歩けよ乙女』で第20回山本周五郎賞、2010年には『ペンギン・ハイウェイ』で第31回日本SF大賞を受賞する。
『太陽の塔』の主人公は京都大学の5回生で、振られた後輩の女子大生を“研究”している。彼女の行動を観察するため、執拗に追跡するのである。主人公は、万博公園にある太陽の塔の驚異に魅せられていた。しかし、その秘密を教えた途端、彼女は主人公への関心を失う。クリスマスを迎え、底冷えの中に震える主人公の周りには、京都の裏小路を走り抜ける叡山電鉄の幻影や、四条河原町で巻き起こる“ええじゃないか”の狂乱とともに、遥か彼方に太陽の塔が浮かび上がる。
本書の舞台は現実の京都の街並みであり、学生向けの古びた下宿である。主人公は犯罪者めいたストーカーなのであるが、エキセントリックというより憎めない間抜けな人物として描かれている。日常描写が非現実のファンタジイに見えてしまうという意味で、魔術的なリアリズム、マジックリアリズム小説の域にあると称賛された。この後も、著者の作品の多くは、キャラクタや設定を微妙に変えながら、同じ路線で書かれることになる。
アニメにもなった『四畳半神話体系』(2005)は、学生の四畳半での下宿生活にSF的飛躍を加えた作品となっている。今どき部屋貸しの下宿生活をする学生は少ないと思うが、京都では最近までそういう生活があたり前だった。
主人公を巡る人々は、卒業の見込みもなく浴衣で棲息する先輩、隠された趣味を持つ先輩のライバル、サークルの権力闘争で暗躍する後輩、飲むと態度を一変させる美人歯科技工士、変人の彼らをものともしない工学部の女子大生らである。彼らを結びつけるのは、『海底二万海哩』、熊のぬいぐるみ、大量発生した蛾の群れ、猫の出汁をとるというラーメン屋、占い師の老婆……なのである。一見脈絡がなく、舞台装置がひどく古臭いのに、いかにもありそうに感じさせるのは、舞台がディープな京都だからかもしれない。最終章は一転、ハインライン「歪んだ家」や筒井康隆「遠い座敷」を思わせるSFになる。
『きつねのはなし』(2006)は短編集である。表題作「きつねのはなし」は『太陽の塔』と同時期に書かれた作品で、鷺森神社近くの得体の知れない顧客と、一乗寺の古道具屋である芳蓮堂との奇妙な関係を描いている。著者の作品は、ほぼ同じ舞台(京都市左京区の北辺や木屋町、先斗町界隈)と同じ設定(共通の登場人物)を中心にして回っている。しかし、最初の『太陽の塔』がほとんどファンタジイの領域で書かれていたのに対して、続く『四畳半神話体系』は一歩現実に接近しSF的な展開を見せ、本書に至るとホラーの様相を見せる。同じものを書きながら、ファンタジイ・SF・ホラーという非現実の3つの位相を描き分けているわけだ。本書でも最初の短編で現れた怪異が、後に続く3つの物語で拡大され、ついに現実を覆い隠してしまう。

『夜は短し歩けよ乙女』は、2007年の山本周五郎賞受賞作。2017年4月には、先輩星野源、黒髪の乙女花澤香菜というキャストで劇場版アニメが公開された。発売以来のロングセラーで、この本が出てから森見登美彦ファンになる女性が急増したという、伝説の恋愛というか変愛(へんあい)小説である。デビュー作『太陽の塔』をリメークしたような作品にもなっている。
5月、先斗町で開かれた結婚パーティーの後、黒髪の乙女は大酒呑みの美人歯科技工士と、浴衣姿の正体不明の男と出会い、伝説の老人と偽電気ブランの飲み比べをする。8月、下鴨神社、糺の森で開催される納涼古本市では、老人が主催する我慢大会が密かに開かれる。そこでは、乙女の探す古本をかけて過酷な闘いが繰り広げられる。11月、大学祭で繰り広げられる神出鬼没のゲリラ演劇「偏屈王」と、取り締まる事務局との争いのさなか、乙女は緋鯉のぬいぐるみを背負って歩きまわり、パンツを履き替えないパンツ総番長やリアルに造られた象の尻と出会う。12月、クリスマスの声を聞く頃、京都は悪質な風邪の病に蹂躙されるが、その根源は糺の森に潜んでいた。
さて、本書は上記4つのエピソードからなるオムニバス形式の長編である。主人公は先輩、新入生で酒豪かつ天真爛漫な黒髪の乙女にほれ込むが、姑息なナカメ作戦(なるべく彼女の目にとまる作戦)でしか近づく手立てを思いつかない。『太陽の塔』では単なるストーカーだった主人公が、本書ではよりナンセンスの度合いを深めている。ファンタジイ=純愛を成就する男として、存在感を増しているのである。そして本書の前に書かれた『四畳半神話大系』や『きつねのはなし』でお馴染みのメンバーが多数登場する。実在の地名と実在の行事、喫茶店まで実名で出てくるのに、とても現代の京都が舞台とは思えない。京都の風景が偽物のように見えてしまう。竜巻に巻き上げられる錦鯉とか、ばらまかれる達磨、深夜の先斗町に忽然と出現する3階建ての叡山電車(もちろん3階建ての電車などない)、という謎めいたイメージの奔流にも驚かされる。
こちらもアニメになった『有頂天家族』(2007)では、妖怪めいたキャラクタが活躍する。京都では、古来より狸と天狗たちが、人間と入り混じりながら生きていた。彼らは巧みに姿を変幻させるため、人と見分けがつかないのである。そんな狸一族の名門下鴨家は、総領の父親が狸鍋で食われてしまってから、どこか抜けたところのある4兄弟たちが助け合ってきた。彼らは叔父の率いる夷川家と狸界の覇権を賭けて対立しているのだが、何せ狸のことであるから、阿呆な事件が次から次へと巻き起こっていく。
神通力を失い安下宿に逼塞した天狗、元は人間だが天狗の魔力を持つ妖艶な女性、年末に狸鍋を囲む怪しげな金曜倶楽部の面々。京都の街並みは変わらないけれど、前作までの京大生たちとちょっと違う魅力的なキャラクタが豊富に登場する。本書の中では「阿呆の血のしからしむるところ」というフレーズが各所に出てくる。ヴォネガットの有名なフレーズ「そういうものだ」は運命に逆らえない諦観から来るものだったが、根が陽気な狸たちは、何事も「阿呆なこと」として片付けてしまうのである。恐ろしい狸鍋でさえ、彼らにとっては阿呆な運命の一つに過ぎないのだ。
日本SF大賞を受賞した『ペンギン・ハイウェイ』(2010)は、舞台が京都から離れ、主人公も小学生になった作品だ。著者が育った奈良県生駒市の新興住宅地(大阪のベッドタウンが多い)をイメージし、そこにスタニスワフ・レム『ソラリス』へのオマージュを込めた、思い入れのある作品だという。
都心から離れた郊外の新興住宅街。主人公は小学校四年生で、常にノートを携行し、物事の観察に勤しむ論理的な少年だった。どんな疑問も書きとめ、読み返して意味を考える。最近のテーマは、住宅街を流れる川の源流はどこかを含む、町の詳細な地図作りだった。しかし、春が深まった5月、空き地に現れたペンギンの群れを見たときから、小さな世界はまったく別の様相を見せ始める。
主人公はえらい科学者を夢見ていて、感情的にならず冷静に物事を見ようとする。大人がみせる鼻持ちならない高慢さからは、まだ無縁だ。といっても子供なので、喫茶店のお姉さんに憧れる気持ちが、実はどういう意味なのか分かっていない。お姉さんは謎の存在なのである。ペンギンはどこから生まれてくるのか、森の中で徘徊する生き物は一体何か、野原に出現した「海」はどういう理屈で存在できるのか。それらと、お姉さんとは関係があるのか。夏休みの中で、謎が無数に渦巻きながら、彼らを飲み込んでいく。本書の場合は、主人公が「科学者」であるところがポイントだろう。巨大な(しかし、人類を揺るがすわけではない)謎に挑む小学生の科学者なのだ。
その後、森見登美彦は体調を崩ししばらく休筆していたが、朝日新聞連載を全面改稿した『聖なる怠け者の冒険』(2013)や、『有頂天家族二代目の帰朝』(2015)、直木賞候補ともなった『夜行』(2016)を出版して復活する。過去の作品を集大成したこれらを併せて、作家生活十周年記念作品(実際は13年だが)としている。特に最後の作品は、京都から離れた主人公が京都にもどってくる(しかし元通りにはならない)物語で、作者の心境を象徴している。
(シミルボンに2017年2月15日掲載)
このあとも森見登美彦は『熱帯』(2018)、初期のオールスターが競演する『四畳半タイムマシン・ブルース』(2020)、ややペースを落としながらも、今年になってから大部の『シャーロックホームズの凱旋』を出すなど筆力は衰えていません。