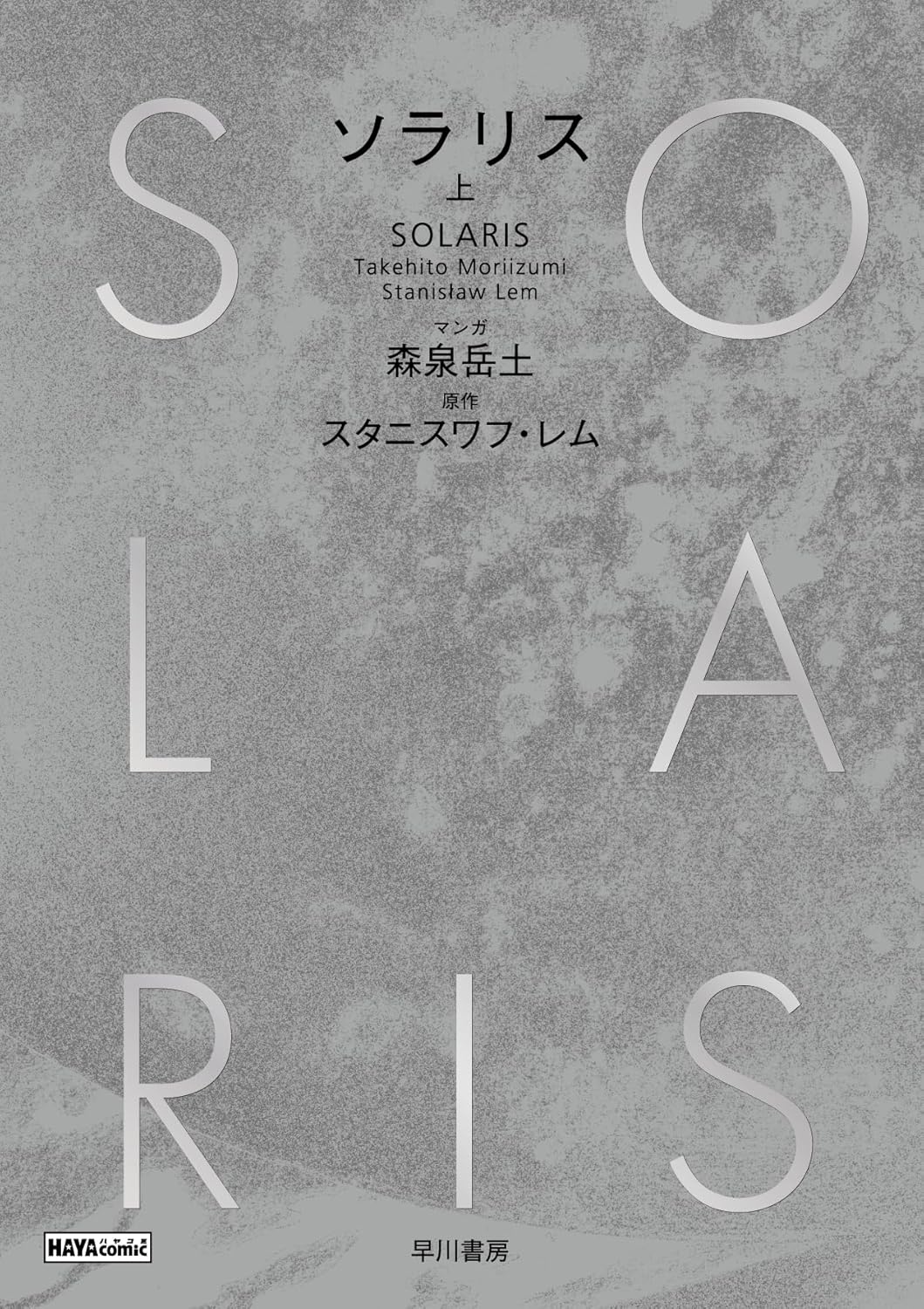写真:(C)Adobe Stock
第12回ハヤカワSFコンテストの優秀賞受賞作。この回では、カスガ(大賞)、犬怪寅日子(大賞)、カリベユウキと3人の受賞者が出たことになる。著者は1971年生まれ、10年ほど前の文学フリマ出品リストに名前が見つかるが、プロ出版はこれが初めてのようだ。最終候補に残った6人の中で、唯一の(他ジャンルを含むプロ経験のない)アマチュア作家である。
主人公は売れない女優、紹介を受けた怪しい仕事を受けざるを得ない立場にあった。それは、都内の巨大団地にまつわる怪奇現象を追うドキュメンタリーで、スタッフがレポーターと学生バイトのカメラマンだけというチープな陣容だった。だが、用意された団地の部屋に泊まり聞き込みを始めると、奇妙な人物が次々と現れてくる。楽器で殴られた老人、激情に襲われる管理人、男を棒で叩きのめす女、望遠鏡でこちらを観察するウェイトレス、屋上で踊る女子高生たち。
物語は都市伝説(人が消える団地)、怪談風に始まる。そこに不条理ホラー要素が加わり、伝奇小説の彩りが添えられ、最後はSFになって終幕する。背景にある「ギリシャ神話」との暗合が、徐々に明らかになっていく展開だ。どちらかといえば、下記リンクにある上條一輝や西式豊のジャンル・ミックス小説を思わせる。アガサ賞ならともかく、これまでのハヤカワSFコンテスト中ではかなりの異色作である。
選考委員の評価(抜粋)は以下の通り。東浩紀:日常ホラーとして始まりつつ、徐々に話が大きくなり壮大な世界観につながる。(略)いささか中途半端な印象も残すが、複数ジャンルを横断しようとした意欲は評価したい。小川一水:(略)怪物が遠近にちらつき、次第に近づいてくる描写が秀逸だった。(略)神話のエピソードに則った儀式的な行動で怪異を鎮める流れが、コズミックホラーとして面白い。神林長平:現実的な導入部から、すっと異世界の存在が身近になる書き方がいい。だがラスト(略)が、ほとんど夢落ちに等しく不満だった。菅浩江:前半はホラーで描写に凄みがあります。(略)後半はアクション主体で一気に安っぽくなっています。(略)70年代の新書ノベルのように、とにかく活力で引きこまれる作品。塩澤快浩:安定感のある語りとシュアな描写が素晴らしい。(略)小泉八雲まわりのプロットが弱い点だけが惜しかった。
さて、本作品はSFに収束する。ただ、述べられる理屈は科学的というより(コズミックホラーという評言もあったが)オカルトに近いものだろう。これはこれで面白みがあるものの、最近のSFではあまり見かけない大胆なスタイルと言える。
- 『深淵のテレパス』評者のレビュー