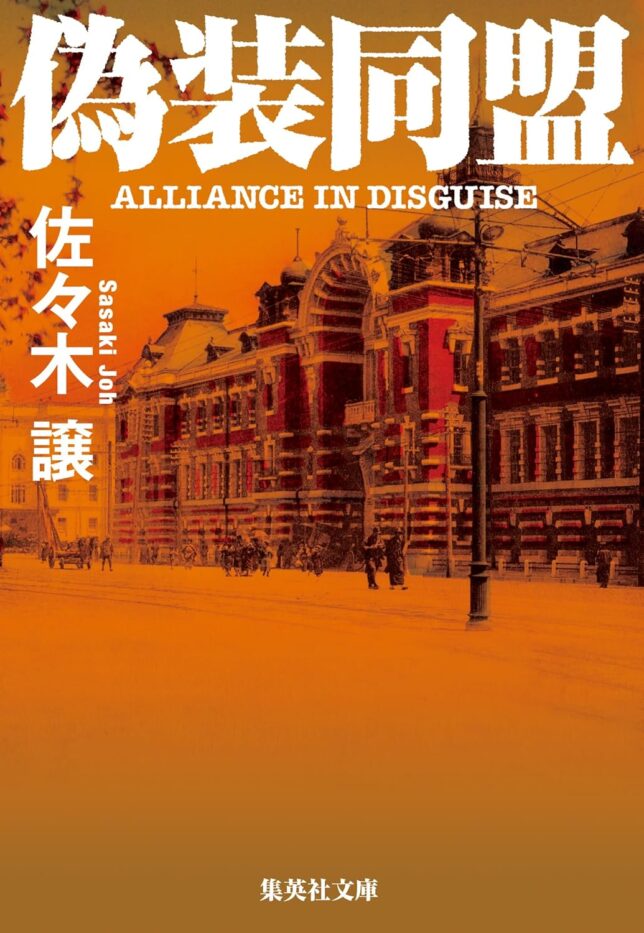

装幀:泉沢光雄(書影は電子書籍版)
『抵抗都市』から始まった《歴史改変警察小説3部作》が『分裂蜂起』で完結したので、前作『偽装同盟』と併せて紹介する。2018年から始まった3部作だが、『偽装同盟』は小説すばる2021年1月~8月連載、『分裂蜂起』は同誌2024年11月~25年8月に連載されたもので、合わせて7年間に渡る大作となった。他に、枝編とも呼べる『帝国の弔砲』などもある。
偽装同盟:1917年の3月、主人公の特務巡査は1人の女性が絞殺された事件を追っていた。洋装で外傷もなく売春をしているようでもない。ロシア人将校の犯行を疑わせる事件だったが確実な証拠がなかった。あったとしても統監府が絡むと問題がこじれる。折しも、大戦が膠着状態にあったロシア帝国で革命が勃発する(ロシア暦二月革命)。
分裂蜂起:1917年11月、川に浮かんだ死体の身元を探る主人公は、潜入捜査を試みる中で、ロシア資本の工場で起こった大規模な労働争議のただ中に巻き込まれる。ロシアでは評議会(ソビエト)を旗印に掲げる過激派のボルシェビキが政権を奪取(ロシア暦十月革命)、駐留ロシア軍も翌年には撤収することが決まり、日本社会は大きな変動期を迎えていた。
日露戦争敗戦11年後からの3部作で、旅順帰りで戦傷に苦しむ特務巡査(刑事に相当)の2年間が描かれる。民間の殺人事件を担当していても、その背景には日本やロシア政府の政治的な思惑が見え隠れる。本書の場合は、時代設定の稠密さが特徴だろう。事実上の占領下、地名もロシア化され、工場経営者や技術者、軍人など3万余のロシア人が在留する東京の風景。一般市民も、経済的に豊かなロシア文化に憧れる。ロシア語が氾濫するようになった東京界隈は(米軍占領下日本のアナロジーとはいえ)異国感が増して印象深い。
大正期、女子の労働はまだ限定的/抑圧的だったし、貧富の差は次第に大きくなり、労働争議は待遇改善を訴えるだけでも犯罪とされた。そういった社会情勢下、日本の高等警察(特高警察)やロシア保安課から干渉を受けながら、ストイックに自身の役割を貫く主人公がなかなか渋い。政治が背景に見え隠れしても、この3部作あくまでも警察小説なのだ。ロシアが去った後の日本は、しだいに元来た歴史へと収斂していく。また違う道もあるのではないかと夢想する。
- 『抵抗都市』評者のレビュー
