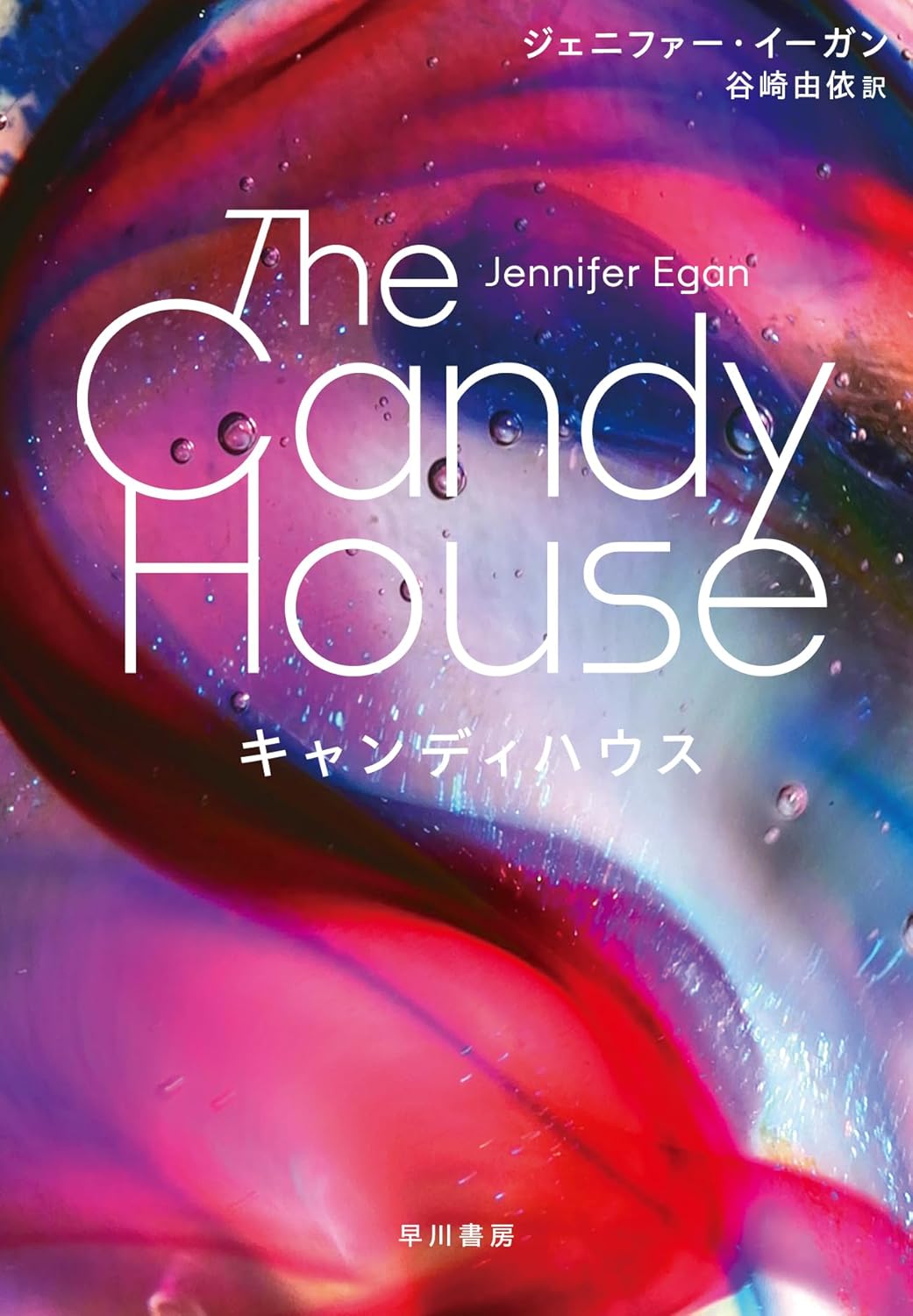
扉イラスト:中山晃子
扉デザイン:早川書房デザイン室
著者は1962年生まれの米国作家。ピュリッツアー賞をはじめ多くの文学賞を受賞したベストセラー『ならずものがやってくる』(2010)で知られる。本作は同書と設定や登場人物の一部を共有するが、未読であっても大きな支障はないだろう(訳者あとがき参照)。学生時代にスティーブ・ジョブズと付き合っていたという特異な経験があり、そのときのことを「テクノロジーは危険なものだと信じて疑わない私にとって(中略)しかし、彼と一緒にいたとき、私は純粋にユートピア的なヴィジョンを目の当たりにしていました」と述べている(Vogue誌でのインタビュー)。この危険さとユートピア感の対照は、本書にも大きく反映されている。
ベンチャー企業マンダラは、個人の記憶をすべて(アンコンシャス=無意識を問わず)外部に取り出す技術=オウン・ユア・アンコンシャスでネット社会を席巻する。外部化すれば(匿名にされていたとしても)あらゆる人のあらゆる記憶と、自分自身の意識していなかった記憶にさえ自由に接続/検索ができるからだ。記憶データを使って人々の行動予測をするカウンター(=計算者)がいる一方、ネットからの離脱を叫ぶエルーダーたちの集団モンドリアンも活動する。
創業者と子どもたち、マンダラの影響下にある社会で生きる三兄弟、技術基盤のアイデアを導いた人類学者(女性)と娘たち、元夫の音楽プロデューサーと異母兄弟たち、さらにその登場人物同士の結びつきなど、とても濃厚な人物像が描き出される。他人の記憶に入り込むというアイデア自体は、もう一人のイーガンや門田充宏をはじめ多数あるが、本書ではそれ自体がテーマではない。他人の体験をリアルに知るということは、人の一生を拡張し関係性を攪拌/混乱させる。そういう複雑な絡み合いが読みどころになる。
さまざまなスタイルが取り入れられていて、ツイッター小説風のスパイもの、SNS/SMS的なメッセージが往復するエピソード、人類学者が考えた人間行動のアルゴリズムとか、SFめいたカウンターの説明もある(あまり科学者的でもエンジニア的でもないが、まあそれはそれ)。作者の考える人を介したテクノロジーの陰陽が(人間関係が複雑すぎるきらいはあるものの)多様に愉しめる作品だろう。
- 『未来』評者のレビュー
