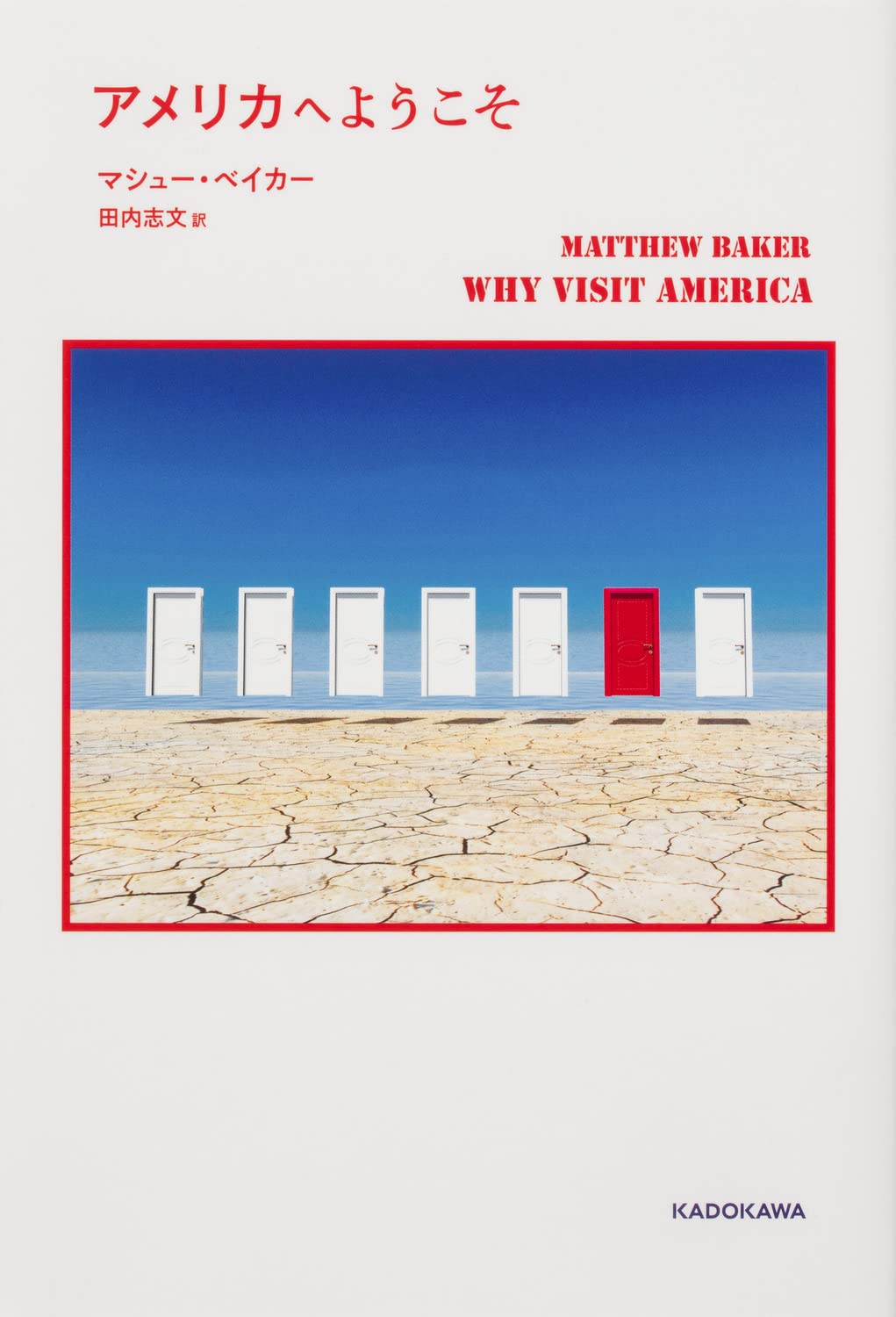
ブックデザイン:川添英昭
著者マシュー・ベイカーは1985年生まれのアメリカ作家。美術学修士取得後に、さまざまな文芸誌や批評誌(オンライン含む)に実験的な短編を発表し、Variety誌の10人の注目作家に選ばれたこともある。プロフィール写真ごとに髪型をドラスティックに変えるなど、ちょっとクセのありそうなアメリカ純文学の人だ。ただ、発表した媒体の中にはWebジンのSF専門誌Lightspeed Magazineがあり、D・ガバルドン&J・J・アダムズの『年刊SF&ファンタジー傑作選』に「終身刑」が採録されている。日本の若手純文作家も同様だが、SF的アイデアを取り入れることに何らためらいはないのだ。版元の紹介文中で本書が「SF短編集」とキャプションされるのも、そういう理由によるのだろう。
売り言葉(2012)辞書編纂者の主人公は、盗用防止の幽霊語創作を仕事にしている、だが、姪の虐めに憤ったことから、当事者の高校生のストーカーを始めるようになる。
儀式(2015)母親の儀式が済んだあと、すでに期限が過ぎている伯父を説得しようとする。しかし周囲の顰蹙を買いながらも、伯父はかたくなに受け入れない。
変転(2016)過度に保守的ではなく世間並みに良識を持つ家族だったが、体を失うという主人公の選択には誰も賛成してくれなかった。
終身刑(2019)刑罰により記憶から過去がすべてが失われていた。日常生活を過ごすには支障はなかったものの、家族すら見知らぬものになった。自分は何をしたのか。
楽園の凶日(2019)ひどい一日が終わり、愚痴を話す相手もいないとわかると、彼女は郊外のガラスドームに覆われた生物園に車を走らせる。
女王陛下の告白* 主人公はお城のような大邸宅に住み、家族は買い物に明け暮れ、部屋はモノで溢れている。その結果、レシオは非常識な高さになっているのだ。
スポンサー(2018)結婚式の寸前になって冠スポンサーが倒産してしまう。このままでは式が立ち行かない。やむを得ず、不仲だった大金持ちの知人に泣きつくが。
幸せな大家族* 保育所から赤ん坊が誘拐される。警察は犯人の動機を知るため人物像を明らかにしようとするが、誰もがあいまいな答えしか返さない。
出現(2013)レストランの駐車場で「不要民」を待ち伏せし、三人を車の中に押し込むと州境へと走り出す。奴らが出現してからもう13年が経っていた。
魂の争奪戦(2020)生まれた赤ん坊がすぐに死んでしまうという現象が頻発する。魂の数が上限に達したからだ、とする説が信じられている。
ツアー* カルト的人気を誇る「ザ・マスター」がやってくる。そのギグに参加するためには莫大な費用とくじ運がかかるが、主人公は奇跡的に両者を手に入れられた。
アメリカへようこそ(2019)地方の田舎町が突然独立を宣言し、元の国名のままアメリカと名乗る。オールド・アメリカはその理想をすべて失ったからだ。
逆回転(2011)生まれたばかりの主人公が感じたのは完全な絶望だった。そして、ポケットから数字の書かれた謎の紙切れがでてくる。
*:未発表作または書下ろし
全部で13編を収める(著者が2009年から書いた短編の4分の1)。すべての作品に奇想アイデアが含まれる。筒井康隆『銀齢の果て』風(あるいは成田悠輔風)、意識のアップロード、死刑に代わる記憶抹消、『男たちを知らない女』の世界、裏返された大量消費社会、過度な広告化、育児の公営化、非人類の難民、井上ひさし『吉里吉里人』的独立秘話、時間の逆転などなど。
ただし、これらの(もはやありふれた)アイデア自体は目的ではない。登場人物をクローズアップするための「特殊設定」に使われている点が、現代SFや文学と共通する特徴といえる。たとえば「変転」では、コンピュータにアップロードされる主人公よりも、うろたえ動揺する家族と母親がテーマとなっているし、「終身刑」でも受け入れる家族と主人公との距離感が読みどころとなっている。
特有の文体、数ページにもわたって段落なしに続く容赦のない描写が効果を上げている。「ツアー」などでは、それが対象を変えながら何段階も執拗に続いて圧巻だ。物語に説明を付けず、唐突に断ち切ってしまう終わり方は、エンタメには少ない純文的なミニマリズムだろう。また「出現」や表題作には、アメリカ的な社会問題が織り込まれている。「逆回転」もよくある時間の逆転を描くが、その先に現れるものはまさにアメリカといえる。
- 『異常』評者のレビュー
