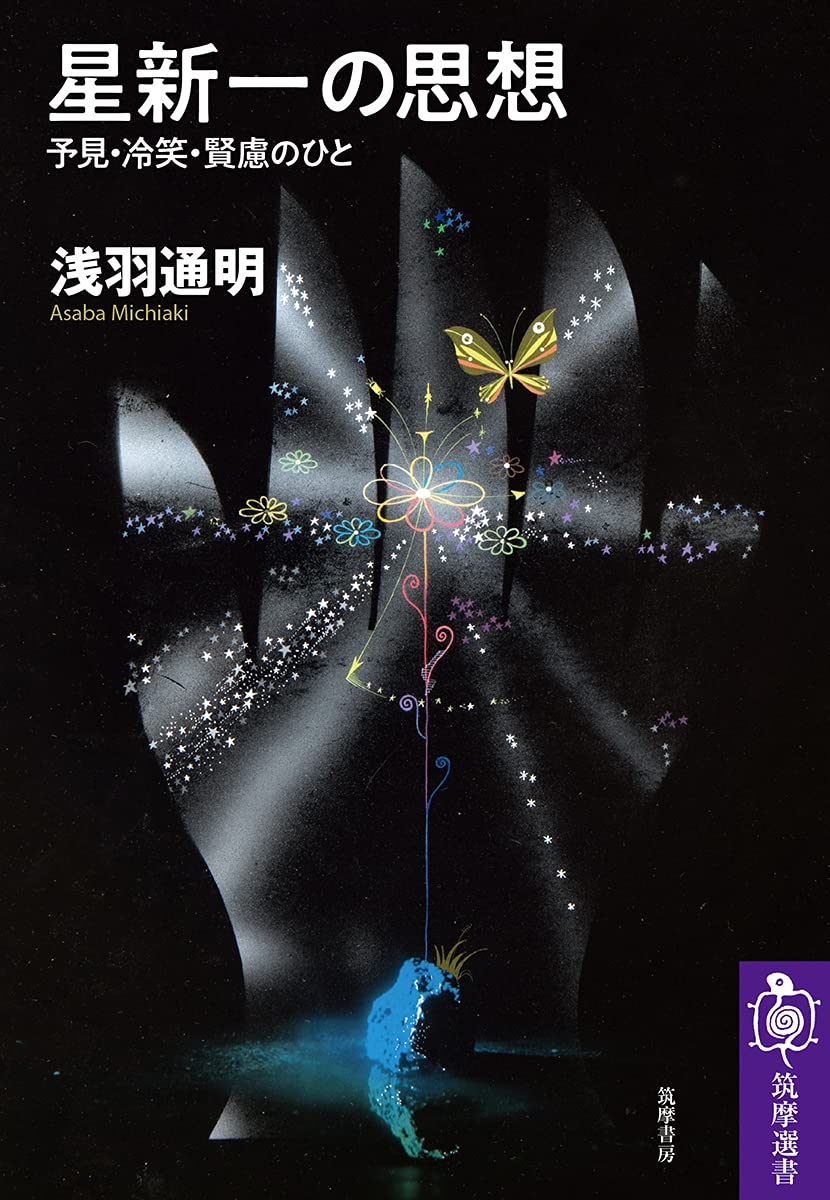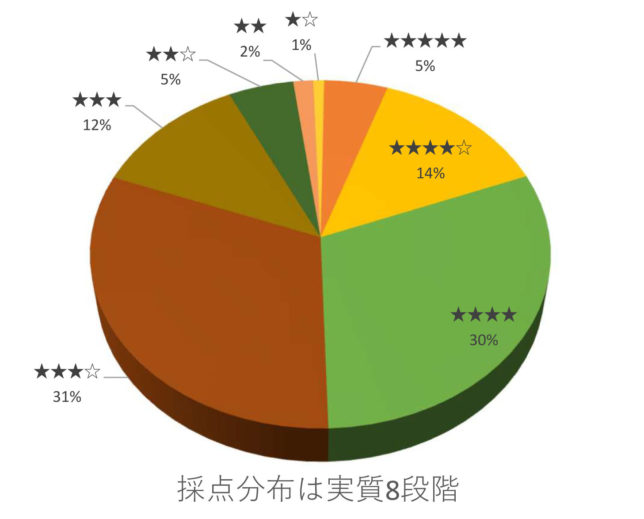以下は『豚の絶滅と復活について』巻末に収録した、津田文夫解説を全文掲載したものです。
本書『豚の絶滅と復活について』は著者岡本俊弥のSF短編集として五冊目にあたる。
最初の短編集『機械の精神分析医』が出たのが、二〇一九年七月(奥付)なので、二年と二ヶ月で第五短編集発刊の運びとなったわけである。ということは、このペースで行けば五年足らずで一〇冊、一〇年後には二〇冊もの短編集が出ているという計算になる。そんなわけないだろ、とツッコまれるかも知れないが、いやこの著者なら可能性は充分と思わせるところが、岡本俊弥という作家の恐るべきところなのである。それは、先に出た著者の第四短編集『千の夢』の解説で、水鏡子が述べているように
六〇代という人生の折り返し点で培ってきた個人的及び俯瞰的な世界と制度と将来への知見、そうした公的私的な景観を、品質管理を施した基本四〇枚前後のSF小説の枠組みに落とし込んでいく
ことができる作家だから。とはいえ今後のことは、著者/神のみぞ知る、なのだけど。
さて、著者の作風については、第三短編集『猫の王』の大野万紀氏の解説に
作品の特色は、その静かでほの暗い色調と、工学部出身で大手電機メーカーに勤めていた経験を生かした、科学的・技術的、あるいは職業的にリアルで確かな描写、そしてそれが突然、あり得ないような異界へと転調していくところにあるだろう
とあり、すでに本書収録の作品群を読んだ方にはとても納得しやすいのではないかと思うのだけれど、もちろんそれだけが岡本作品の特徴ではない。もっとも水鏡子解説のように
意外であったのは、SFの最先端や周辺文学を読み込んでいるはずの著者であるのに、落とし込む先の小説形態がノスタルジックなまでに第一世代のころのSFの骨組みに近しい印象があること。はっきり言ってしまうと、眉村さんの初期作品群を彷彿とさせる
といわれると、大野解説との落差があまりにも大きく、ちょっとあたまのなかに「?」が浮かんでくるが、これは水鏡子先生お得意の超絶SF論ワザなのであまり気にしない方がいいでしょう。
ここで三番目に登場した解説者(筆者のこと)は、作家岡本俊弥の作風をどう受け止めているかを書く前に、著者との関わりを書いておこう。
第三及び第四短編集の解説者は、それぞれ著者の出身大学のSF研究会の先輩方で、著者とはそれ以来ほぼ半世紀近いあいだ定期的に集まってさまざまな話をしてきた人たちである。
一方、筆者が京都の私立大学に入ったのは一九七五年で、当然のごとくSF研に入りその夏初めて第一四回日本SF大会(筒井康隆/ネオ・ヌル主催のSHINCON)にSF研の仲間とともに参加した。このSF大会で水鏡子、大野万紀、著者の三氏は筒井康隆が発行していたファンジン『ネオ・ヌル』関係者(著者は編集長)でもあり大会スタッフとして参加していたのだが、当時はまったく三氏とは面識がなかった。しかしわがSF研メンバーとして筆者は珍しくペイパーバックでSFを読むタイプだったことで、熱心に英米SFを読んでいる人たちが毎週日曜日に集まる大阪の喫茶店へ、先輩が連れて行ってくれたのである。そこで初めて著者や大野万紀や水鏡子と知り合ったのだった。当時この集まりには多いときで十数人が参加していた。これが後に関西海外SF研究会(KSFA)となる。新参の筆者は当然集まりの中で若年だったが、最年長者でも三〇歳そこそこだったことを思うとまだSFファン層自体が若かった時代といえる。まあ筆者は最若年とはいえ浪人していたので、水鏡子、大野万紀、著者、筆者はそれぞれが一歳違いである。
大学を終えて田舎に帰ったあとも、KSFAの活動やイベントに参加していたこともあり、また二一世紀に入ってからは大野万紀主催のTHATTA ONLINEにも読書感想文もどきを定期的に投稿することで、やはり四半世紀近くの付き合いが続いている。ただし、家族が増えて以来は年一、二回集まりに顔を出せればいいような具合である。すなわち、前二作の解説者たちとちがって筆者には著者に関する個人的な情報があまりなく、作家としての著者に関しては一読者に近い立場にあるということなる。
ここで著者の作風の話にもどると、本書をふくめ五冊の短編集に収録された四二編とその四二編の原型を含め六〇編以上の作品を読んできて、まず感じるのは著者の文体の冷静さであろう。著者の作品は基本的に科学技術にかかわってストーリーが構成されるいわゆるSFの最たるものであるが、その叙述法は科学技術/SF的アイデアの核はさまざまなものがありながら、ストーリーの語り口に一定の冷静さが常にある。それは最終的に物語の話者が狂気に侵されるような作品でも変わらない。大野万紀解説いうところの「ほの暗い色調」である。それはまた水鏡子解説にある「この数年の毎月生産される短編のその静かで五年前も最近作も変わらぬ安定感」をもたらすというのと同じかもしれない。
そして短編SFとしてその結末がもたらす印象は、サタイア/風刺的なものと不気味なもの/ホラーへの傾斜であろう。もちろんそれだけでは語れない作品も多数あるが、サタイアや不気味な風景を感じさせることは短編SFの得意とするところなのである。著者の短編としてはおそらく一番多いと思われるこのタイプの作品が、冷静な語り口と相まって、水鏡子解説いうところの「岡本地獄」の印象を引きだすのだろう。
しかしなんと云っても岡本SF作品の最大の特徴は工学部出身者で長年電機メーカーの研究所に籍を置いたその経歴からうかがえるとおり、バリバリの理工学系SFになっていることだ。これは根っからの文系SF読みである筆者がもっとも強く感じる岡本SFのトレードマークなのである。そのことは本書収録作の印象を並べてみて考えてみよう。
冒頭の「倫理委員会 Ethics Committee」は、最初に出てくるカタカナで呼ばれる四人の登場人物がネットメディアのフェイク度を議論する場面から「倫理委員会」の意味は了解され、その登場人物が分野別に特化したAIであること、というところまではなんの違和感もなく読めてしまうが、人間である語り手がAIの議事録を書いているというところからこの作品のSF性が生じる。AIたちの議論を書き残せるとはどういうことかに思いを巡らせば、そこに著者が半世紀近く前の大学時代からコンピュータを操っていた経験から、人間とAIの違い/落差を読み手に納得させる小説のアイデアが立ち上がる。人間とAIの線引きの鮮やかさに著者の理工学系的思考が見える。
続く「ミシン Sewing Machine」は、「ミシンが頭に被さり、針を打つ」というホラータッチの一文から始まるけれど、あとの文章を読めば、これは最先端技術による極小の針と糸を使った手術のようだと分かる。物語は「コロナ禍」のソーシャル・ディスタンス/テレワーク化が極限まで進んだ社会で生じる「事故」の激増とその解決法が主人公によってもたらされるまでの経緯が語られる。ここでは他人に認知されない特性を持つ主人公が駆使する最先端脳科学テクノロジーによってある種の解決がもたらされる。この作品の語り口がいわゆる「ほの暗い色調」であり「岡本地獄」であり、筆者が岡本作品の特徴と思っている「遅延性ホラー」の典型だと思われる。頭に無数の針が刺さったイメージはやっぱりホラーだし、「ミシン」というと家庭用ミシンしか思い浮かばない筆者のような読者には不気味なものに感じられる。
「うそつき Fibber」もまたAIが出てくるが、ここでは一般家庭でもAIが日常化した社会の陥穽(最近見ませんね、こんな文字)を描いたサタイアでありホラーである。開発コストを意識しながら、AI技術開発を人間側の心地よさに合わせて進めることに対する著者の視点が実体験からもたらされているかのように見える。
「フィラー Filler」は、デジタル技術でよみがえらせた物故俳優ばかりを使ったドラマが作られるようになった時代だが、役を演じるという行為はAI(作中では機械)だけではどうしてもうまくいかない。修正には膨大なコストかかるので、その修正を請け負うのが機械エンジニア出身の語り手だ。もうこの設定だけで理工学系SFになっている。しかし、語り手の物語は役を演じる行為のオリジナリティという意外な視点で進んでいく。ここでも人間と機械の線引きの鮮やかさに理工学系的思考を感じる。
「自称作家 Call Yourself a Writer」は、文学部出身ではないが作家志望というか実際に会社勤めをしながら何十年も文芸作品を書いている主人公が、作品を広く読者にアピールできるという電子出版サービスからのメールを受け取るところから始まる。実際契約してみると、主人公の作品が売れ始めるのだが……。ネットメディアによく話題になる人為的な売れ筋の話を著者ならではの着実な技術的背景とともに進めていく。これは悲哀の色が強いサタイアでホラー色はない……でもないか。
「円環 Wheel」は、著者としてはめずらしいアイデア一本勝負な作品。ヒトは老いとともに赤子に返って行く、というのはよくある話で、わが老親を見ていると実感が湧いてくるのだけれど、著者は表現に工夫を加えなおかつ表題のとおり実現してみせる。最後の一行がまた著者にはめずらしく叙情/感傷を湛えている。
「豚の絶滅と復活について On the Extinction and Resurrection of pigs」は本書表題作。このタイトルからオールドSFファンなら誰でも五〇年代アメリカSF短編のレックス・ジャトコ作「豚の飼育と交配について」を思い浮かべる。これは、ある惑星で変異ウィルスのため人口が激減、男は二人しか残っていない、という設定のSFで、男の片方が養豚場の経営者ということで、男たちの立場は……、というもの。この設定はスタンダードになっていて最近では筒井康隆が短編集『世界はゴ冗談』収録の「不在」で部分的に使っている。と、ここまで引っ張ってきてなんなんだといわれそうだけど、この表題作と「豚の飼育と交配について」が似ているのはタイトルだけで、こちらでは本当に変異ウィルスでリアルに豚が絶滅して復活する話である。研究所の男女研究員のユーモラスな会話のなかで立ち上がるこの「リアル」というところに理工学系の話づくりの確かさが感じられる。しかもこれは著者の作品としては思わずニヤリとさせてくれる珍しいコメディタッチが成功している一品。でもやっぱり結末はサタイアでホラーだと思う。
「チャーム Charm」は、「いじめ」を受けている子供が話から始まるが、その途中でいじめっ子たちは気まずそうに立ち去る、チャームが発現したからだ……。このプロローグが主人公の体験であり、主人公のチャームへのこだわりは、彼を脳科学に向かわせ国立の研究所で「感情の脳内マップ」を研究するまでになった……。まさに理工学系作家岡本俊弥の典型的な設定といえる作品で、これがSFなのは表題となっている「チャーム」がいかにもありそうな仮説に見えて、その上で物語の結末を支えるアイデアにもなっているからだ。われわれが若い頃の本格SFの定義に「SF的設定を抜くと物語が成立しないような作品」というのがあったけれど、これは岡本作品の多くに見られる。それにしてもこの結末がまた不気味な風景で作者の持ち味がよく出ている。
「見知らぬ顔 An Unknown Face」は、入国審査が高速の自動化ゲートだけになってしまった時代に、ある国の男が観光目的で入国しようとして機械ゲートに虚偽判定されたエピソードから始まる。筆者は著者が「機械」と名付けているものがAIに思えるのだけれど、常に「機械」と呼んでいるところに長年の理工学系技術研究を実践してきた著者のこだわりがあるのだろう。この物語は「ぼく」が機械ゲートの判定は何を意味していたかを依頼人の弁護士に報告する形になっている。すなわちこれは「機械の精神分析医」シリーズの一編なのだ。ということで岡本作品中最も多く書かれているシリーズの雰囲気がここでも味わえる。多分、「機械の精神分析医」である「ぼく」が著者にとっていちばん自分を仮構しやすい人物なのだろう。
「ブリーダー Breeder」は、二度目の定年を迎えた主人公がこれといった趣味もないのでよくある自宅のDIYを始めるが、それに飽きたころ「ブリーダー募集」のチラシに興味を持つ。この募集元が「株式会社 次世代知能技術研究所 NTL」というところが、やっぱり著者のSFたるところ。主人公が任された「ブリーダー」の相手は「会話するアプリ」で、主人公は画面中の猫アバターを選択し結構熱中するのだが……。ここでもまるでAIのディープ・ラーニングみたいなものを思わせておいて、著者は近未来テクノロジーのSF的ヴィジョンを披露する。これはサタイアでもホラーでもない一作。
トリは本短編集の中でいちばん長い「秘密都市 The Secret City」。視点人物は会社を早期退職し、家族と別れヤモメ同然の生活をしていたが、ある日、以前ライターをしていたころ世話をした若者がいまはネット投稿記事サイトの編集者として取材仕事を依頼してきた。取材先の近くにいるので経費が安く済むと考えたらしい。あまり乗り気ではなかったが引き受けた。そして物語は主人公が書いた取材レポートとして展開する……。これはいわゆる陰謀論/トンデモ系のウラ歴史物で、ソ連崩壊時に多くの核技術者が各国へ離散したという事実を踏まえて、著者の作品としてはかなり異例の大がかりな仕掛けを用いている。さすがに話が大きすぎるのではと思うけれど、著者は最初からウラ事情系ネット投稿サイトの取材記事として予防線を張っている。著者の作品の中でも異色な部類に入ると思う。
最後に、著者の刊行予告を見たら本短編集のテーマは「お仕事」とのことだった。うーむ、それにふさわしい作品紹介になっているか心許ないが、ここらで〆とさせていただく。
POD/Kindle版解説ではこの後に「おまけ」が続きます。ここでは割愛しています。