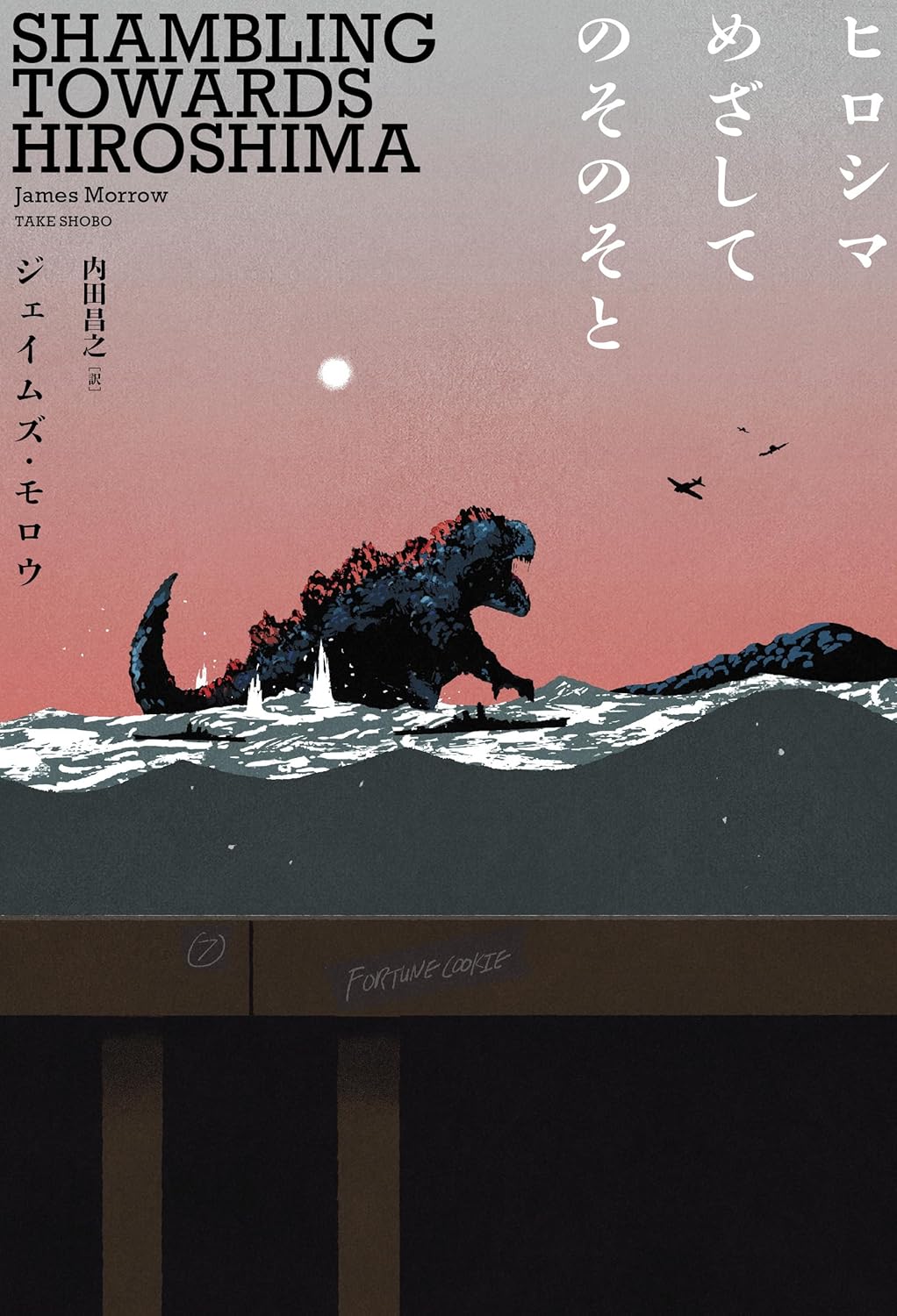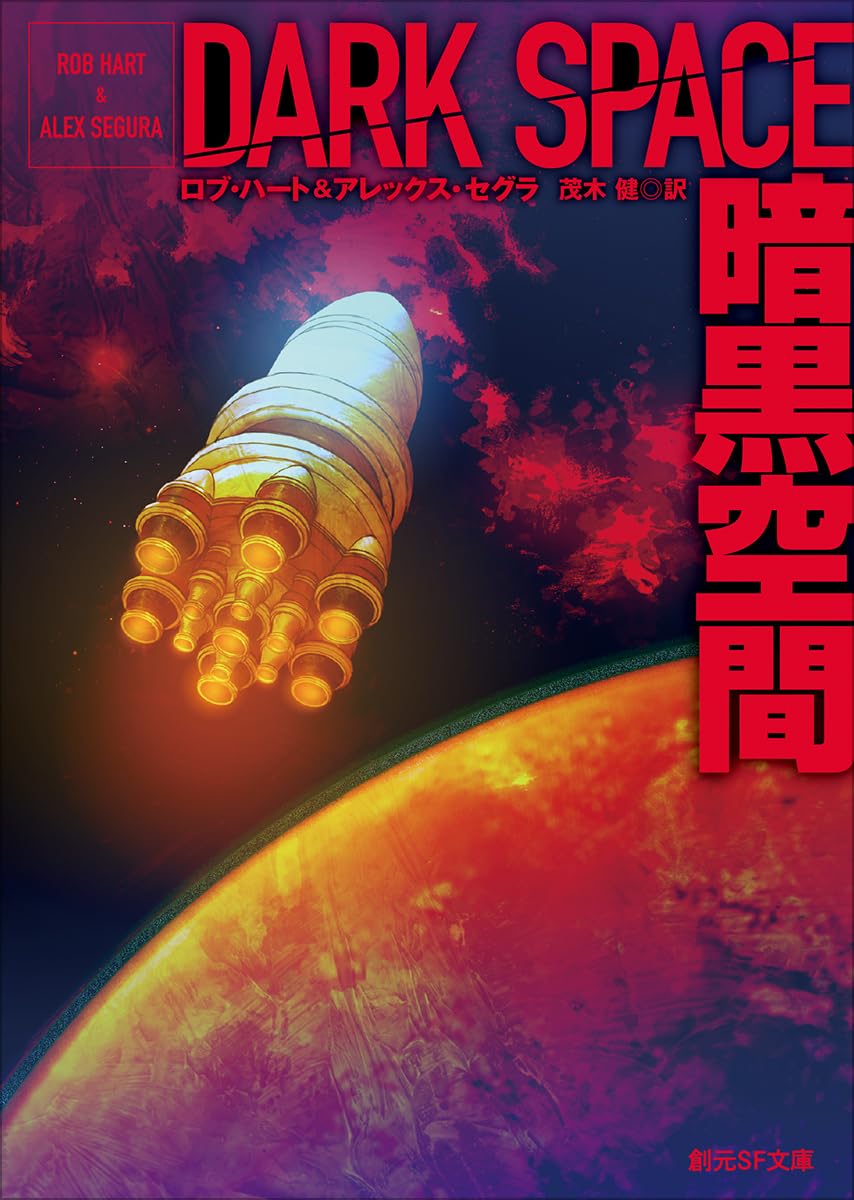Cover Design:岩郷重力+S.I
第13回ハヤカワSFコンテスト優秀賞受賞作。今回は大賞はなく、優秀賞と特別賞各1作という結果だった。著者の関元聡は、既に短編での受賞歴(第9回、第10回の星新一賞グランプリ)がありアンソロジイへの寄稿もしているプロの作家である。どんな長編を書くのかと注目度も高かった。
温暖化が進む地球にどこからともなく宇宙船が現われ、各地に断熱密閉ドーム「コクーン」を建造してまた飛び去る。それは灼熱地獄から人類を生存させる砦となり、宇宙船は〈救済者〉と呼ばれるようになった。しかし、気温が100度近くまで上昇するドーム外の環境では人類は生き残れず、コクーン内のエリートたちを残して死滅してしまう。それから数百年経った未来、世界各地のコクーンからの通信が次々と途絶する異変が起こっていた。
この時代の地球は、しかし死の世界ではない。高温に適応した動植物が繁栄し、特殊な生存能力を秘めた女系種族も生きていた。物語はそんな女系種族の2人、コクーンの科学者である1人の女性を軸に進む。火星のテラフォーミングなどをちりばめながら、異変の真相を探る物語でもある。
選考委員の評価(抜粋)は以下の通り。小川一水:変わり果てた未来世界での、黙示録的な長旅の風景はSFというに相応しく、やや複雑だが構成力に富んだ話作りを認めて全員が一定の評点を付けた。神林長平:ストーリーはよく出来ていて構成も上手いのだが、この物語の設定を読者に納得させる力が弱い。菅浩江:真っ向勝負のSFで嬉しかったです。(中略)文章表現も巧み、ネタもよく処理もよい。細かい傷をつぶした後の書籍化が楽しみです。塩澤快浩:SF的なアイデアや精緻な自然描写は素晴らしかった。一方で(中略)クライマックスへ向かっていく感興に乏しい点が残念だった。
長所、短所に対する指摘については、各選考委員の意見はほぼ一致しているようだ。修正ポイントは明らかなので、書籍化された本書はどうなのかと思って読んでみた。標題はクレメント的なハードSFを連想させるが、そういうものより人間寄りの物語である。超温暖世界で特殊進化した人類(特殊化された地球)と、火星に行くしかない旧来の人間とが共存できるのか。それはまた、過酷な母系社会の母娘と、文字通り閉じられた旧社会の父娘との相克をも描く。この著者の場合、興味の中心は「物理」よりも「環境」にあるのだろう。そういう本来のテーマがより明瞭に示された仕上がりだった。
- 『羊式型人間模擬機』評者のレビュー