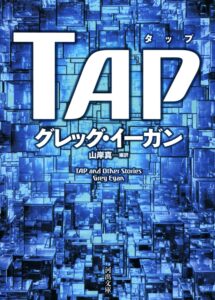今回のシミルボン転載コラムはイーガンです。海外のSF作家、それも英米圏ならテッド・チャンとグレッグ・イーガンは日本での人気の双璧といえます。多くの翻訳作品がありますが、ほとんどは現行本か電子書籍で読めるというロングセラー作家でもあります。以下本文。
1961年生。オーストラリアの作家。ポートレートを一切公開せず、イベントやサイン会にも参加しない覆面作家として知られる。理論的なバックグラウンドを備えた本格的なハードSFを書く作家で、英米よりも日本での評価が高いのが特徴だ。母国オーストラリアのディトマー賞で辞退騒ぎがあった2000年以降(ノミネート自体を拒否している)は、日本の星雲賞(長編部門で2回、短編部門で4回)での受賞回数が際立っている。
『祈りの海』(2000)は編訳者山岸真による、日本オリジナルの短編集である。この本が出る前は、長編『宇宙消失』(1992)や、仮想環境下でシミュレートされる生命を描いた『順列都市』(1994)で注目されてはいたが、まだコアなSFファン内部にとどまっていた。イーガンの魅力を存分に伝えた本書が、一般読者を含む幅広い人気を生み出すきっかけになったのだ。
1日ごとに違う自分だったら。可愛いが人とは認められない赤ん坊がいたら。不死を約束する意識のコピーを持てたら。あるいは、未来から送られてくる日記があったら。誘拐されたのが自分の感性だとしたら。人類の祖先はアダムなのかイヴなのかが分かったら。そして、神々と逢える海(ヒューゴー賞、ローカス賞、星雲賞を受賞した「祈りの海」)の正体を知った主人公はどう行動したのか。人間の根源である意識や思考は、単なる物理・化学変化が生み出す錯覚にすぎないのかもしれない。こういったアイデアの数々は、読者に衝撃を与えた。
短編集『しあわせの理由』(2003)では、星雲賞をとった表題作で、不治の病に冒され死につつある少年が描かれる。不幸なはずの少年は幸せだった。何もかもが肯定的、あらゆるものが楽天的に感じられるからだ。彼の脳内で育ちつつある癌が、ある種のエンドルフィンを分泌する。それが人に究極の幸福感を与えてくれる。本書のどの作品もシニカルだ。派手な盛り上げはない。たんたんと物語が流れていく。デジタル化され、化学物質で感情が左右されると、逆に人間の本質があらわになる。最愛の夫を宿せと言われた妻を描く「適切な愛」や、この「しあわせの理由」で顕著に現れるのが、肉体や感情のコントロールこそ、純化された人間そのものというメッセージだ。電脳やナノテクは非人間的という、一般的なパターンをはるかに超越した考え方だろう。
『万物理論』(1995)は、2005年の星雲賞受賞長編である。21世紀半ば、遺伝子情報は大企業が寡占している。さまざまな遺伝子操作の可能性は奇怪な事件や人物を生み出していた。そんな生命を弄ぶ取材に疲れた主人公は、物理学会で画期的な理論の発表がされることを知る。「万物理論」は宇宙創造を説明し、物理の根本を説明できるという。
本書のキモは、やはり「驚くべき結末」を構成する奇想アイデアであり、いかにも本当らしい理論的説明にある。誤解を避けるため、反科学の立場は本書で否定的に描かれているが、アイデア自体は疑似科学を思わせる。それをトンデモ説ではなく、客観的な立脚点で描ききったところがSF作家イーガンの際立つ才能といえる。
2006年の星雲賞受賞作『ディアスポラ』(1997)は本格宇宙SFである。30世紀、人類は少数の肉体で生きる人々を除いて、大多数がソフトウェアによる電脳者だけになり、彼らは情報を集積する唯一のハードウェアであるポリスで生活している。ある日、文明を支えていた予測理論では予見できない宇宙的異変が起こり、地球環境が破壊されてしまう。このままでは、彼ら自身のポリスの未来も不確かなままだ。真理(新しい法則/理論)を求めるべく、1千もの宇宙船が宇宙に散開(Diasporaの意味)する。しかし、そこで彼らの目にしたものは、ありうるべき理論をはるかに超える未知の存在だった。
本書のように、文字通り次元を超えた大変移は、既存のどんな作品でも書かれたことがない。宇宙SFというより宇宙論SFなので、イーガン流の重厚な世界を正面から楽しむつもりで読むべき作品だ。もちろん「宇宙物理SF」を読むのに宇宙物理の素養は必要ない。
ハードSFはやっぱり苦手という人には、同じ山岸真編の『TAP』(2008)という作品集もある。ちょっと不思議系作品が選ばれている。本書の中では、実験室で人知れず実験動物を使って培養されるもの「悪魔の移住」や、偶然大金を手にした夫婦が、生まれてくる子供に最高の遺伝子を持たせようとする「ユージーン」の結末が、いかにもイーガン風の皮肉で面白い。
長編『ゼンデギ』(2010)は宇宙ではなく、近過去(2012)と近未来(2027)のイランを舞台にした作品。そこで流行しているVRゲーム(ゼンデギ)をからめて、イーガン得意の人間意識の電子化を描く異色作だ。
『ゼンデギ』(2010)の次に書いたのが、《直交3部作》(2011-2013)である。しかし、これに手をつける前に、『白熱光』(2008)をまず読んでみることをお勧めする。
ハブと呼ばれる中心を巡る軌道の上に、その世界〈スプリンター〉はある。異星人である主人公は、理論家の老人と知り合い、さまざまな実験と観測の結果、ついに世界の秘密を説く鍵を見つけ出す。一方、150万年後の未来、銀河ネットワークに広がった人類の子孫は、銀河中心(バルジ)から届いた1つのメッセージを頼りに、別種の文明が支配するその領域に踏み込もうとしていた。
物語は、時間軸の異なる2つの系統から作られている。六本脚の異星人が孤立した星の中で、独自に物理法則を発見していく物語と、生物由来/電子由来の区別がなくなった超未来の人類が、銀河中心に旅する物語である。後者は、最終的に前者との結びつきを発見することになる。種明かしにも関係するが、本書の舞台はブラックホール/中性子星という、超重力の近傍世界だ(それ自体ではない)。
何しろ、理論物理学の教科書を読まないとわからないことが、数式なしで書かれている。シミュレーションすることで初めて見えるような物理現象が、ビジュアルに書かれている(つまり、明確な根拠を持っている)。著者自身その詳細を、数式で解説している。そもそも書かれた世界ではニュートン力学ではなく、相対論的効果の下での力学が働いているのだ(われわれも厳密にいえば相対論的効果の下にあるが、その効果を日常で感じることはない)。翻訳版では解説に謎の答えのヒントがあるし、物理的な背景も(なんとなく)分かるので、比較的読みやすいだろう。
次に『クロックワーク・ロケット』を始めとする《直交三部作》(2011-2013)がある。ここでいう直交 Orthogonal とは、本書の場合、主人公たちの宇宙と直角に交叉する直交星群を指す。原著が3年かかって出たのに対し、翻訳は1年以内に3部作を刊行しようとしている。これまでイーガンを一手に引き受けていた山岸真に加え、中村融を共訳者に据えた強力な布陣(前半後半を分担し、全体調整は山岸真)が注目される。
別の物理法則が支配する宇宙、主人公は旧態依然の田舎から逃げ出し都会で学者の道を選ぶ。やがて、夜空に走る星の光跡から回転物理学を発表、世界的な権威となる。一方、大気と衝突する疾走星がしだいに数を増し、破滅の危機が叫ばれるようになる。主人公らは、巨大な山自体をロケットとして打ち上げ、そのロケットの産み出す時間により世界を救うことができるのではないかと考える。ロケットを時間軸に対して垂直になるまで加速すると、母星の時間は止まり、無限の時間的余裕が生まれるのだ。
主人公は人間ではない。前後2つづつの目を持ち、手足は自在に変形できる。腹部に記号や図形を描き出し、それが重要なコミュニケーション手段となる。性は男女あるが、女は男女2組の子供を産む(この男女が双と呼ばれ、通常なら生殖のペアとなる)。主人公は単独に生まれた女で、出産を抑制する薬を飲む。人類とかけ離れた生態ながら、主人公らは人間的に感情移入しやすく描かれる。人という接点がなければ、小説として成立しなくなるからだ。
『白熱光』は特殊な環境の星を舞台にしていたが、そうはいっても同じ相対論宇宙での出来事だった。本書は違う。根本的な物理法則が異なっており、相対性理論は回転物理学と呼ばれている。なぜなら、時間経過を示す方程式で、時間の二乗が距離割る光速の二乗で「引かれる」のではなく「足される」からである。そのあたりの理論的解説は、例によって著者のHPで詳細に書かれている(が、それを読んで直ちに理解できる人は少ないと思う)。巻末にある板倉充洋による解説の方が分かりやすい。
本書は、ありえない世界の一端を物理現象として見せてくれる。物理法則は世界の在り方を記述する。しかし、そこを書き換えた結果、何が起こるのかをすべて予測するのは難しい。著者自身述べているように、全く異なる世界をシミュレーションするには、無限大の知見が必要になるからだ。その隙間こそ、小説が埋めるべきものだろう。前例がないわけではない。レムは架空書評集の形で書いたし、小松左京は「こういう宇宙」でその雰囲気を描いて見せた。
ところで、なぜクロックワーク・ロケットなのか。この宇宙では原理的に電子制御ができず、ロケットは機械仕掛けのみで動くこと。もう一つ、時間と空間が完全に等価であり、光速による制限がない=光速を越えられる=タイムトラベルが自在=時を動かす装置、等の連想もできるだろう。
『エターナル・フレイム』(2012)は、《直交3部作》の2作目にあたる作品である。母星から直交方向に飛ぶ巨大な宇宙船〈孤絶〉内部では、すでに数世代の時が流れている。故郷を救う方法は未だ得られず、帰還に要するエネルギーも不足する。しかし、接近する直交星群の1つ〈物体〉を探査した結果、意外な事実が判明する。一方、乏しい食料と人口抑制の切り札として、彼らの生理作用を変える実験も続けられていた。
前作では直交宇宙における相対性理論=回転物理学と、その理論を解明する主人公たちが描かれていた。今回は量子論である。解説で書かれているように、20世紀から21世紀にかけての量子力学の成果が、形を変えて直交宇宙で再演されている。光が波なのか粒子なのか、といったおなじみの議論もなされるが、当然我々の宇宙と同じにはならない。物理学上の大発見と並行して起こるのが、ジェンダーの差による宿命を揺るがす生物実験だ。それは、宇宙船内を巻き込む大事件へと広がっていく。物理学の再発見という静的な物語の中で、これだけは感情に左右される問題だろう。ある意味、とてもイーガン的なアイデアなので、インパクトを与えるものとなっている。

さらに『アロウズ・オブ・タイム』(2013)は3部作の完結編である。アロウズ・オブ・タイムとは“時の矢”のこと。時間には流れる方向があり、それは矢が飛ぶ様子になぞらえられる。放たれた矢は一方向に飛び、逆転してもどってくることはない。しかし、時間と空間が完全に等価なこの宇宙ではありうる。たとえば、未来からのメッセージを過去の時点で受け取ることが可能なのだ。片道に6世代を費やしてまで母星の危機を解決しようとした〈孤絶〉内部では、帰還への旅の過程で、メッセージの受け取りと意思決定を巡って深刻な対立が巻き起こる。
この3部作は、相対性理論・量子力学・時間遡行までを扱う究極のハードSFなのだが、意外にも軽快に読めてしまう。設定は重厚でも、お話は変にひねっていないので読みやすいのだ。別の宇宙の物理を組み立て(著者のホームページにはさらに詳しい設定資料があるが、物理が平気な人以外にはお勧めできない)、ノーベル賞級の発見(相当)をこれだけコンパクトにまとめた、イーガンの手腕には改めて驚かされる。
(シミルボンに2016年8月31日、及び2017年2月24日掲載したものを編集)
この記事の後も、イーガンは長編『シルトの梯子』(2001)や、星雲賞を受賞した「不気味の谷」を含む作品集『ビット・プレイヤー』(2019)などが翻訳され、2020年には文藝夏季号で特集が組まれるなど、ジャンルを超えた幅広い人気を維持しています。