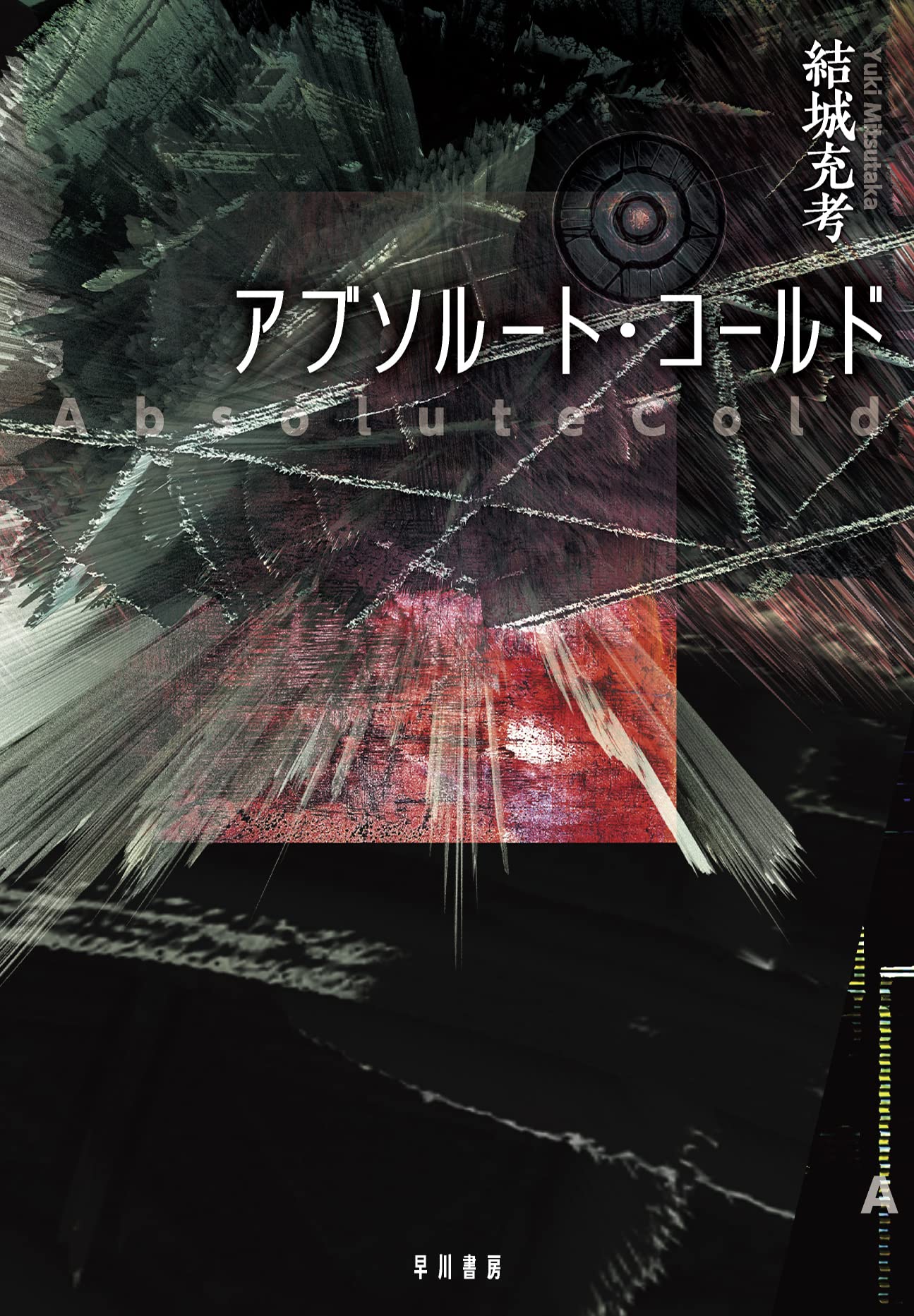
2004年に第11回電撃小説大賞でデビュー後、2008年に第12回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞、以降主に《女刑事クロハ》などミステリを手掛けてきた著者による、2冊目のSF長編である。もともと新潮社の電子雑誌yom yom(現在はWEBマガジン)で2020年8月号まで連載されたもの。単行本化にあたって削除シーンなどを復活させた完全版である。
舞台は叶(かなえ)県の一部をなす、見幸(みゆき)市と呼ばれる治外法権を得た都市。そこは、私兵集団を擁する佐久間種苗株式会社(バイオからITまですべてを支配)によって、事実上牛耳られている。だが、200階建ての本社ビルで大規模なテロが発生し多くの研究者が亡くなる。首謀者は何者か。事件の真相を探るため、死者の最後の記憶を読み取る装置=アブソルート・ブラック・インターフェイス・デバイスが用意される。
SF第1長編の『躯体上の翼』(2013)から10年近くが経過するが、そこに登場する「佐久間種苗」が本作にも出てくるなど、緩やかなつながりはあるようだ。時間的な流れでいえば本書が先にあり、前作の世界はより幻想的ではるかな未来にある。
市民を狙撃した暗い過去を持つ警官、植物状態で眠る娘の介護に疲弊する元警官、遺品の引き取りをするだけだったのに事件に巻き込まれる準市民の少女、主にこの3人を巡って物語は展開する。死者の記憶に絡むハードボイルドな犯人捜しかと思っていたら、AI「百」やテュポン計画など、謎めいた電脳世界を巡る暴力的なバトルへと話はスケールアップする。
ルビを多用する短いセンテンス(たとえば、雑音にノイズと振るなど)、廃墟めいた猥雑な未来都市の光景、文体も初期の黒丸尚翻訳を思わせる(このあたりはSFマガジン2023年6月号の著者インタビューでも言及されている)。そこから「令和日本に放つサイバーパンク巨篇」という惹句になる。とはいえ、サイバーパンクはもはや過去を連想させるレガシーなタームである。映画「ブレードランナー」(1982)や、ギブスン《スプロール三部作》(1984-88)に代表される80~90年代の流行だからだ。
ただ、本書の参考文献に、映画「Eddie and the Cruisers」(1983)、評論『サイボーグ・フェミニズム』(1985)という80年代作品が示されているのを見ると、作者は意図的に「失われたサイバーパンク的未来の再演」を試みたと考えるべきだろう。50~60年代とかではなく、80年代すらレトロフューチャーになり得るのだ。
- 『躯体上の翼』評者のレビュー
