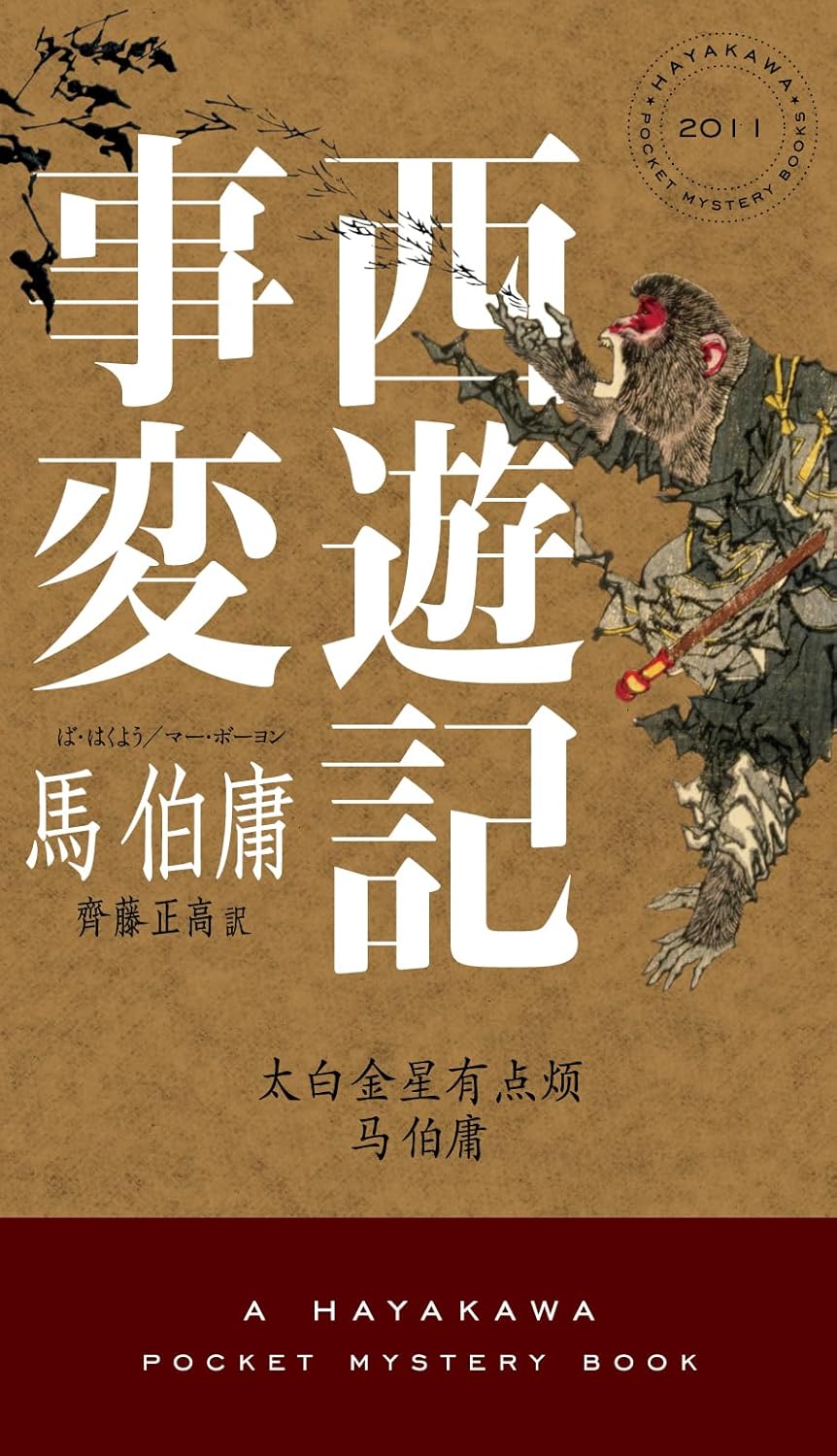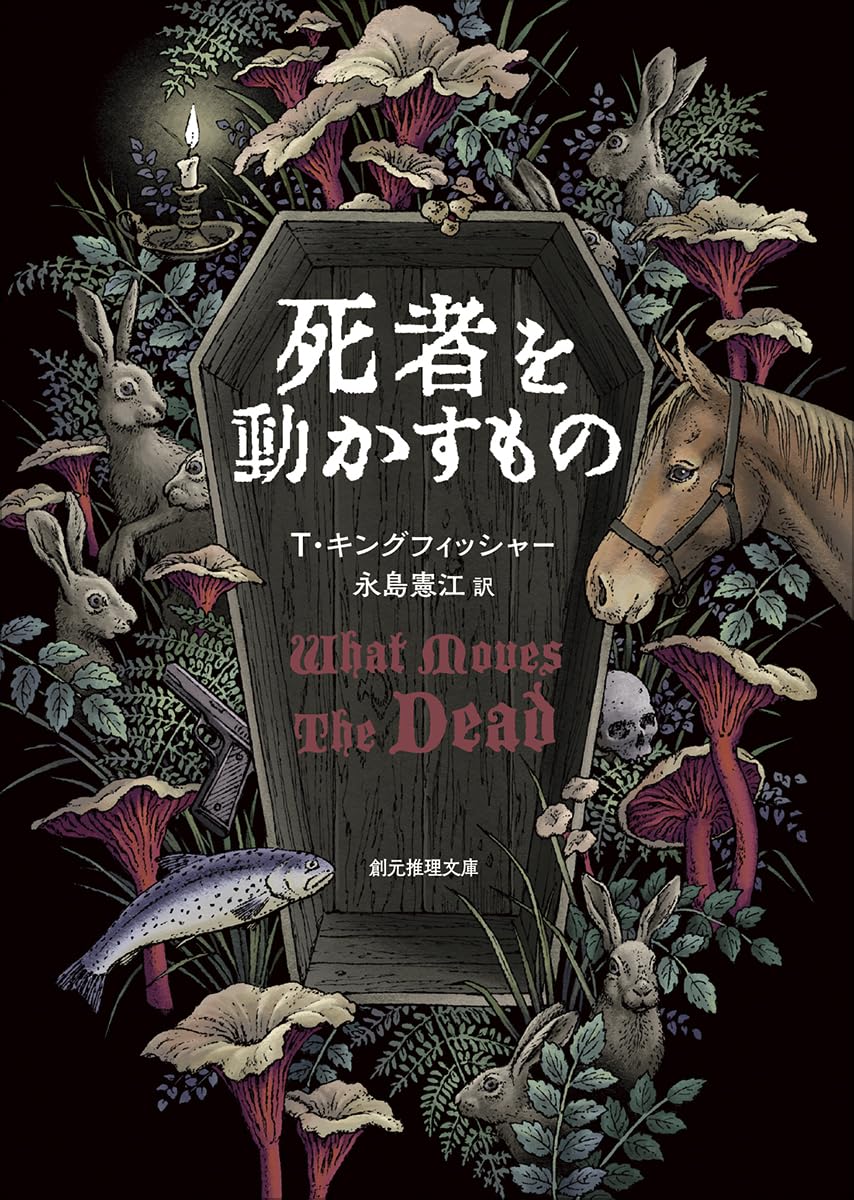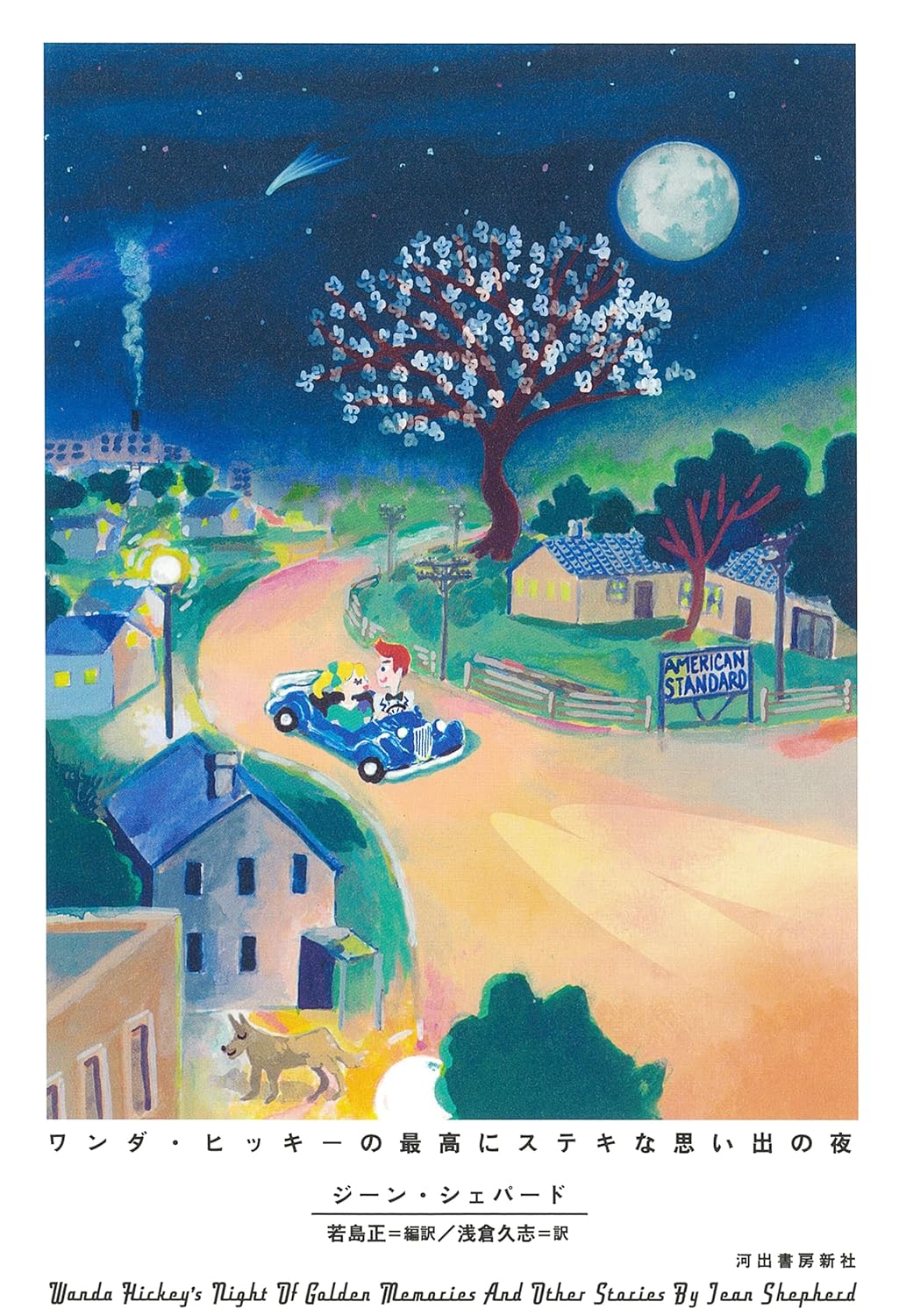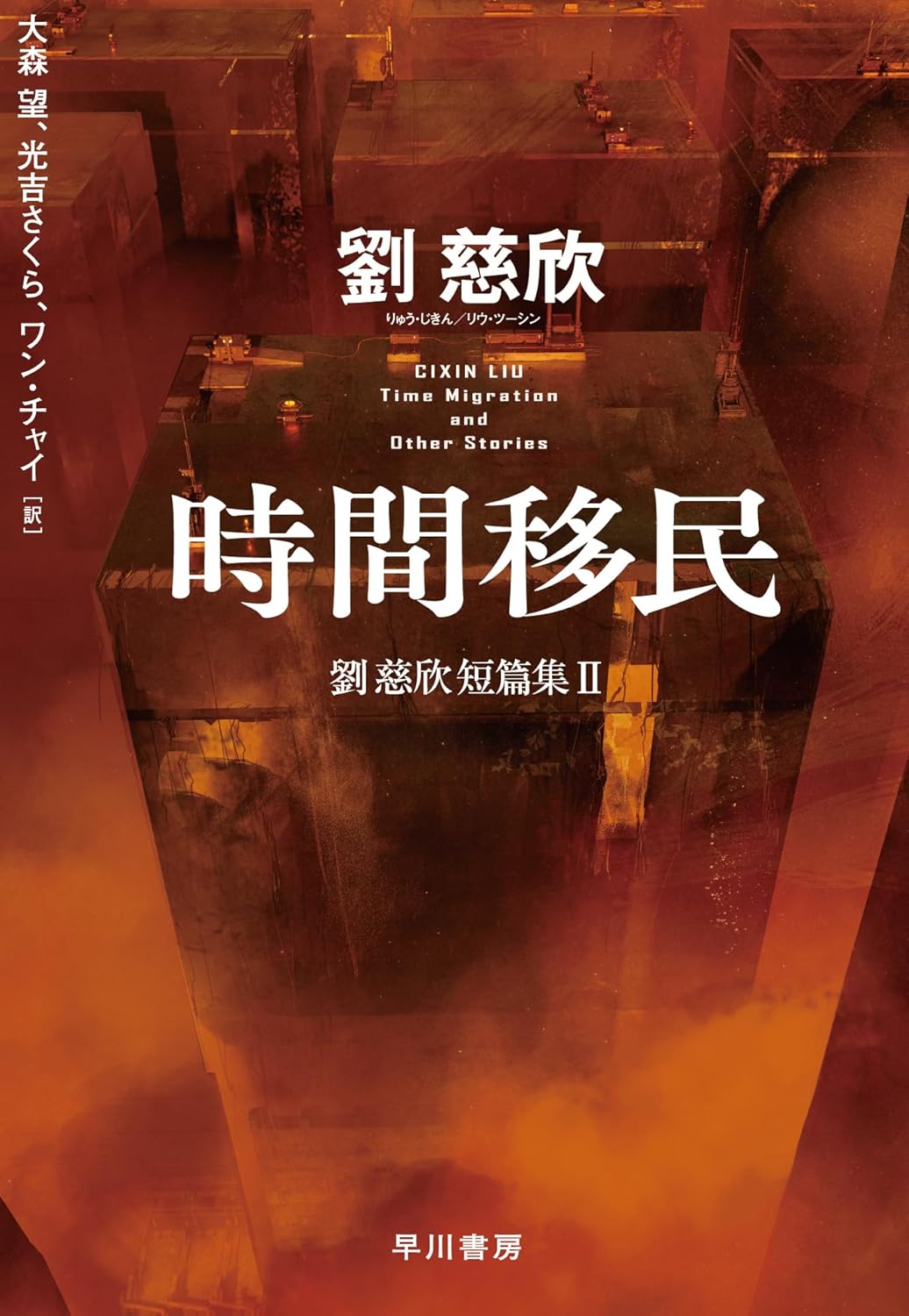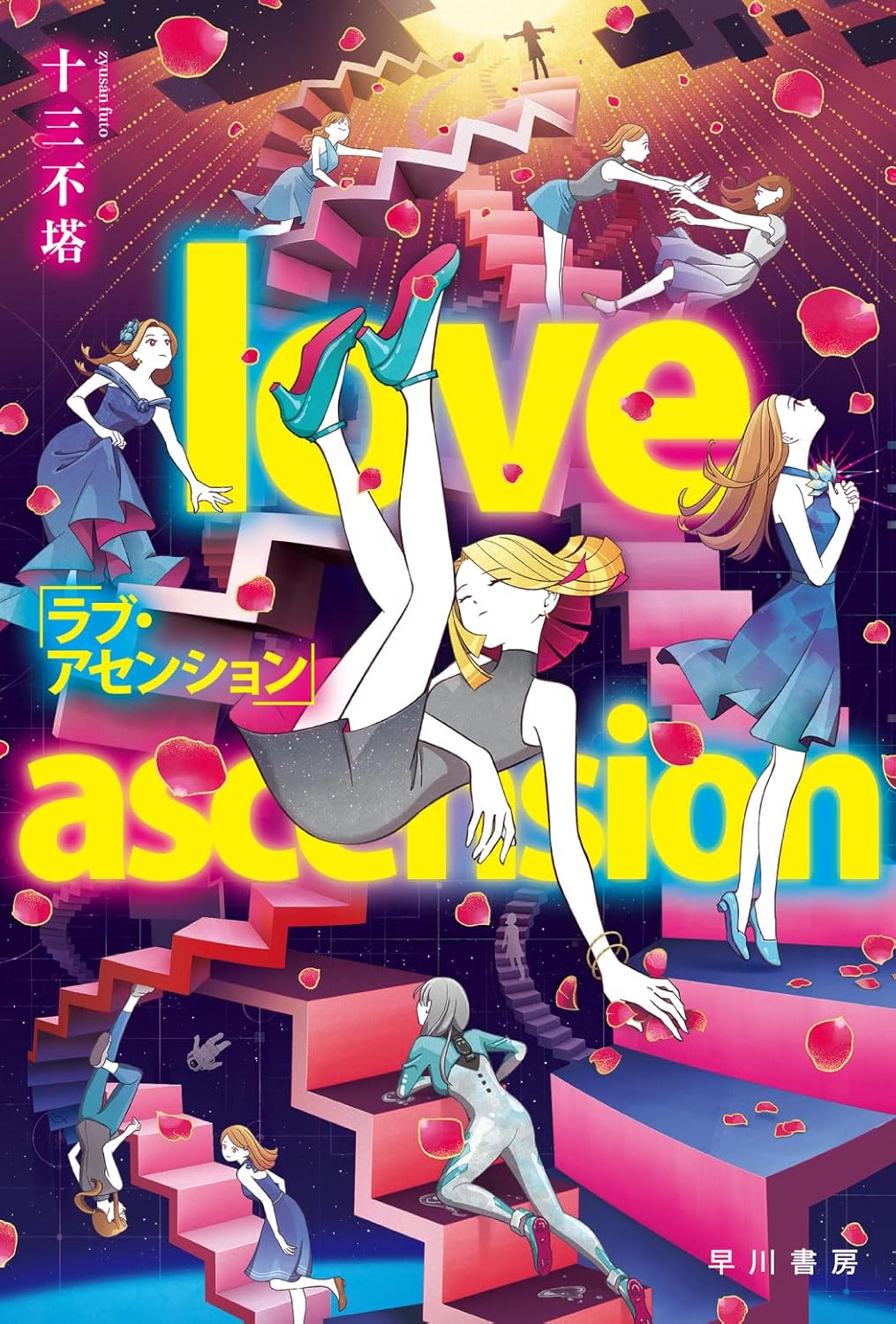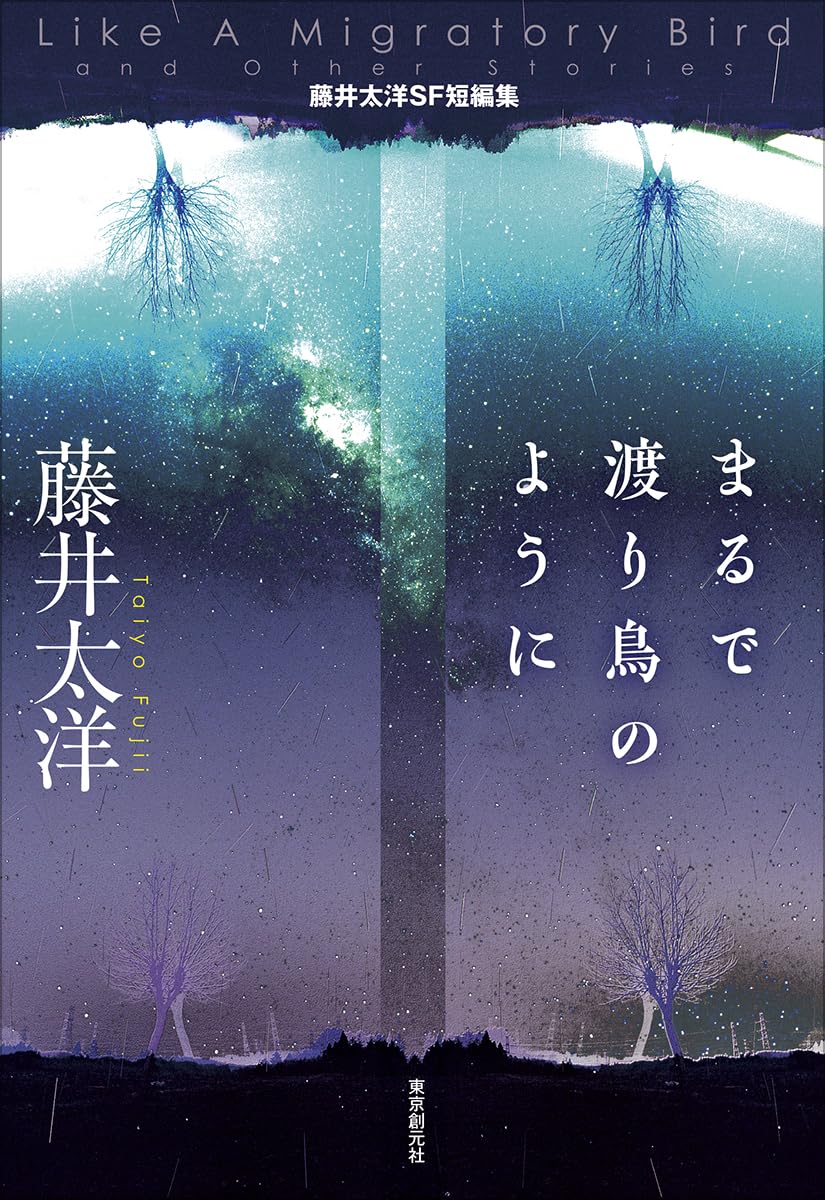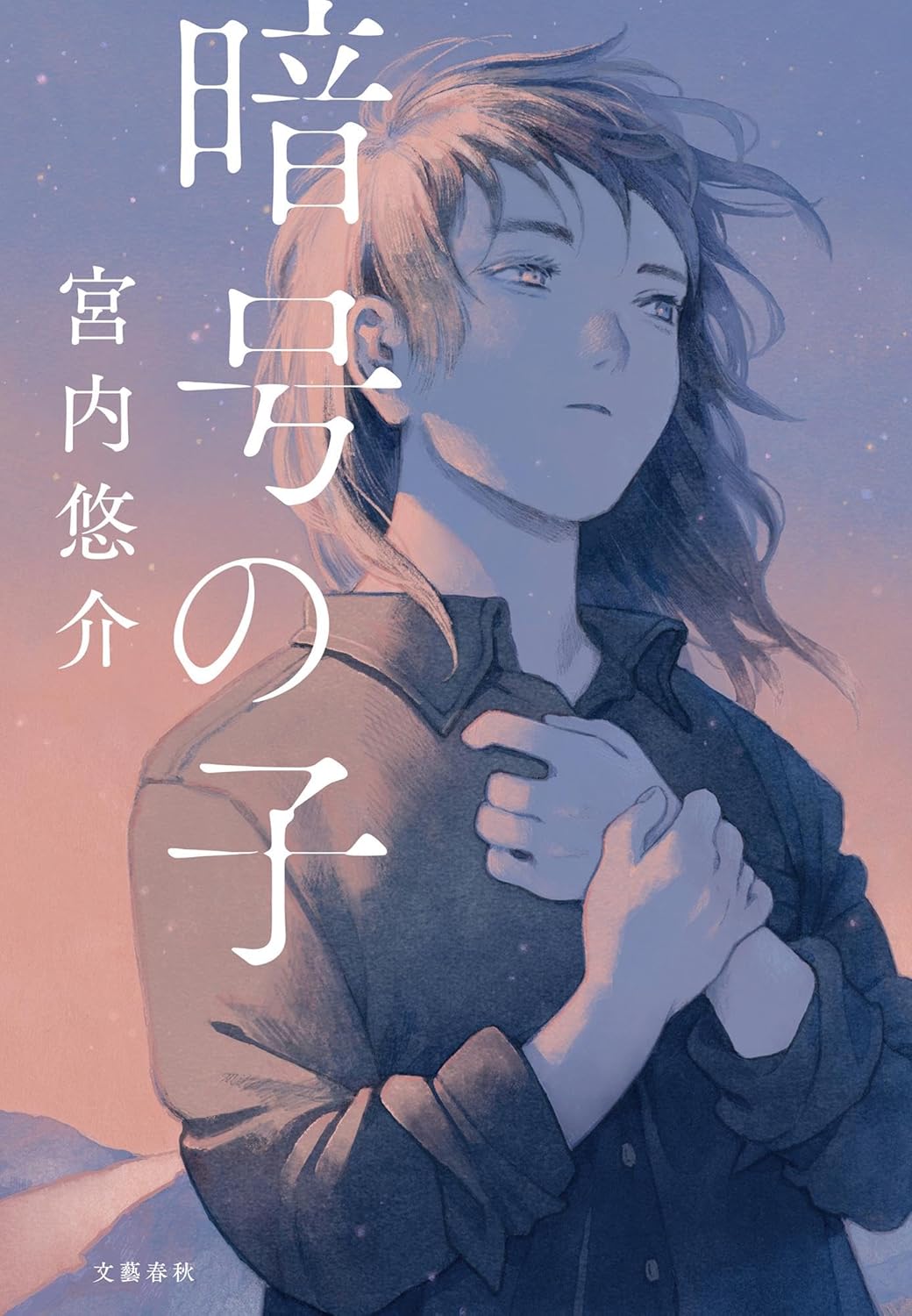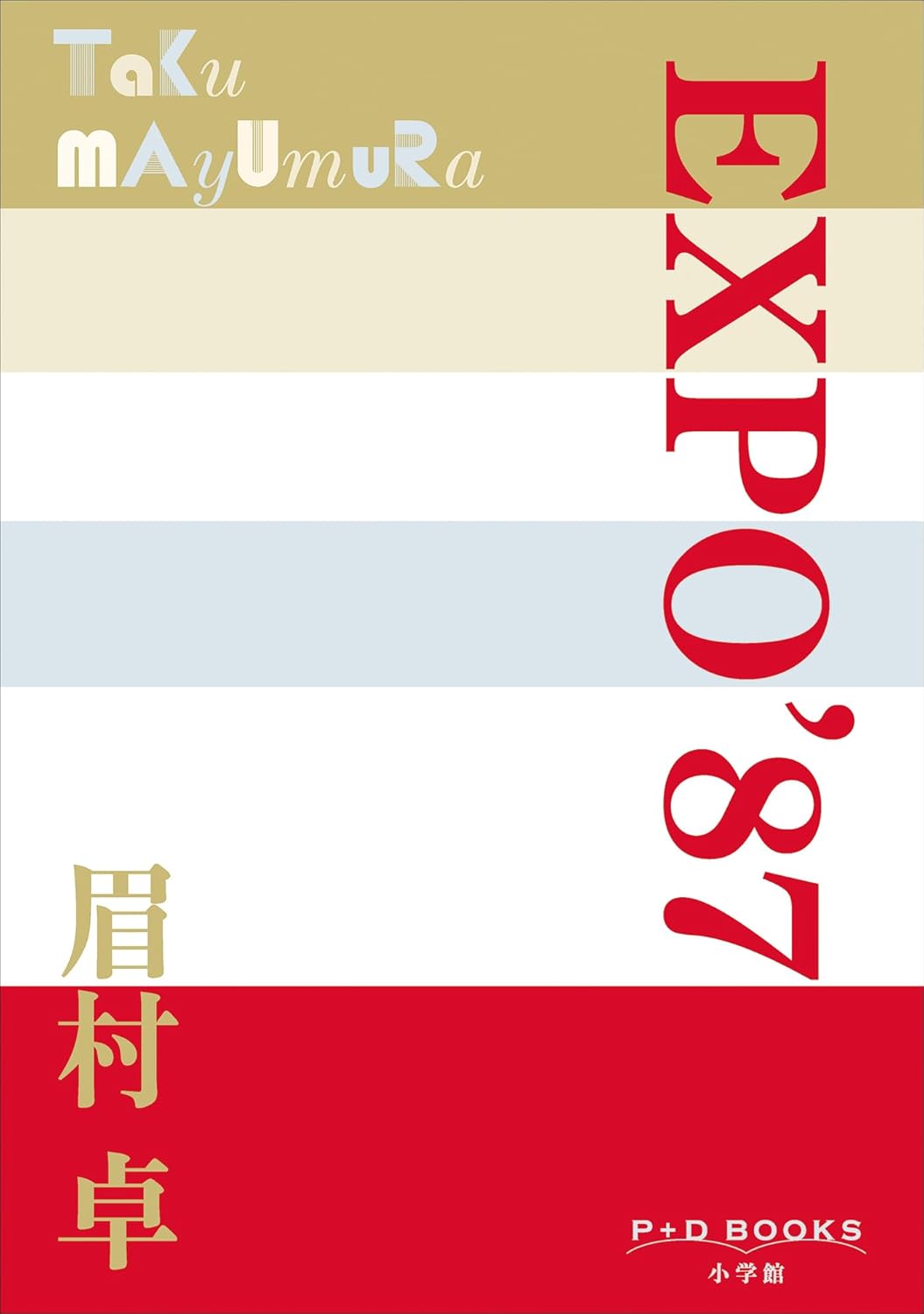
『EXPO`87』はSFマガジンの1967年8月号から68年1月号に連載され、同年末に《日本SFシリーズ》の1冊として単行本化、その後1973年にハヤカワ文庫、78年に角川文庫版が出た眉村卓の初期長編である。1970年の(旧)大阪万博前に書かれ、長らく絶盤状態だったが《P+D BOOKS》(オンデマンドブックに近い廉価な装丁の叢書)で復刊した。舞台を執筆時の20年後に設定し、今でいう近未来サスペンスとした作品である。同シリーズの筒井康隆『48億の妄想』がブーアスティンの疑似イベントに材を採ったディストピア小説だったのとは対照的に、シリアスな社会派群像劇となっている。
愛知県の安城市で開催される東海道万国博は、その17年前の大阪万博とは大きく意味合いを変えた博覧会だった。貿易自由化の圧力下でアメリカ巨大資本が日本市場に進出、残りのパイを財閥や非系列が奪い合うという構図が、そのまま会場のパビリオンに反映される異例の企業博となっていた。独立系の大阪レジャー産業は、万博を独自技術の実感装置をアピールするチャンスと捉え、身の丈を越える資金投入をしていた。
政府は財閥の出身者に牛耳られ、女性主体の家庭党が台頭し発言権を増す。世界では核保有国が数十に拡大し不安定化が進み、外資に制圧された経済はネットワーク化が進む。街では電気自動車が主流となり、電話の代わりを映話が担う。群小のタレントは淘汰され、才能あるビッグ・タレントがオピニオンリーダーとなって万博反対を叫ぶ。一方、外資に対抗する秘密兵器、産業将校たちが姿を現す。
もしこれを予言の書というのなら、1987年段階での的中率は高くないだろう(レトロ・フューチャー的な部分もある)。現代まで敷衍すれば、アメリカ政府が会社のCEOに支配され、日本の情報インフラは外資に制圧されたので、別の形で的中したと見なせるかもしれない。しかし、本書の本質は未来を予見することにはない。最大のポイントは「産業将校」の存在である。産業将校は(肉体、知能の)実務能力を極限まで高めたスーパーエリートなのだが、『ねらわれた学園』を支配するグループとよく似ている。合理的で無駄がないからと民を意図的に操り、独裁を目指すエリートはどんな社会からでも生まれてくる。それでいいのか、と眉村卓は警鐘をならすのだ。
- 『異世界への旅人 眉村卓』評者コラム