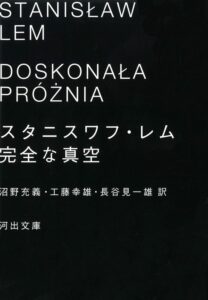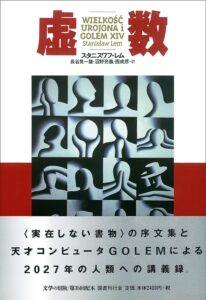シミルボン転載コラム、今回はレム。国書刊行会の《レム・コレクション》は第2期まで進み、日本での人気の根強さを感じさせます。この作家紹介コラムは、いきなり選書ではハードルが高いという初読者の方や、数冊読んだが全体像が分からないという方のために、おおまかな全体像を提供する目的で書かれています(マニアの皆さまには今更ながらの内容ですが悪しからず)。以下本文。
1921年生。2006年に84歳で亡くなる。レムは究極の弧峰である。多くのファンを持ち、ポーランド国内はもちろん国際的な評価は高いけれど、その流れを継ぐ者や、追従者すら見当たらない。何ものも寄せ付けないという意味で、そびえ立つ弧峰なのである。
『高い城・文学エッセイ』(1966)に収められた自伝によると、レムは旧ポーランド領(現在はウクライナ領)のルヴフに生まれた。父親は医師で、幼いころから高価だった多くの本を読むことができた。際限のない知識欲を満たすために、百科事典をくまなく読んだりもしている。もらったおもちゃは残らず分解され、元に戻ることはなかったという。
ギムナジウム時代に、レムは奇妙な遊びに熱中する。それは架空の国/機関の書類(パスポート、許可証、証明書類)を捏造するというものだ。さまざまな役職と、複雑な許認可制度が考え出され、書類ひとつひとつに意味が持たされた。これなどは、官僚的迷宮に主人公が迷い込む『浴槽から発見された手記』(1961)を思わせるが、レムのお話作りのベースがどこにあるのかをうかがわせるエピソードだろう。
レムが30歳の時書いたデビュー長編『金星応答なし』(1951)は、ツングース隕石に書き込まれたメッセージをもとに、金星に向かった探検隊が遭遇する異星文明を描くものだった。社会主義リアリズム全盛期に書かれた作品だが、後に書かれる思索的な宇宙ものの萌芽を含んでいる。この後、労働部分と思考部分が分離した生物が登場する『エデン』(1959)、『ソラリス』(1961)、昆虫のような群体ロボットを描く『砂漠の惑星』(1964)を出版する。それぞれ極めてユニークな知的生命を創造した、宇宙3部作といえる作品だ。
『ソラリス』(1961)惑星ソラリスが人類に知られてから百数十年が経った。その惑星は二重太陽系に伴う不安定な軌道を、重力を制御することによって自立的に安定させているのだ。ソラリスは惑星海面全体を覆う巨大で単一の生命だった。しかし、最初の接触を目指したさまざまなプロジェクトはことごとく失敗する。あまりに異質で、共通点のない知性とコミュニケートする手段はないのか。しかし、ある日ステーションの科学者が行った個人的な実験が思わぬ結果を生む。科学者たち自身の奥底に隠されていた傷跡が、実体を伴って現れるのである。主人公の場合、それは19歳で自殺したかつての恋人だった……。
『ソラリスの陽のもとに』(ロシア語からの重訳版)が出たのは、半世紀以上前のことである。その時点で、すでに『ソラリス』は伝説的な傑作と評されていた。本書は2回映画化されている。アンドレイ・タルコフスキー監督は『惑星ソラリス』(1972)でロシア的な原風景をふんだんに鏤めた原罪と罰の物語を作り、スティーヴン・ソダバーグ監督『ソラリス』(2003)は悲劇的な失われた愛と甦りのロマンスを映像化した。しかしレムが描き出すのは、異質な知性=不完全な神とのコンタクトの物語である。現在入手できる最新版は、コンタクトテーマに関わる欠落部分が補われた、ポーランド語原典からの完訳である。
550枚ほどしかない短い長編だが、余計なものは一切含まれない。そこに、コンタクトの物語、人の持つ罪と奥底に隠された罪悪感の物語、失われた甘美で悲劇的な恋の物語という、複数の物語が並存している。そもそも単一の視点しかない作品では、これほど長生きできなかったろう。ようやく世間がレムに追いついてきたのか、原点としてのテーマ“完全に異質なものとのコンタクト”が重要な意味を持ち始めている。たとえば、人の知性=大脳生理作用の物語、不完全=欠陥を持った神の物語と見れば、グレッグ・イーガンやテッド・チャンとも違和感なくつながってくる。
レムはこの他にも、相対論的(ウラシマ)効果で未来社会にもどってきた宇宙飛行士たちの戸惑いを描く『星からの帰還』(1961)や、宇宙から届くメッセージを解読しようと苦闘する科学者たちの考察『天の声』(1968)を書いた。どちらも、未知のものとの意思疎通の困難さという問題に踏み込んだ作品だ。
『完全な真空』(1971)は書評集である。といっても、ここに収められた書評の対象はどこにも存在しない。レムが書こうとして果せなかった“架空の本”についての書評なのである。理想の作品を想像しながら、なおかつそれについての書評を書くという、極めて倒錯した作品集なのだ。中には思わず読みたくなる傑作もある。アルゼンチンの奥地に忽然とあらわれたフランス『親衛隊少将ルイ十六世』や、失われた天才を探索する旅『イサカのオデュッセウス』などである。物理法則自体がゲームであると説く『新しい宇宙創造説』はイーガンの《直交3部作》のようだ。小説レベルを越えた巨大なアイデアである。
『虚数』(1973)は架空序文集である。「GOLEM XIV」は思考するスーパー・コンピュータの本で、序文だけでなく一部の抜粋が収録されている。GOLEMはプログラムされるコンピュータではない。今日の人工知能を思わせるが、どちらかというと人工生命に近いのかもしれない。レムの描くGOLEMは、既存の頭の悪い人工知能を遥かに超越した上位概念を垣間見せる。それが人間に語りかける様子を一部とはいえ書いているのだから、まさに離れ業に近い。本書が序文集でしか収録できなかったわけもわかる。人間以上の知性が書いた、文章や概念と出会ったらどうなるのかを問いかけているのだ。『完全な真空』も『虚数』も、書かれている本はすべて存在しない。しかし、実在の本を読むのと同等、あるいはそれ以上の衝撃を与えてくれる。
レムはこの他にもユーモアあふれる一連のシリーズものを書いている。1つはレム流の《ロボット》が登場するお伽噺風のシリーズ『ロボット物語』(1964)や『宇宙創世記ロボットの旅』(1965)などだ。ロボットといっても、これらは人工知能の原点サイバネティクスを発展させたもので、アシモフ流のロボットとはずいぶん違う。
もう1つは宇宙探検家泰平ヨン(イヨン・ティーヘ)が、さまざまな惑星や地域を訪れる《泰平ヨン》である。『泰平ヨンの航星日記』(1957/1971)、『泰平ヨンの回想記』(1971)、『泰平ヨンの未来学会議』(1971)、『泰平ヨンの現場検証』(1981)で、もともと文明風刺の色合いが濃かったシリーズだが、後半に行くほど、生物学から宗教論を含む幅広い考察が含まれるようになる。
『泰平ヨンの未来学会議』は、人口問題を解決するために赴いた世界未来会議で、ヨンが幻覚剤を使ったテロ事件に巻き込まれ、奇妙な未来社会に迷い込むお話だ。2013年にアリ・フォルマン監督による『コングレス未来学会議』として映画化され、アニメと実写の混淆したユニークな仕上がりになっていた。
残念ながら、レムの短編は紙版が途切れ電子書籍化も進んでいない。これ一冊だけというのであれば、紙書籍だが、国書刊行会レム・コレクションに含まれる『短篇ベスト10』(2001)がある。クラクフで出版された15編を収録する短篇ベスト選から、さらに10編を選びだしたものだ。上記で紹介した《ロボット》や《泰平ヨン》などレムの主要な短編が万遍なく盛り込まれている。
(シミルボンに2017年2月27日掲載)
《レム・コレクション》の第2期が開始となったのは2021年のこと。現在も継続中ですが、『マゼラン雲』など幻の初期作や、新訳の『インヴィンシブル』、『浴槽で発見された手記』という既訳作品に対する新解釈/新発見まであって目が離せません。泰平ヨンものの最後の作品『地球の平和』も出ています。