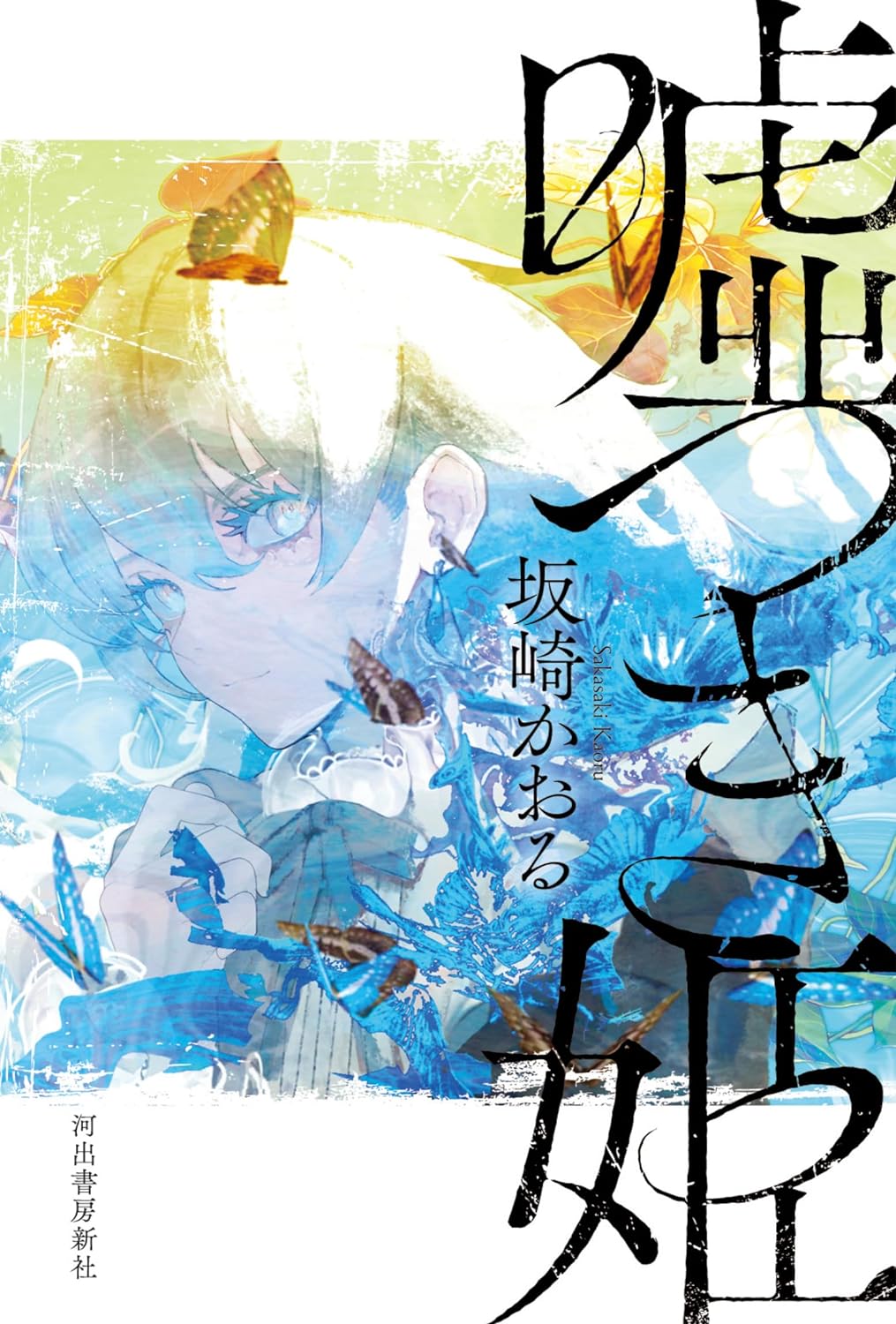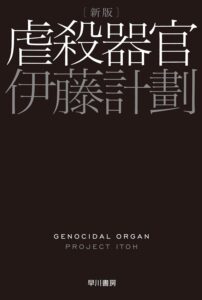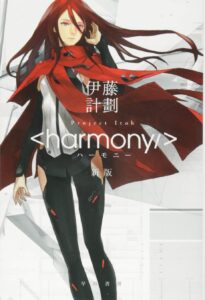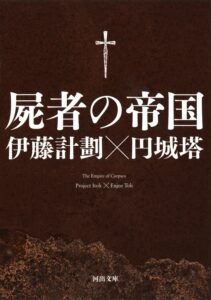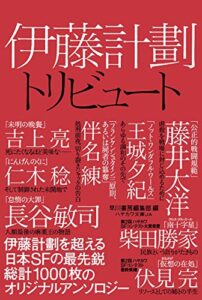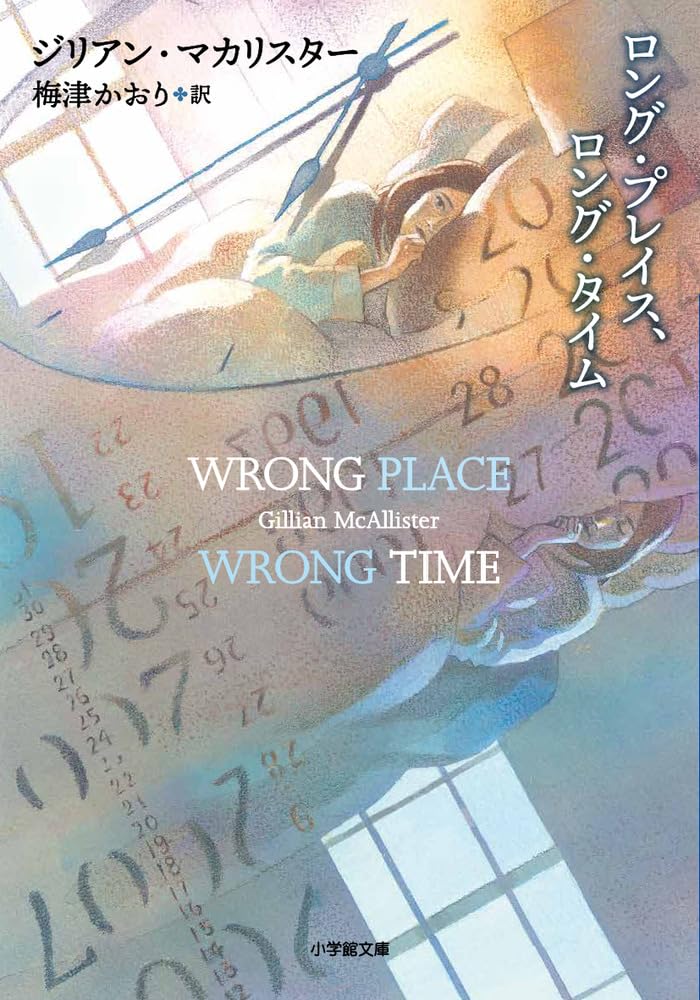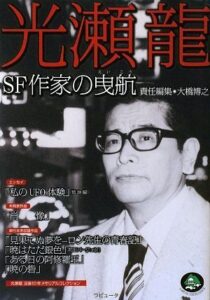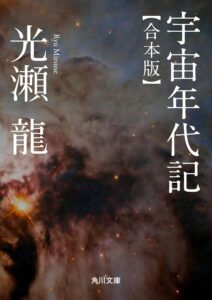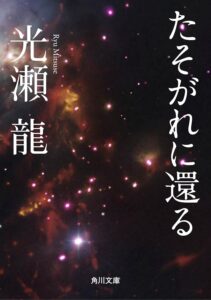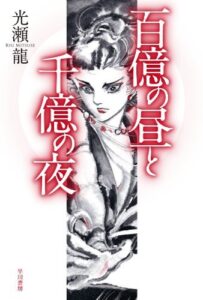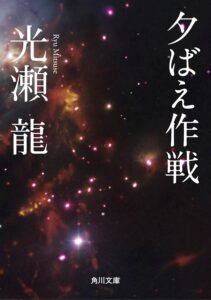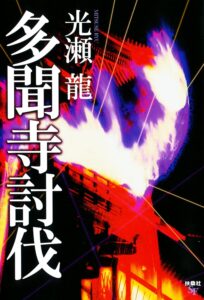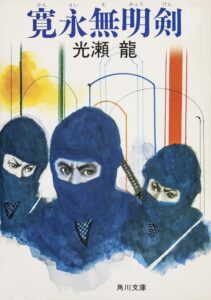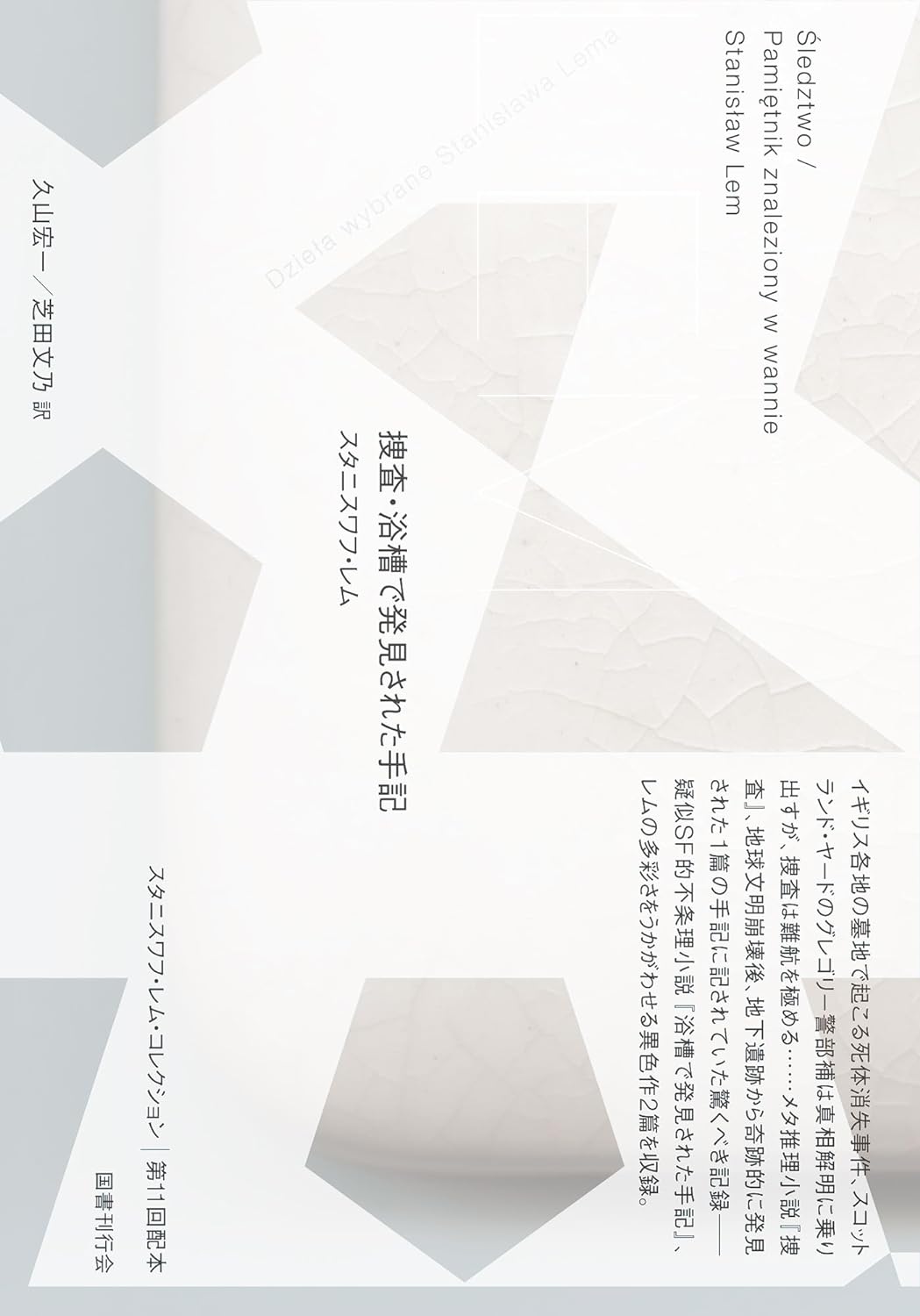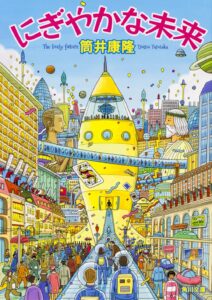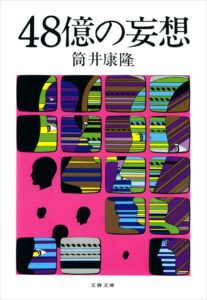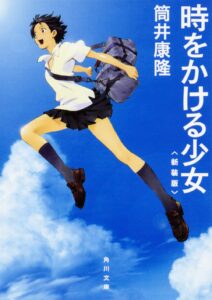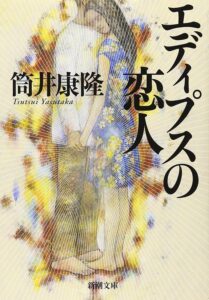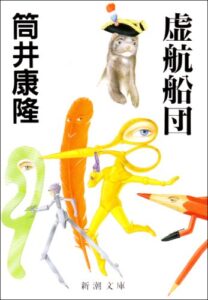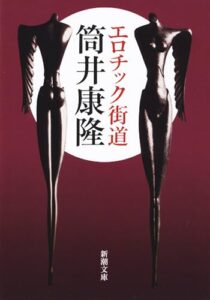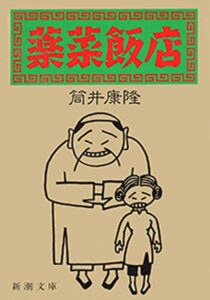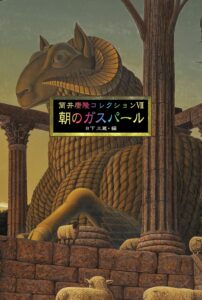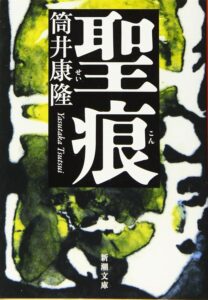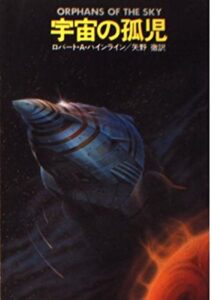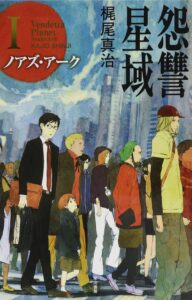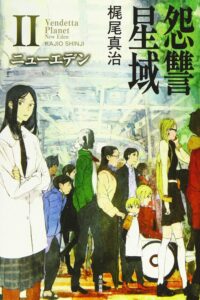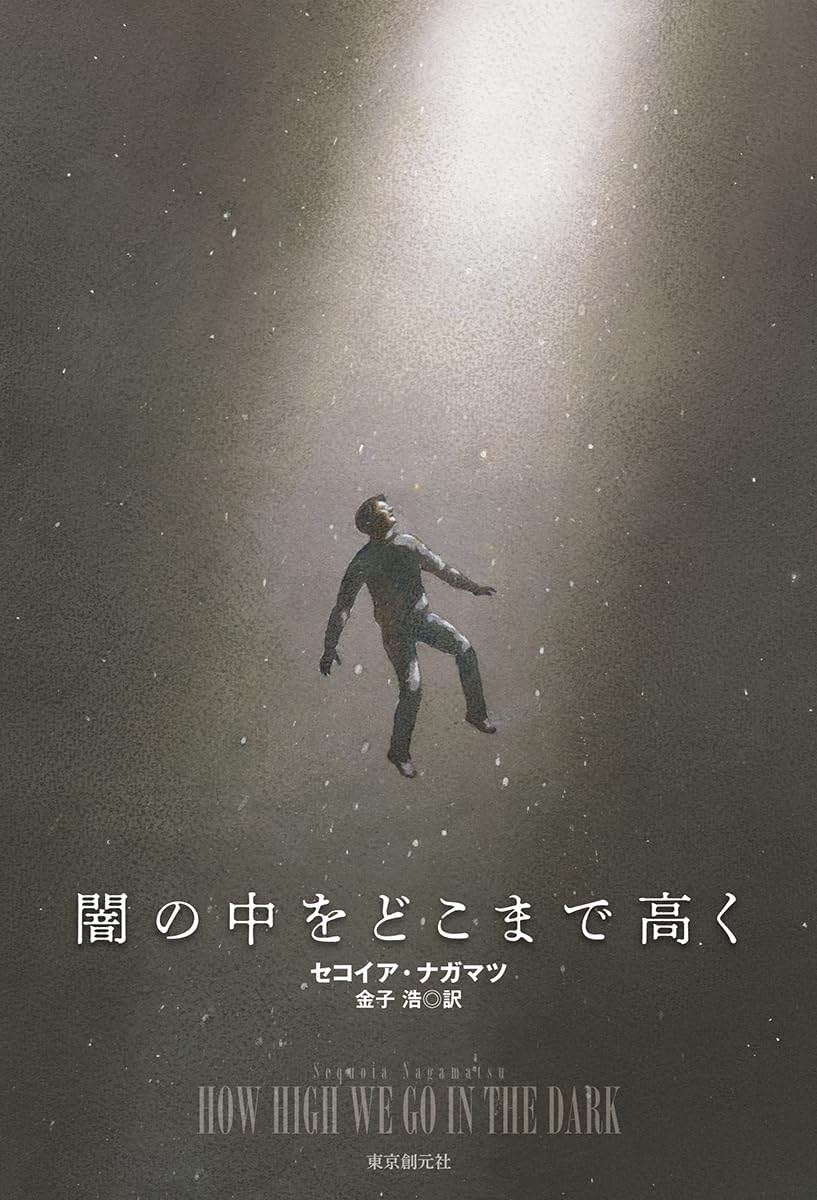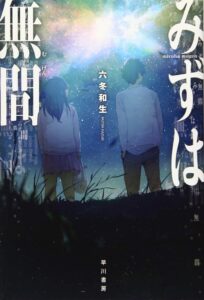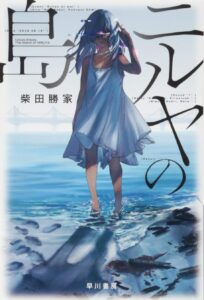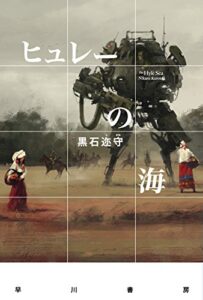今年ハヤカワSFコンテストは、第12回目の公募を迎えています。このシミルボン転載コラムは、(7年前時点で)その意義を捉えなおそうというものです。コンテストの醍醐味として「意表を突く新人登場の瞬間を目撃」というのがありますが、将来どうなるかは簡単には見通せません。以下本文。
早川書房が主催するSF新人賞は、1961年から始まり多くの作家を輩出してきた伝統ある賞だ。ただこの賞は、時代によって大きく性格を変えている。1961年第1回から63年第3回までの「空想科学小説コンテスト/SFコンテスト」と呼ばれた時代は、田中友幸、円谷英二らが審査員に入り、東宝とのタイアップで映画化を目指すというものだった(ただし、映画化まで進んだ作品はない)。入選または各賞に入った作家には、眉村卓、豊田有恒、小松左京、平井和正、半村良、光瀬龍、筒井康隆らがいる。第1世代作家の多くは、唯一のSF新人賞だったこの賞を目標にしていたのだ。
この後11年の空白のあと、1974年の第4回「ハヤカワ・SFコンテスト」では、川田武、田中文雄、かんべむさし、山尾悠子らが(この回のみのアート部門では、加藤直之、宮武一貴らが)登場する。5年を空け、小説専門に戻した1979年の第5回から1992年の第18回までは毎年実施される。野阿梓、神林長平、大原まり子、火浦功、水見綾、草上仁、橋元淳一郎、中井紀夫、貴志祐介、藤田雅矢、柾悟郎、金子隆一、北野勇作、森岡浩之、松尾由美、秋山完ら多数が受賞者に名を連ねた。
しかし後半になると、応募作の減少や入選作のない年が増え、中断を余儀なくされる。以降20年という最長の空白期間が生じる。この間、新人は「小松左京賞」「日本SF新人賞」や、「日本ファンタジーノベル大賞」「日本ホラー小説大賞」、あるいは多数生まれたライトノベルの新人賞など、他ジャンルの賞に移っていった。結果として、2002年から始まった早川書房のSF叢書《Jコレクション》では、新鋭作家のほとんどが別の新人賞を経た作家で占められるようになる。そこで2013年に再スタートした「ハヤカワSFコンテスト」では、
(前略)世界に通用する新たな才能の発掘と、その作品の全世界への発信を目的とした新人賞が「ハヤカワSFコンテスト」です。
中篇から長篇までを対象とし、長さにかかわらずもっとも優れた作品に大賞を与え、受賞作品は、日本国内では小社より単行本及び電子書籍で刊行するとともに、英語、中国語に翻訳し、世界へ向けた電子配信をします。
「募集開始のお知らせ」より
と、新たな目標「世界展開」を掲げ通算回数をいったんリセット、リニューアル感を鮮明にした。六冬和生『みずは無間』は、新生ハヤカワSFコンテストの第1回大賞受賞作である。
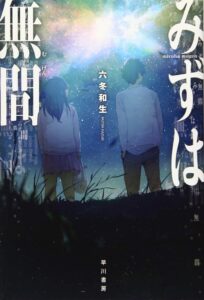 カバー:loundraw
カバー:loundraw
主人公はAIである。人間の意識が転写されたもので、遠宇宙へと飛び続ける無人宇宙機に搭載されている。膨大な時間を経ても機能するように、物資の調達、自己改変をする仕組みを持っている。しかし宇宙は空虚なままで、何ものとも遭遇することはない。やがて、AIは自身をコピーし、銀河に遍く散開させる。刻み込まれた“みずは”の記憶とともに。
コピーされた人格という概念は、もはやSFのスタンダードである。生命に束縛されないから、何千何万年の時間スケールで宇宙を航行しても何の問題もない。イーガン『白熱光』がそうだった。小松左京『虚無回廊』に登場する“人工実存”はその一種になる。ところが、本書には主人公(AIの人格)の他に、みずはという恋人が現れる。きまぐれで直情的、食べることに対する執着、遠く離れた恋人にまで作用する暗い存在感。その“みずは”との泥沼の人間関係が時空間に拡張されていく異様さが、まさしく本書のポイントとなる。宇宙機のAIが、現代日本人の形而下的な感情に翻弄されるわけだ。読み手に対するインパクトという意味で、21世紀のSFコンテスト、今のSFの立ち位置を再認識できる作品といえる。
第1回では、この他に坂本壱平『ファースト・サークル』と小野寺整『テキスト9』、下永聖高『オニキス』(短編集)が、最終候補作から書籍化されている。
翌年、第2回ハヤカワSFコンテストでは、大賞に柴田勝家『ニルヤの島』が選ばれた。独特のペンネームと、侍のコスプレが話題を呼ぶ。
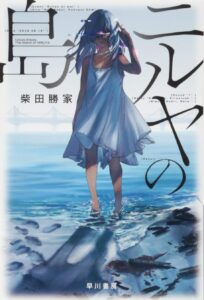 カバー:syo5
カバー:syo5
書名の「ニルヤ」は、沖縄神話の中のニライ・カナイ(理想郷)の別称ニルヤ・カナヤに由来するものだ。主な宗教で死後の世界が否定され、人々は自身の記憶を叙述し記録することが、死を克服する手段になると考えるようになった21世紀末。そんな神のいない世界の中で、島々を長大な橋で結ぶことで成立したミクロネシア経済連合体には、死後を信じる宗教が生きていた。カヌーで死者を送り出す彼らの宗教にどんな意味があるのか。文化人類学者や模倣子行動学者たちは、それぞれの立場からその謎に迫っていく。
物語は4つのセクションに分かれ、それぞれが平行に進んでいく。「Gift 贈与」は、2069年に文化人類学者が、島に残る伝承の語り手を訪ねるところから始まる。「Transcription 転写」では、島で休暇中の模倣子(ミーム)行動学者が死後を信じる統集派の葬列と出会い、「Accumulation 蓄積」は、橋が完成する前、現地で危険な潜水作業に就く父娘の物語である。チェスや将棋に似たゲームをひたすら続ける「Checkmate 弑殺」の章は、不連続な時間の流れ方となる。人の記憶する時間は断片的で連続しない。それは「叙述」されることで1つの物語になる。叙述という言葉は伝承(語り伝える)文学との関係を意識したと、〈SFマガジン2014年1月号〉の著者インタビューにもある。電脳世界におけるデータ化された人間は、イーガン『順列都市』の強い影響を受けたという。ポリネシア=沖縄神話と、今風のヴァーチャルな世界観を結ぶ野心作といえる。
第2回では、最終候補作の神々廻楽市(ししば・らいち)『鴉龍天晴』と、倉田タカシ『母になる、石の礫で』が書籍化された。また伏見完はアンソロジイ『伊藤計劃トリビュート』に最初の作品を寄せている。
第3回ハヤカワSFコンテストの大賞受賞作は、小川哲『ユートロニカのこちら側』である。連作短編形式で書かれている。ユートロニカとは、ユートピア+エレクトロニカ(電子音楽)から作られた造語だ。
 カバー:mieze
カバー:mieze
サンフランシスコの郊外に、アガスティアリゾートと呼ばれる都市が建設される。そこは見たもの聞いたものなど、全ての個人情報を企業に提供する代わりに、生活が保障されるある種のユートピアだった。個人の行動は事前に推測できるため、犯罪も予め抑えられる。そういった利便性は、プライバシーと引き換えに与えられる。物語は6つの章に分かれ、リゾートにかかわった人々の運命を描いている。
犯罪者を予防拘束するといえば、映画やTVシリーズにもなったディック「マイノリティ・リポート」があり、Google的なIT企業がプライバシーを失わさせるデイヴ・エガーズ『ザ・サークル』、存在しなくなった都市を電脳空間に再現するトマス・スウェターリッチ『明日と明日』など、アイデア自体には先行する作品がいくつかある。しかし、本書は楽園の暗黒面を、陰謀(秘密組織や国家が黒幕)のようには描かない。その周りに住む(こちら側の)人々を点描することによって、自由意志とは何かを表現しているのだ。
第3回では、佳作となったつかいまこと『世界の涯ての夏』が書籍化されている。
第4回ハヤカワSFコンテストでは、優秀賞が2作品、黒石迩守(くろいしにかみ)『ヒュレーの海』、吉田エン『世界の終わりの壁際で』、及び特別賞の草野元々(くさのげんげん)『最後にして最初のアイドル』が選ばれた。審査委員の意見が割れたため、大賞受賞作は出なかった。
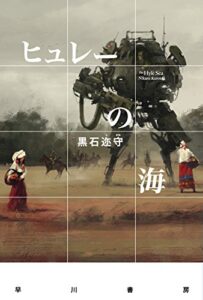 カバー:ジェイコブ・ロザルスキ
カバー:ジェイコブ・ロザルスキ
未来のいつか。文明は混沌に呑み込まれ崩壊、情報的記録の海が地球を覆う。人類はシリンダ型の塔のような都市に住み、都市は7つの序列を持ち、さらに資本家と労働階級に分かれる。人類はある種の情報生物となって世界に適応している。そんな中、過去の記録にある本物の海を見ようと、下層民の少年少女は旅立つ。
『ヒュレーの海』のヒュレーとは、アリストテレス哲学でいう、形相(エイドス)と質料(ヒュレー)に由来する。情報生物が主人公なので、ソフト/ファームウェアとハードウェアとでもいえばよいのか。現職プログラマーの経歴を生かした、ITの専門用語をルビで駆使する異形の世界が印象的だ。
 カバー:しおん
カバー:しおん
未来の東京は山手線の内側に壁を築き、その外部との出入りを遮断している。内側にある〈シティ〉は、大規模な環境変動から逃れるための箱舟なのだ。外側で育った主人公は電脳ゲームの名手だったが、ある日アルビノの少女や奇妙な人工知能と出会ったことで、内側世界の秘密を知ることになる。
物語では、ゲーム空間でのバトルと、リアル世界である壁内側/外側の争いが並行して描かれている。優秀賞受賞の2人は、ともにオンラインサイト〈小説家になろう〉で活動していることでも話題になった。
「最後にして最初のアイドル」は120枚ほどの中編小説だが、この題名通りステープルドン『最後にして最初の人類』をベースに、その主体が人類ではなくアイドルだったら、という驚くべき発想で書かれている。電子書籍でベストセラーに上がり、『伊藤計劃トリビュート2』に収録されるなど注目を集めた。
ハヤカワSFコンテストは2017年で第5回目を迎える。応募総数こそ、ラノベ系やネット系新人賞に比べて少ないが、入選作を見る限り応募作の水準は相当高い。発足の趣旨に沿った世界展開が図られ、新人発掘の場として機能していくことを期待したい。
(シミルボンに2017年2月7日掲載)
国際化を謳ったハヤカワSFコンテストですが、英訳や中国語訳などの実績はまだないようです。この趣旨は、VG+主催によるかぐやSFコンテストで実現しています。なお、5回から11回までのコンテストについては、このページからリンクを逆にたどることで読むことができます。