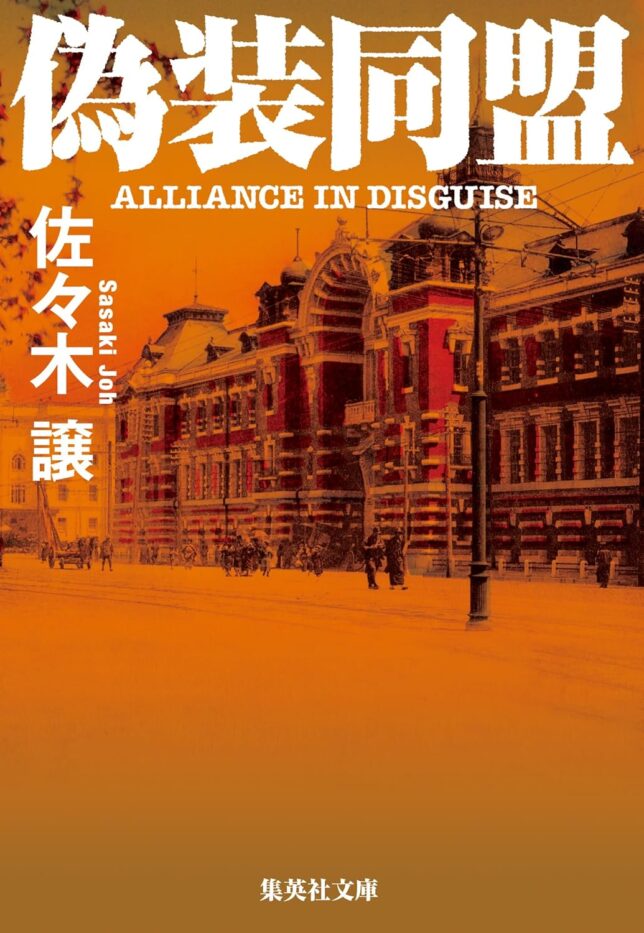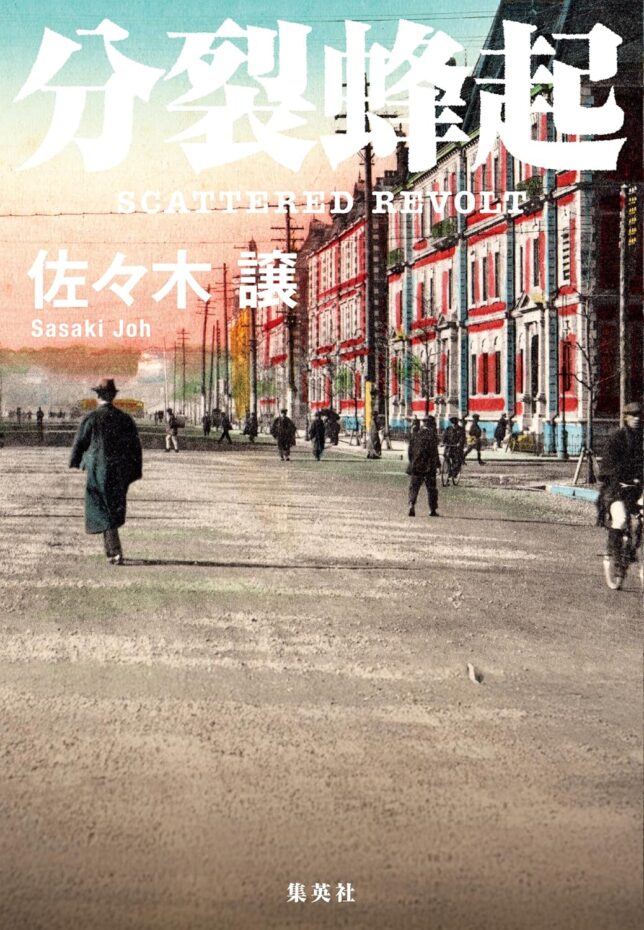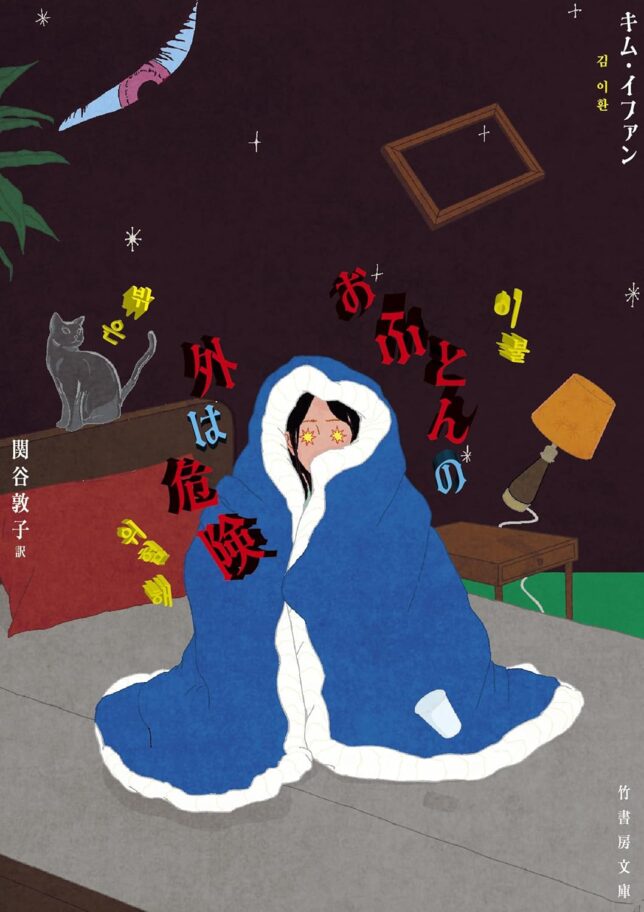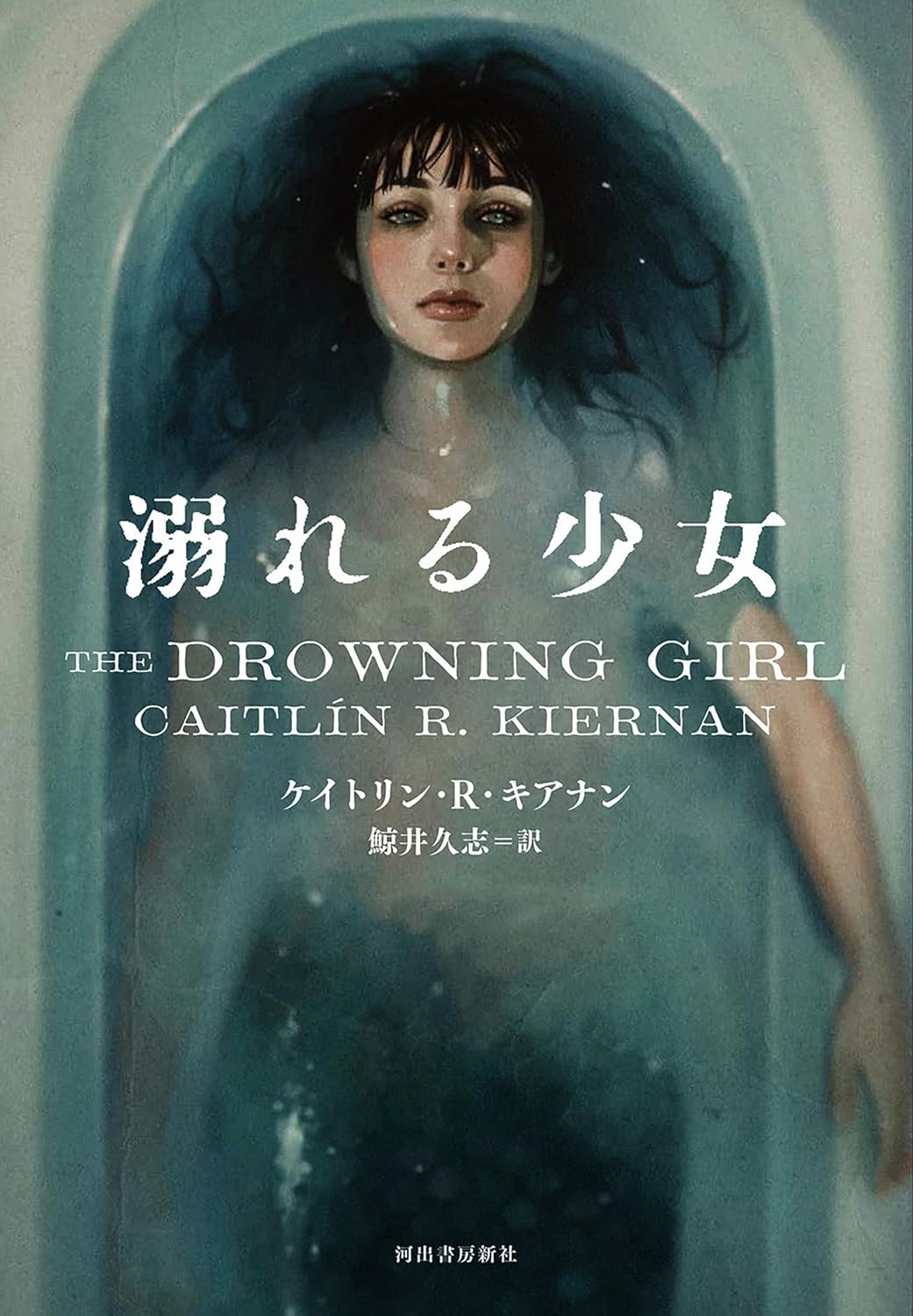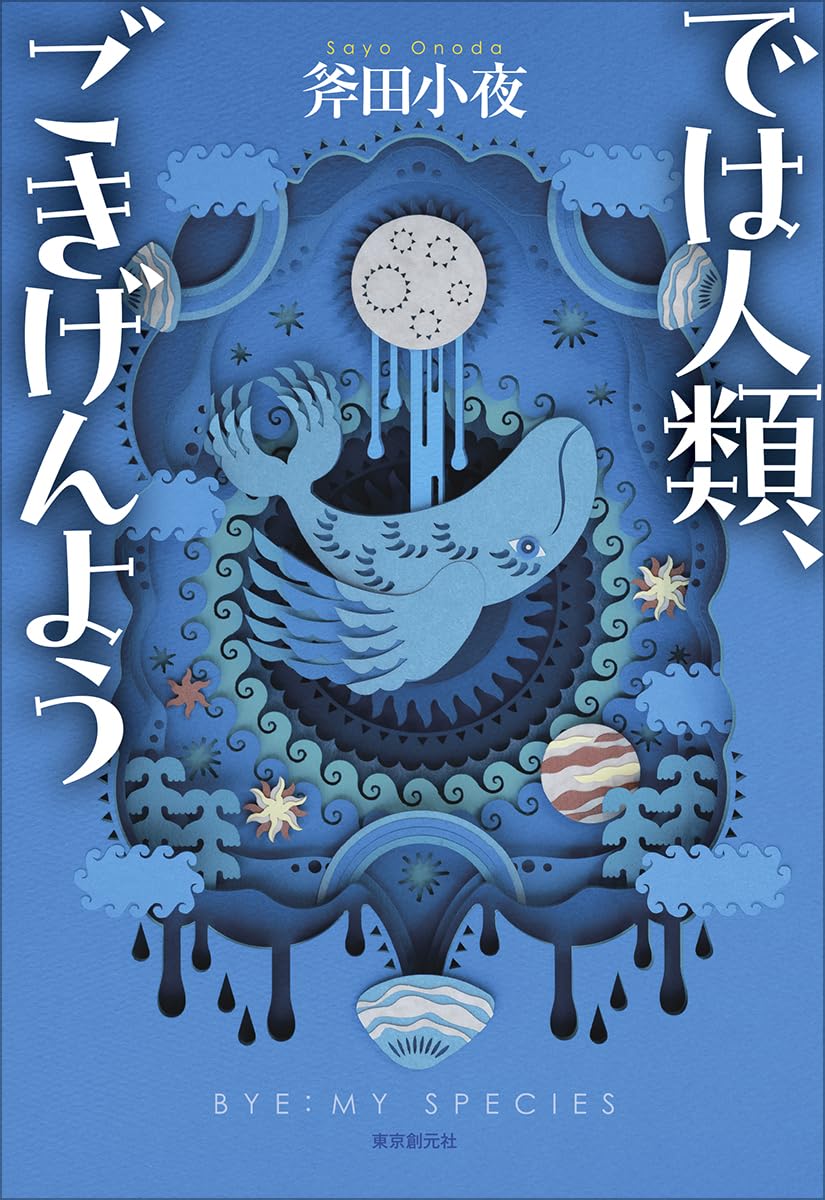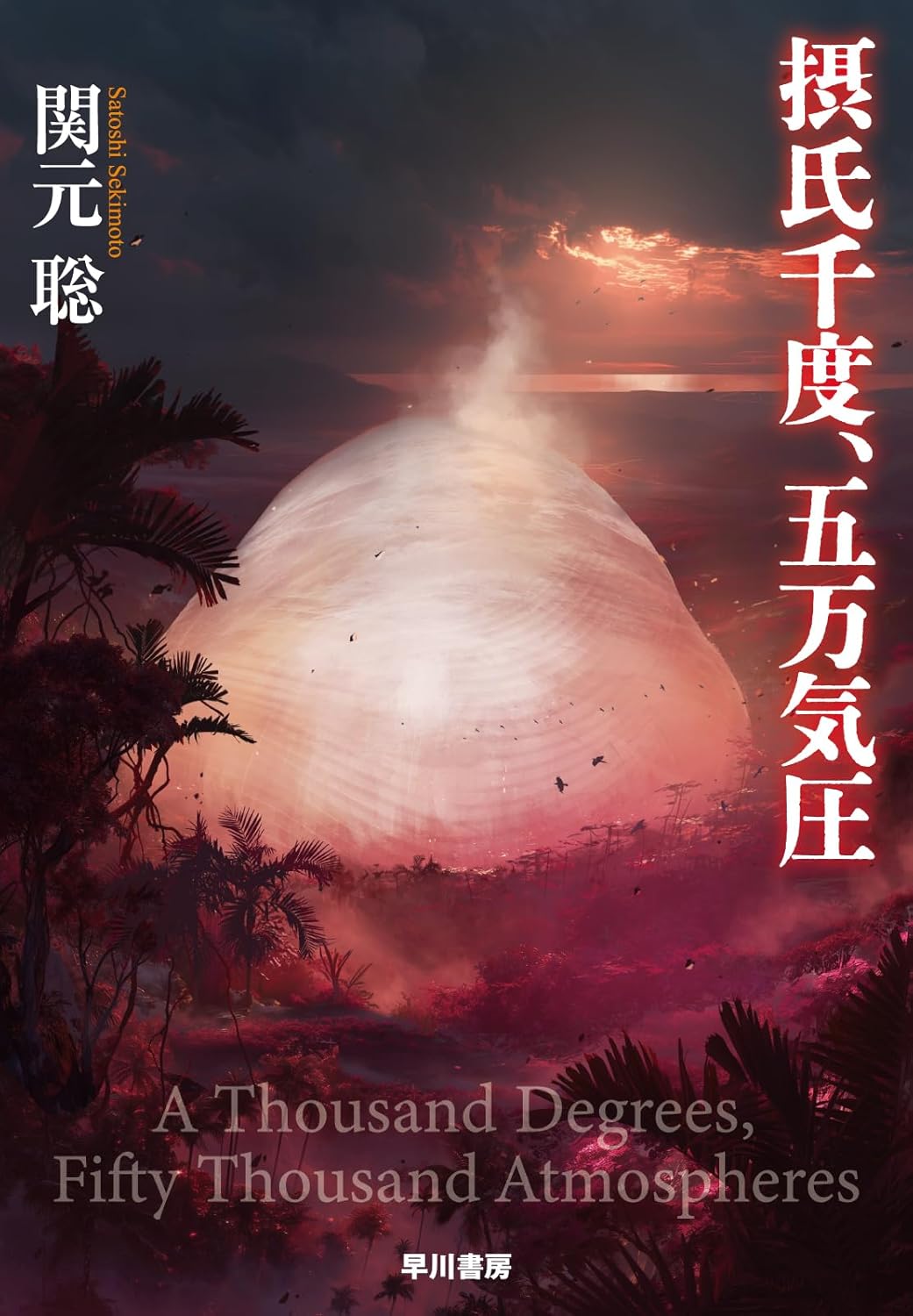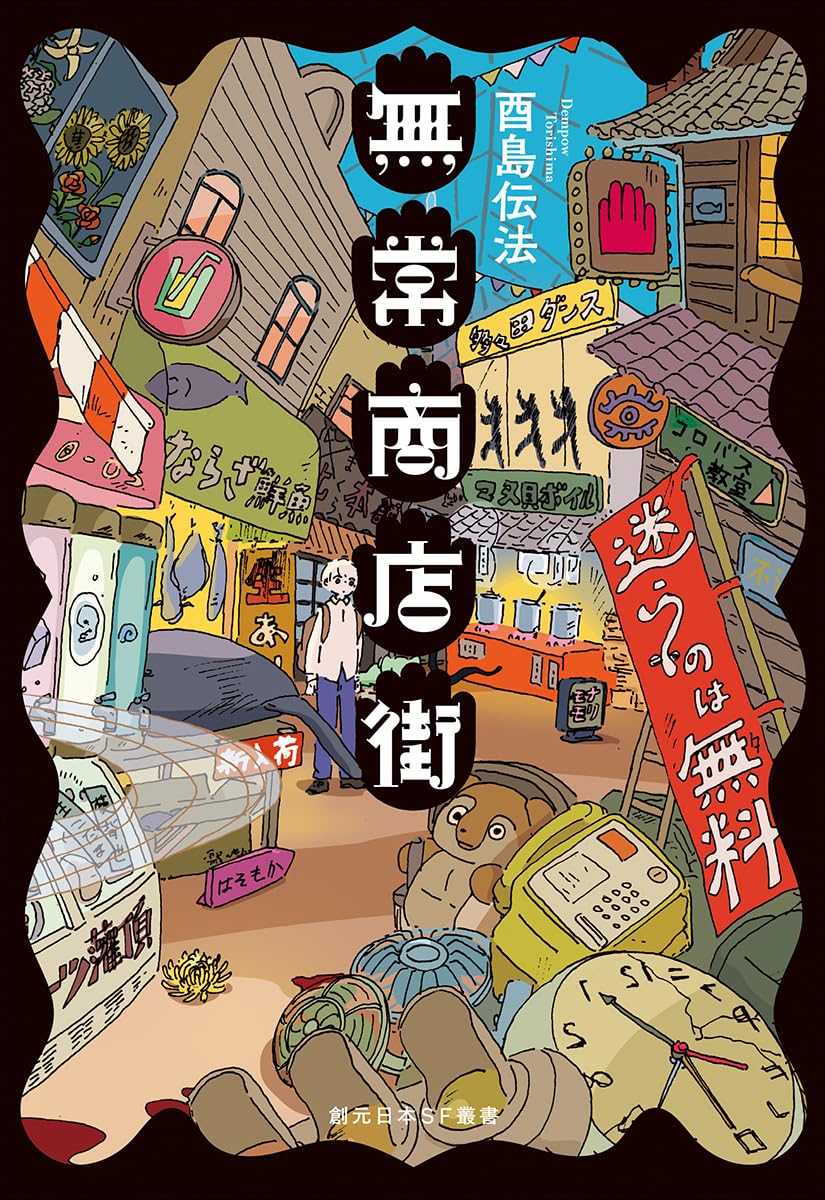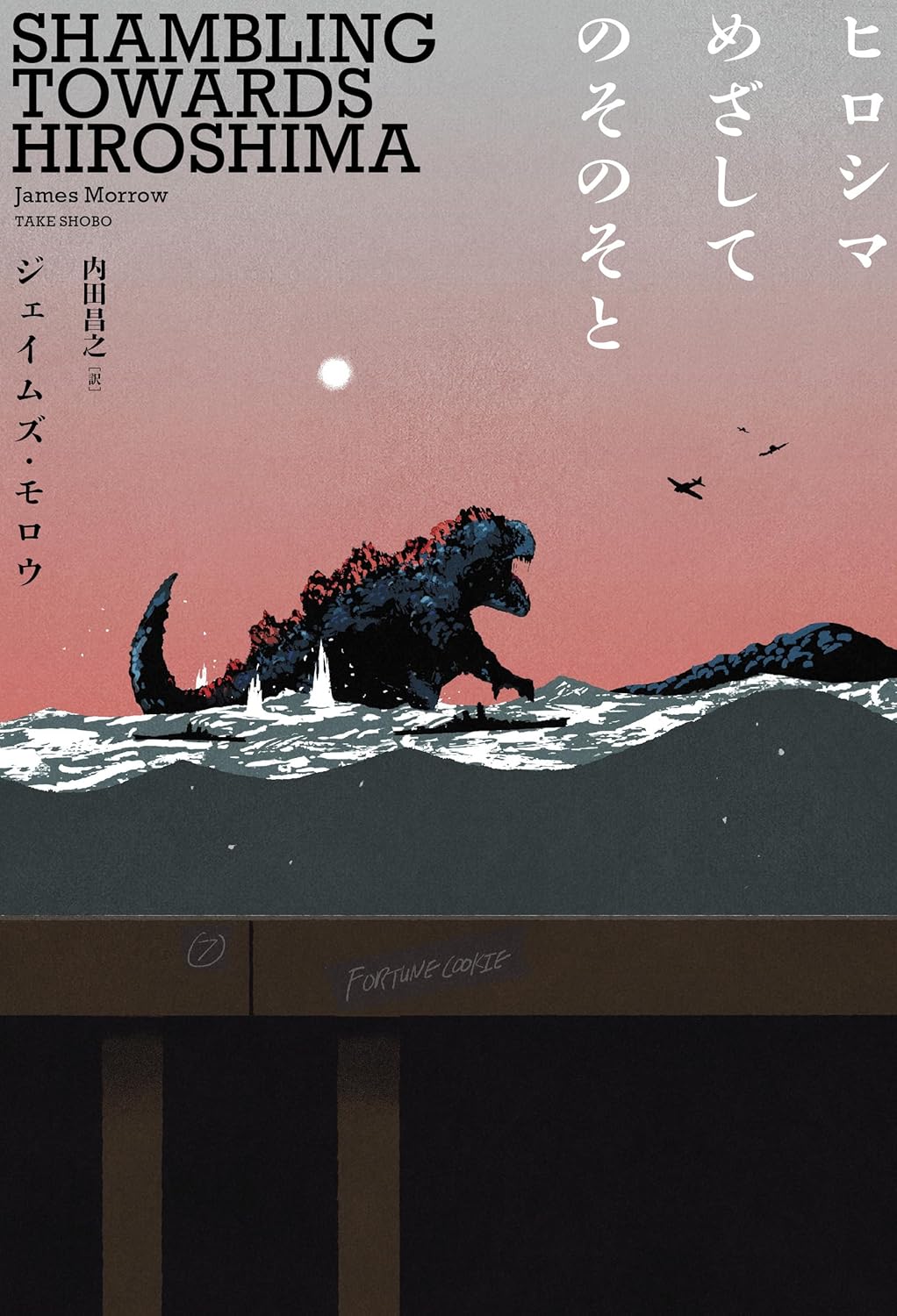装幀:田中久子
第13回ハヤカワSFコンテスト特別賞受賞作。著者は1980年生まれで、本作がデビュー作となる。版元に本作の専用ページができている。最近のコンテスト受賞作は、たとえ地球規模の問題でも個人の視点からミニマムに描く「新たなセカイ系(シン・セカイ系)」とでもいえる作品が目立つ。ただし、そのセカイは地球温暖化と民族/難民差別というリアルなものに直結する。
〈ヘヴンズガーデン〉は近未来のどこかに置かれた、ある種のホスピスである。温暖化の影響が及ばないグリーンフィールズにあり、湖に面した低層の建物〈パレス〉と緑に包まれた森からなる。ここにやってくる超富裕層の人々は、巨額の財産をすべて寄付して安らかな/希望通りの死を選ぶのだ。それが自治区の収入となり、受け入れる難民の保護に充てられる。主人公は施設で働くコーディネーターだった。
ホスピスと言っても、ここでは肉体的な苦痛を和らげるのではなく、精神的な苦しみや罪悪感を贖罪する。地球温暖化がさらに進んだ世界、居住可能な地域は縮減し大量の難民が発生する。富裕層は快適さが残る北か、超高層のタワーに閉じこもり、難民を排除する。そこに難民を受け入れる自治区が作られ、篤志家(富裕層の一部)の財産贈与で運営がなされる。
主人公はさまざまなゲストを迎えて自死するまでの要望を聞き、施設に勤める従業員や三毛猫の姿をした管理人と交流する。彼らの厳しい境遇は、物語の中で徐々に明らかになっていく。優しい登場人物ばかりだが、物語の全体に死と破滅の影が見え隠れる。リアルさをちょっと踏み越えた設定(ヘヴンズガーデン)、数奇な運命を経た人物の心の機微(弱さや精神的外傷)を描き出す手法は、菅浩江の《博物館惑星》を思わせる。
選考委員の評価(抜粋)は以下の通り。小川一水:この締めくくりが主人公にとって幸福なものなのかそうでないのか、わからない。未知を残した余韻に感嘆して、改めて大賞に推した。神林長平:いつなのか、本当にそういう時が来るのかは、だれにもわからない。このわかりにくい書き方が、〈物語の力〉を殺いでいる。菅浩江:「主人公の魂の落ち着き先」=「読者の納得」は明確に打ち出した方がよかったと思います。ですが、わたしはこの雰囲気がとても好きでした。塩澤快浩:これは果たして小説なのか、死に向かう人たちのドキュメントに過ぎないのでは、という疑問が生じてしまった。ただ、メッセージとしての強さは比類ないものがある。
関元聡の作品と同様、審査員の見解は概ね一致している。この作品では、結末の「わかりにくさ」が難だった。単行本化の段階で改善されたと言えるが、まだモヤモヤするのは、全体のトーンが死=救いのように読めてしまうからだろう。死ではなかったとしても、果たして主人公は救済されたのか。
- 『摂氏千度、五万気圧』評者のレビュー