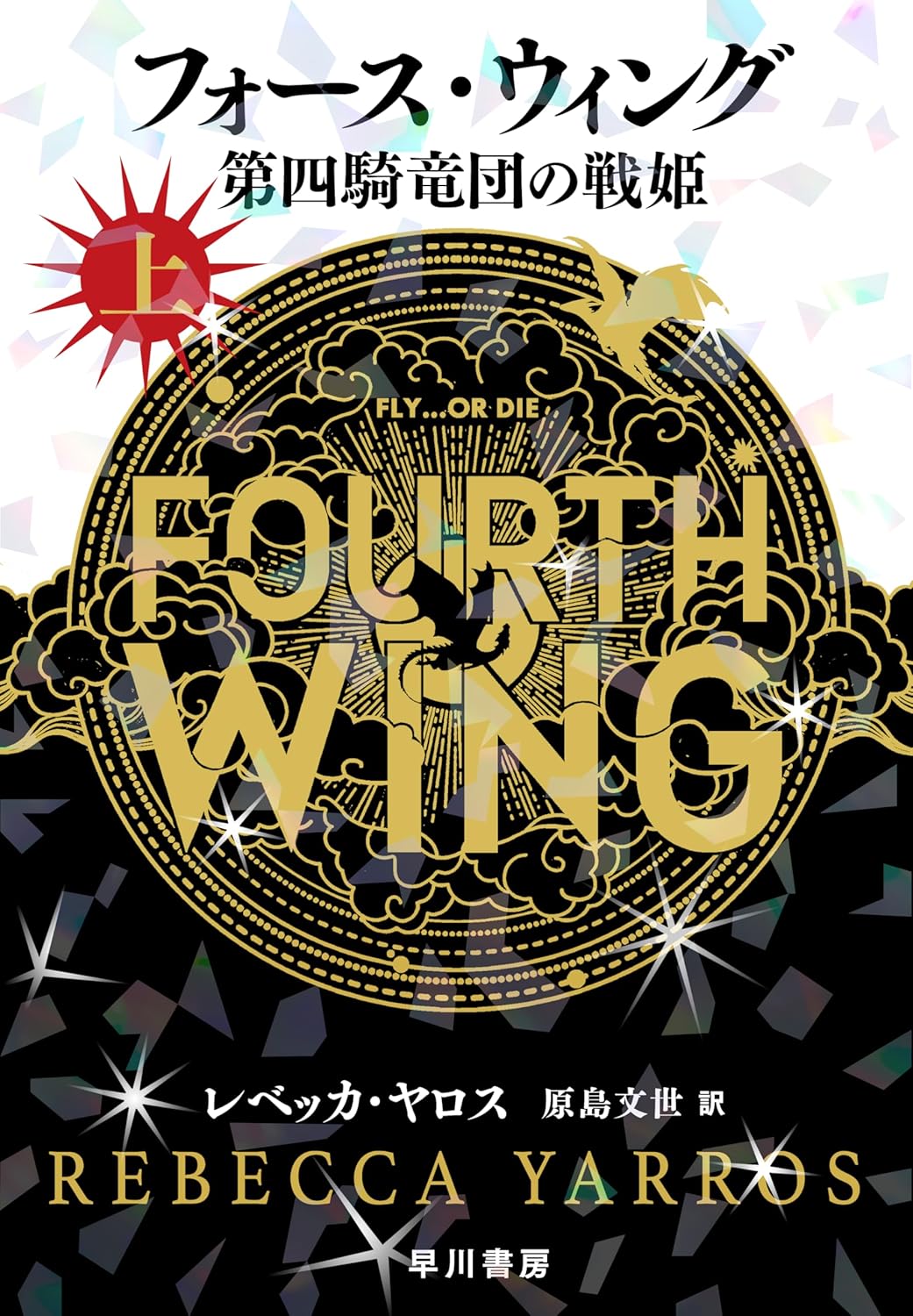画像:(C)jodiecoston/Getty Images
マンカインドmankindと一語で書いてしまうと、われわれ人類のことになる。ではマン・カインド man kindとはいったい何か、人類を継ぐもの? 本書は、藤井太洋がSFマガジン2017年8月号~21年8月号まで連載した作品を(テクノロジーと社会状況の激変に合わせ)大幅に加筆修正した最新長編である。書き始められた当初、COVID-19はまだ現れておらず、BERTもGPTも、CRISPER CAS9も一般には知られていなかった。
2045年、南米のブラジル、ペルー、コロンビアが国境を接する地域の小さな市が独立を宣言する。市は合法的な麻薬生産で財を成していたが、国から高率の関税を課せられたからだ。市の武装解除を巡って公正戦が行われることになった。ブラジル政府は実績あるアメリカの民間軍事企業に委託、しかし独立市側の防衛隊には無敗を誇る軍事顧問が就いていた。主人公のジャーナリストは、そこで信じられない光景を目撃する。
配信記事には自動でレーティングが付き、信用度が低いものは配信されない。公正な判断に基づくはずが、原因不明で悪い点数となることがある。物語では、量子技術を使った事実確認プラットフォームを担う企業で、原因究明に奔走する若手担当者も登場する。やがて、一見無関係だった軍事顧問や軍事企業を結ぶ糸が見えてくる。
この作品のベースには、ドローンを主体とした競技のような限定戦争(戦闘員だけが死ぬ)を描く「公正的戦闘規範」と、分断されたアメリカが内戦状態となる「第二内戦」が含まれる(どちらも作品集『公正的戦闘規範』に所収)。さらに格差を象徴するニードルと呼ばれる超高層住宅がそびえ、ビッグテックの最先端技術に翻弄される不確かな(ある意味おぞましい)未来が浮かび上がる。しかし、作者はディストピアを描いているわけではないのだ。
南米が起点なので、小松左京『継ぐのは誰か?』(1972)の結末を引き継いだような始まりだが、本書の「人類を継ぐのは何か」は、小松の問題提議「(いまの人間の)技術に追いつけない叡智」に対する一つの回答とも読める。半世紀を経てようやく得られた解により、見知らぬ明日はポジティヴな希望に結びつくのかもしれない。
- 『近未来を見すえる確かな視点 藤井太洋』評者の作家紹介記事