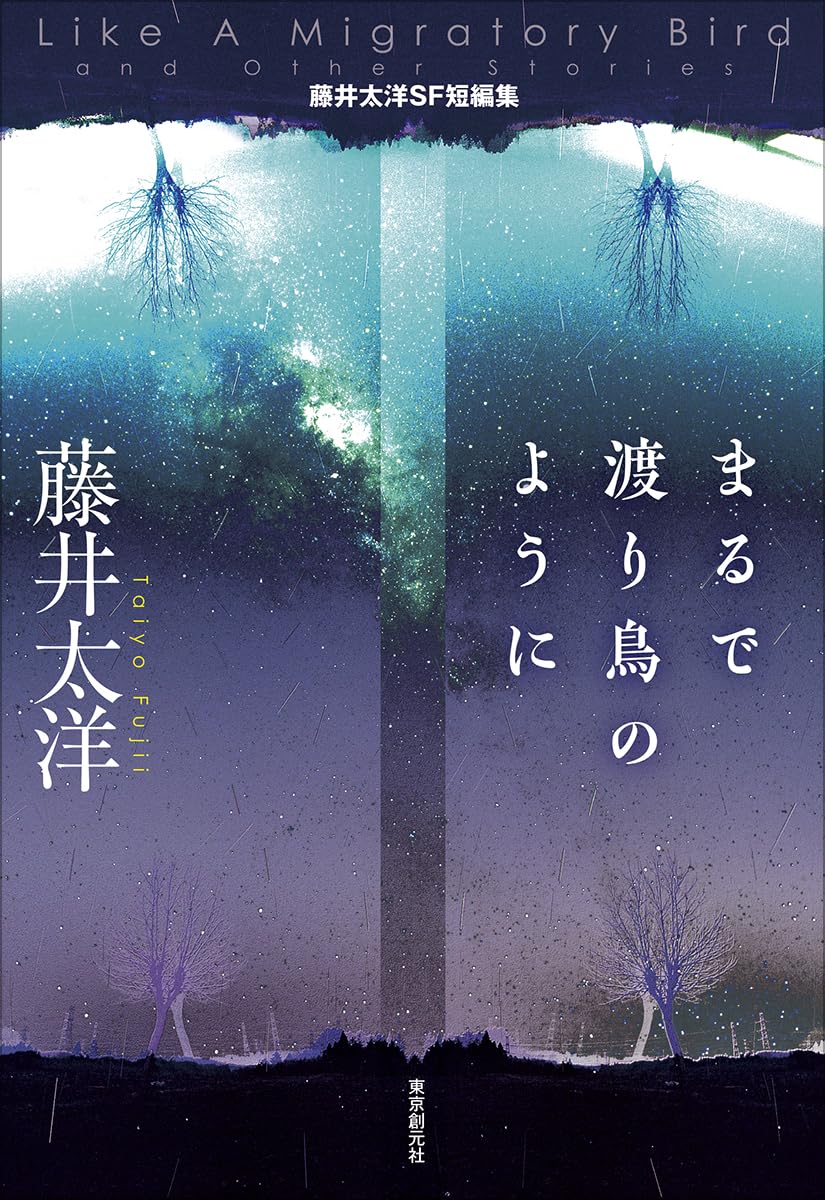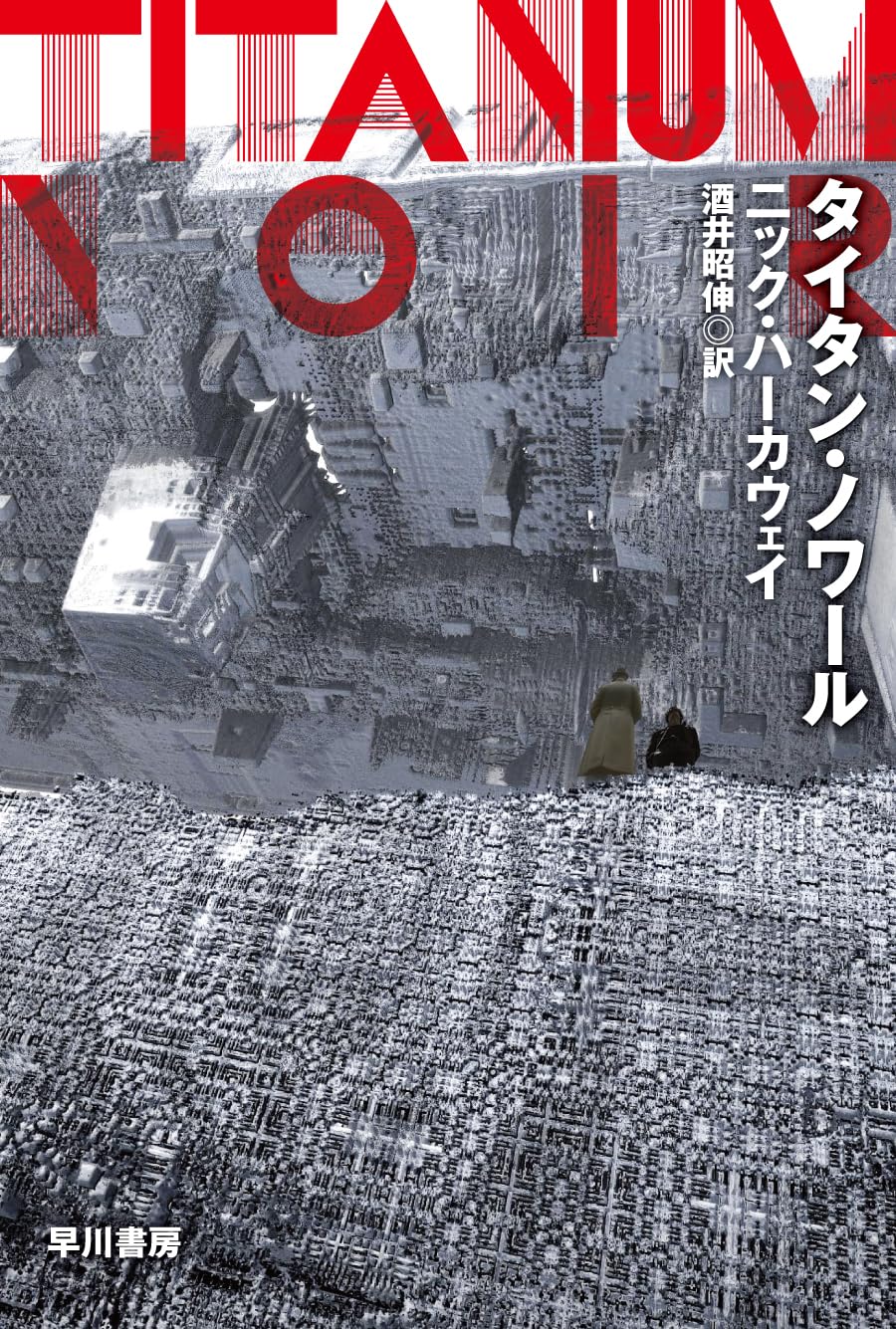カバーデザイン:岩郷重力+Y,S
カバーデザイン:岩郷重力+Y,S
昨年出た『AIとSF』の第2弾。前巻は22編(22作家)を集めた大部のアンソロジーだったが、今回11編と半減、しかし書籍としてはこちらの方が100ページ余り分厚い。巻頭に長谷敏司のノヴェラ(300枚強の短めの長編)を収めるなど、中編クラスがメインのためだろう。AIテーマが熟れたせいなのか、昨年版より絞り込まれた作品が多いように思われる。
長谷敏司「竜を殺す」兼業作家の一人息子が殺人を犯す。子どものことを分かっていなかったと嘆く主人公は、被害者の背景を調べるうちに思いがけない事実を知る。
人間六度「烙印の名はヒト 第一章 ラブ:夢看る介護肢」〈介護肢=ケアボット〉は〈メタ〉を自己肯定感で満たすために働く(新作書下ろし長編の冒頭部分)。
池澤春菜「I traviati 最後の女優」最後の舞台女優と呼ばれる主人公は、インプラントしたパーソナルAIを使ってAI単体ではできない最高の朗読劇を演じようとする。
津久井五月「生前葬と予言獣」災害危険区域から住民を移転させるプロジェクトで対話型AIが説得に使われる。しかしなかなか理解は得られなかった。
茜灯里「幸せなアポトーシス」国のノーベル賞級卓越研究のため、不老不死研究で知られる生命科学者の脳情報がAIにインストールされる。期待通りの成果が生まれ始めるが。
揚羽はな「看取りプロトコル」アンドロイドAIが終末期医療で看取るのは、火星から帰還した末期がんの患者だった。患者は意外な要求をしてくる。
海猫沢めろん「月面における人間性回復運動の失敗」月のオートタクシーを運転するAIと人間のペアのところに、危ないお客が乗ってきてかみ合わない会話を交わす。
黒石迩守「意識の繭」世界に蔓延する電脳昏睡症の治療のため、Rアバターが開発される。外部から脳を刺激するBCI用のアプリだったが、やがて病の真相が明らかになる。
樋口恭介「X-7329」意識を持つAI、X-7329が最後のアナログ=人間を排除するために森の中を徘徊する(ChatGPT-40などを全面的に使用して生成した作品)。
円城塔「魔の王が見る」アレケトが3日かかって道路を横断し、世界がちぐはぐに見えて、NNはニューラル・ネットワークではなくネームド・ネームレスである。
塩崎ツトム「ベニィ」ある家族の兄弟たちの運命は、1950年代にアメリカの国家プロジェクトとして密かに進められたある計算機の開発へと収斂していく。
目の前、10年後の未来を舞台とする「竜を殺す」は家族の物語である。単身赴任中のため不在の妻、解雇通知を受けた塾講師で兼業作家の夫、親や友人よりスマホAIに依存する(この時代ではふつうの)高校生の3人家族だ。この社会/この家族で起こる問題は、いまの時点で(少なくとも兆しが)あるものばかりといえる。たとえば作家はAIに流行を分析させ、AIが生成する物語を編集して作品にする。善し悪しとは無関係に、AIは欠かせない道具になっている。
アンソロジーで目立つのはAI時代の作家のあり方だろう。「竜を殺す」の作家はAIのオペレータのようであるし、その現在形がプロンプトで物語を(実際に)生成した「X-7329」なのだ。「ベニイ」では複雑な家族関係と偽史(架空のコンピュータ史)を絡める中で、小説を含む文化自体の存在意義が問われている。
「烙印の名はヒト 第一章 ラブ:夢看る介護肢」と「看取りプロトコル」では、終末期用介護士/看護師アンドロイドが出てくる。「I traviati 最後の女優」「幸せなアポトーシス」「意識の繭」では、脳インプラント型アシスタントや脳の複製=ツインがキーとなっている。これらは、拡張(増幅)機能としての(いわゆる人工知能に捕らわれない)AIが人に何を及ぼすかが描かれる。「生前葬と予言獣」はVRを組み合わせて人に希望を抱かせるアイデア、「月面における人間性回復運動の失敗」や「魔の王が見る」はテーマを逆手にとる独自の展開ながら面白い。