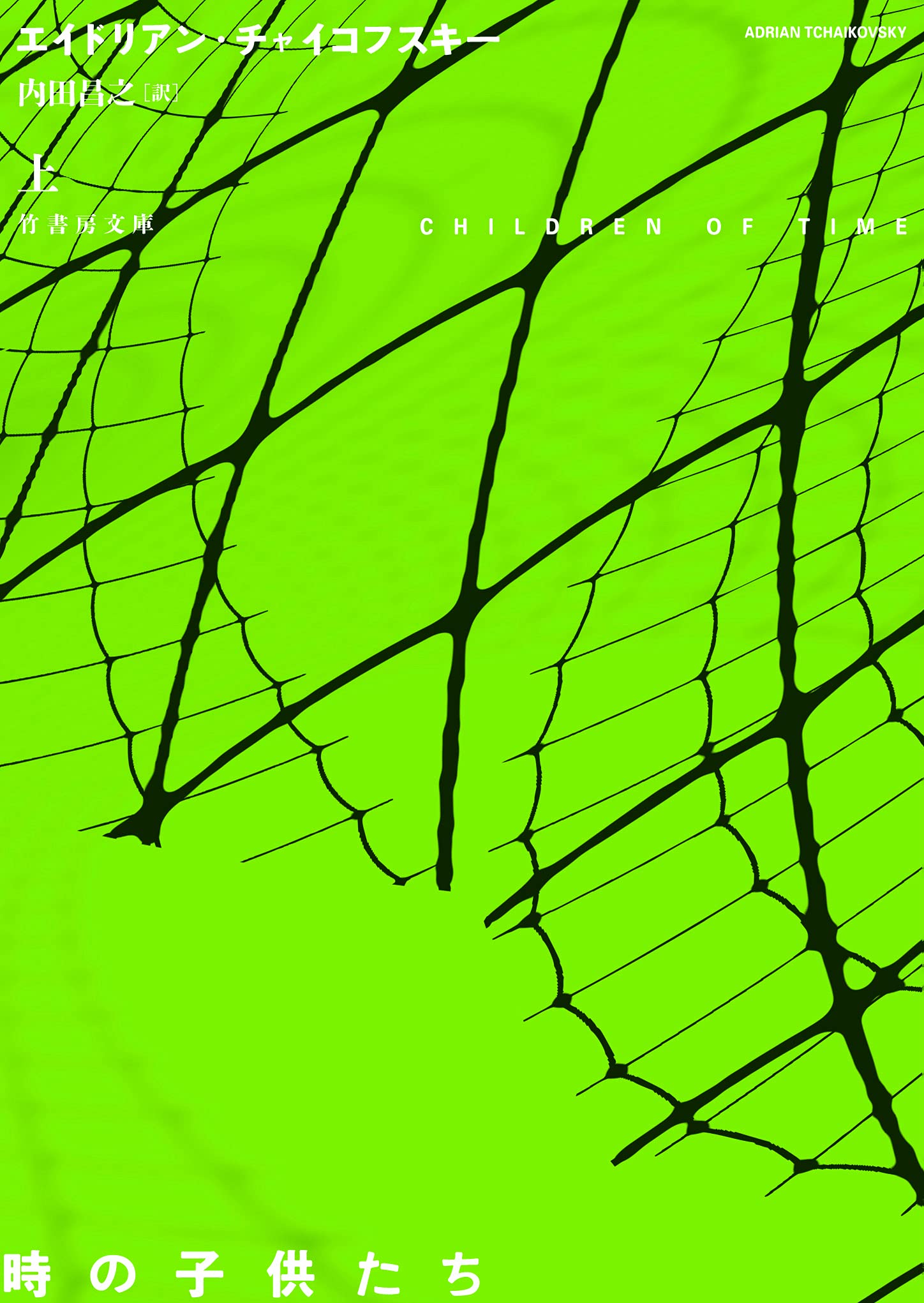カバーデザイン:川名潤
牧眞司編によるラファティ・ベスト版の第1集「アヤシイ編」(編者自ら付けた愛称)。ハヤカワSF文庫で過去に出たラファティは本書を含め5冊あるものの、20世紀既刊の3冊『九百人のお祖母さん』『どろぼう熊の惑星』『つぎの岩につづく』は新刊での入手がもはやできない。カルト的な人気はあっても、残念ながらラファティは万人の受け入れる作家ではないのだ。しかし、本書ではそういうラファティの魅力を、円やかにではなく、逆に先鋭化して再提示してみせる。
町かどの穴(1967/72)仕事から帰ってくると、家族はなぜか自分を怪物呼ばわりして叫び出す、ゼッキョー、ゼッキョー。
どろぼう熊の惑星(1982/93)その惑星ではあらゆるものが盗まれる。食料や資材だけでなく、人の記憶や知性までもが。
山上の蛙(1970/72)銀河系で最も危険な狩りに挑む男の前に、猫ライオン、熊、コンドル鷲、そして岩猿またの名(翻訳しだいでは)蛙男が立ち塞がる。
秘密の鰐について(1970/87)世界にはたくさんの秘密結社があり、裏から社会の各分野を支配している。その中でも〈鰐〉こそが最上位に君臨する結社だった。
クロコダイルとアリゲーターよ、クレム(1967/88)優秀なセールスマンだった主人公は、ある日猛烈な空腹感と違和感に襲われる。その原因は自分自身にあった。
世界の蝶番はうめく(1971/92)世界をぐるりとひっくり返し、裏の世界と入れ替えてしまう蝶番がある。ひとたび反転が起こると、住んでいた人々は別のものに変わってしまう。
今年の新人(1981/81)* 能力増強剤が普及してから毎年飛び抜けた新人が生まれてくる。でも今年の新人はどこかダサかった。
いなかった男(1967/80)* 嘘つきと評判の家畜商の男がとっておきの話を始める。存在感の薄かった男を消してみせるというのだが。
テキサス州ソドムとゴモラ(1962/77)国勢調査員の男は人がほとんど住まない地域を担当するが、そこで数万の小さな人々を見つけ調査用紙に記入しようとする。
夢(1962/74)その娘は、緑色の雨が降りしきる夢の世界の話をする。話を聞きつけた男は、夢の内容を執拗に聞き出そうとする。
苺ヶ丘(1976/2015)* 外部と没交渉のまま孤立する丘の上の家に、二人の少年が肝試しに潜り込もうとする。
カブリート(1976/2014)* 小さな居酒屋に集う7人の男たちと、カブリート(仔山羊肉のロースト)を売る女主人が話すおかしな話。(1957年に書かれ保留されていた初期作)。
その町の名は?(1964/79)辞書の単語と単語のすき間、人々の記憶のすき間に、この世から失われたある町の名前が潜んでいる。《不純粋科学研究所》の1編。
われらかくシャルルマーニュを悩ませり(1967/79)過去改変を試みる大実験の成果は、しかし実証が困難なものばかり。《不純粋科学研究所》 の1編。
他人の目(1960/79)今度の大発明は大脳走査機である。他人の脳と自分の脳を同期させることができるのだ。《不純粋科学研究所》 の1編。
その曲しか吹けない(1980/2014)* 友人たちとを比べると、主人公の能力は劣っていたのだが巧妙さでは勝っていた。その性質が、やがて恐ろしい運命を呼ぶ。
完全無欠な貴橄欖石(1970/72)リビア海岸を「北」に見ながら太洋を進む帆船は、澄み切った海水の中に得体の知れないジャングルの存在を感じ取る。
〈偉大な日〉明ける(1975/2017)* 偉大な日がやってくる、それも今日にだ。時計からは分針が取り除かれ、飲み物のコップすらなくてもよくなる。
つぎの岩につづく(1970/72)石灰岩の台地を発掘する考古学チームは、燧石に彫られたラブレターらしきものを発見するのだが。
(原著発表年/初翻訳)*…短編集初収録(雑誌、アンソロジイ収録作)
基本的には入手困難な3短編集からの13作品と、これまで短編集には収録されていなかったレアな6編からなるオリジナル作品集である。
あらためてラファティの作品を19編立て続けに読んでみると、その抽象度の高さに驚かされる。「町かどの穴」からは、自分が非人間だとは思っていない怪物が現われ、むさぼり食われる妻はセリフを棒読みするように無感動に叫ぶのみ。「完全無欠の貴橄欖石」では、非実在の海を帆走する船が実在の(ような)アフリカに浸食される。「つぎの岩につづく」はアメリカの地層を掘っていくと、ありえないものが次々現われる。描き出されるのは、リアルからはるかに遠い奇想の世界である。
非倫理的で(人肉嗜食や)始原の野蛮さが顔をのぞかせる点は、ボルヘスのような観念的・哲学的なものとは印象が異なる。だが、エンタメ小説の過剰なサービスやスプラッターを目指しているわけではない。どれも淡々というか、飄々としている。ユニークさを重視する編集者、デーモン・ナイトやフレデリック・ポールらが好んだのも頷ける内容だ。ただし、本書を読むのなら一日1作程度が望ましいだろう。一度に読むと目まいを起こしてしまう。想像力が物語に追い越されてしまうのだ。