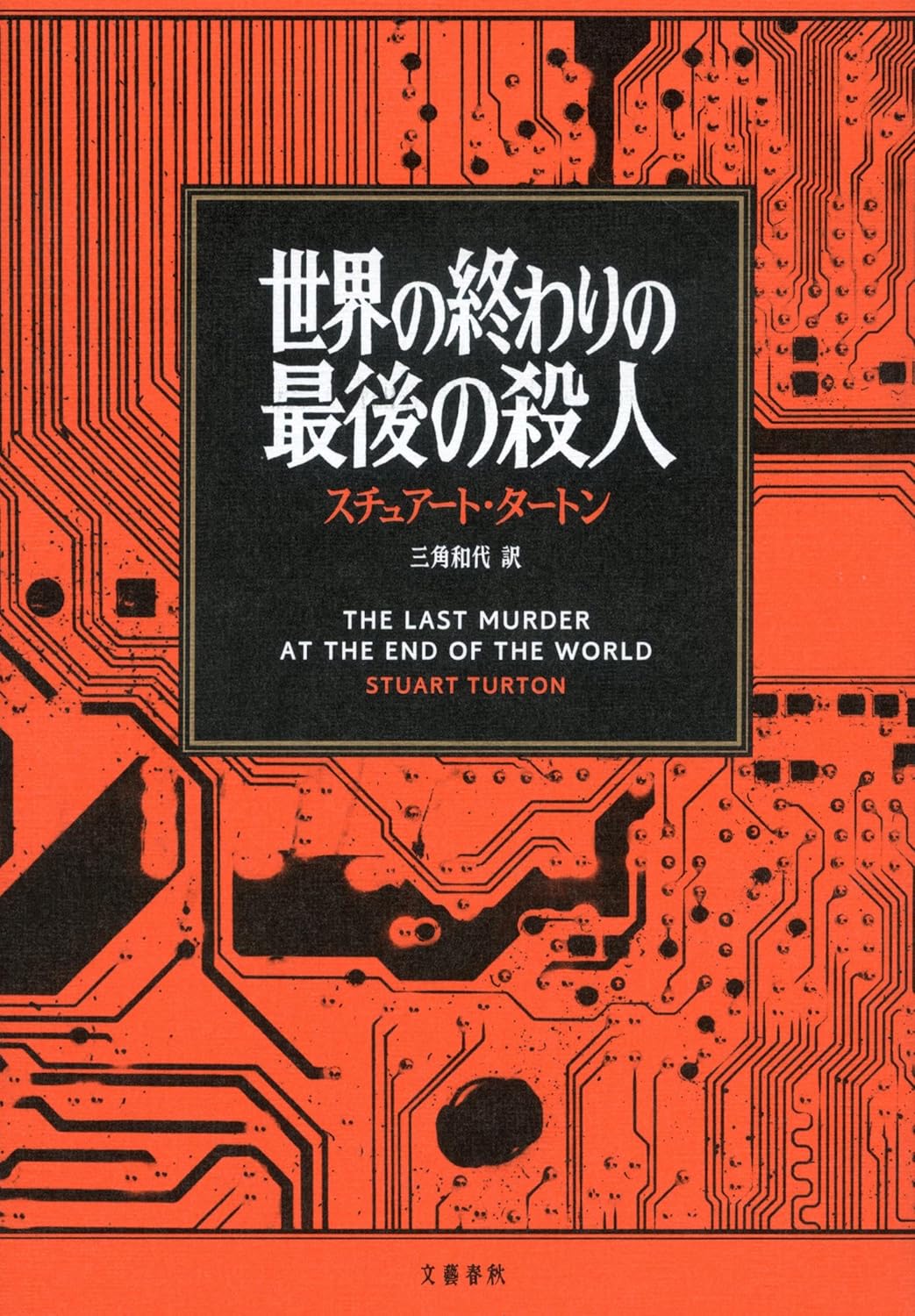装画:カワグチタクヤ
装幀:島田小夜子(KOGUMA OFFICE)
日本在住の日本人でありながら英語で作品発表を行い、年刊傑作選に収録されるなど高い評価を受けているオガワユキミの日本オリジナル短編集(類例がないわけではないが)。本書の11編はすべて英文だが(本人ではなく翻訳者により)和訳されたものである。
町外れ(2013)結婚相談所にやってきた古風な女は、マスクで耳元までを覆い「雄が必要なのだ」と繰り返した。仕方なく相手を探す相談に乗るのだが。
煙のように光のように(2018)決められた段取りに従って大きな納屋の空間に入り、大旦那のところに行くと、そこで召喚された若い幽霊、母親と男の子の姿を見る。
お化け屋敷へ、ようこそ(2019)お化け屋敷にはさまざまな妖怪がいる。人形や傘、リュート、何枚かの皿などのモノが化けている。ただ、記憶は朝にはリセットされる。
つらら(2013)つららは半分人間で半分雪女だった。心臓が氷柱でできていた。ひとりで海を見に行く決心をし家を出ることにした。
童の本懐(2018)家に取り憑いた妖怪は、そこに住む女と祖母、娘のために力を盗み出す。しかし、自分から力を盗んだことで何もかもが緩慢に悪くなる。
NINI(2017)宇宙ステーションに設けられた高齢者施設では、やさしい外観をしたニニが医療AIとの仲立ちをしている。餅を分解して非常食とする機能さえ持っていた。
手のひらの上、グランマの庭(2021)父親が進学資金を使い込んだため、わたしは異形の生き物グランマの、ワームホールの先にある家で働くことになった。
パーフェクト(2014)変色したマグノリアのドレスを着たわたしは、出会う人々から完璧なもの、頬や手や目玉、肉体を次々と手に入れていく。
千変万化(2016)島の呉服店で働く主人公は、爪先の色を自在に変化させる有名なモデルと知り合いになる。ところが、偶然ポリッシュを手に入れたことで。
巨人の樹(2014)夢の中で共に過ごした巨人との暮らしは、ふるさとの校庭にあるケヤキの巨木とつながっている。
アウェイ(書下ろし)「ナミ様」はさまざまなものになって生き返ってくる。今度は空だった。そして甦るたびに、元の世界から何かを連れ帰ってくるのだ。
日本の妖怪もの(たとえば《しゃばけ》とか)のユーモラスな雰囲気を感じさせる。だが、結末は少しダークになる。舞台も日本とはいえないどこか(日本的な幽霊とトウモロコシ畑が共存する)、無国籍の設定となっている。発表誌の多くはホラー/ファンタジー系が多い。
物語では、現実に近い世界と夢の世界/異世界とがシームレスに置かれている。「アウェイ」では、何にでも姿を変えるナミ様が存在する世界(ファンタジイ)に、元の生々しい世界(リアル)が垣間見える(現実の方がアウェイなのだ)。異世界もまた単純ではない。「煙のように光のように」では大旦那様の納屋の中に、さらに霊界を呼び出す2段階目の異世界が現出する。こういう、一筋縄でいかない構造の精妙さがユキミ・オガワの面白さなのだろう。
- 『白猫、黒犬』評者のレビュー