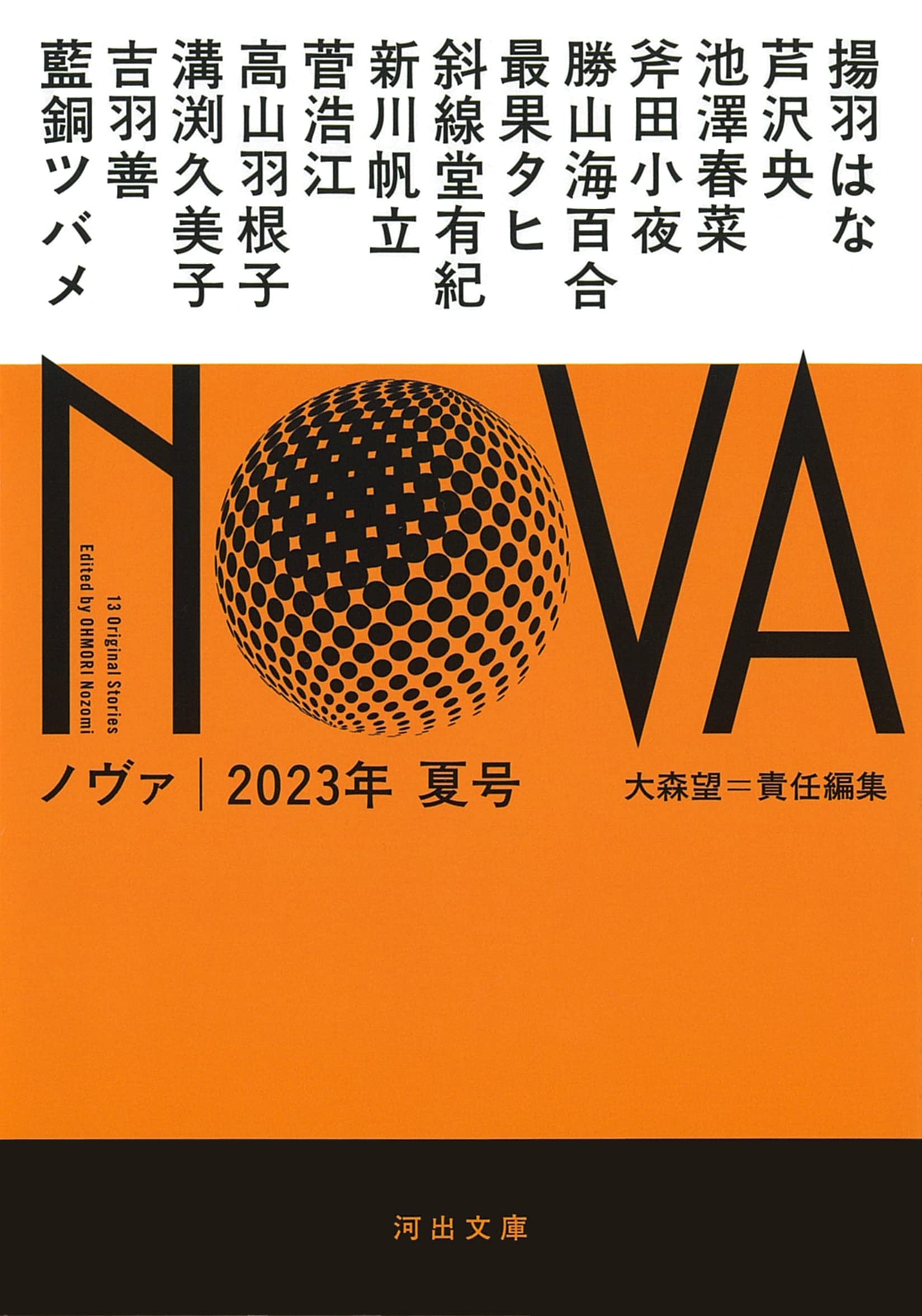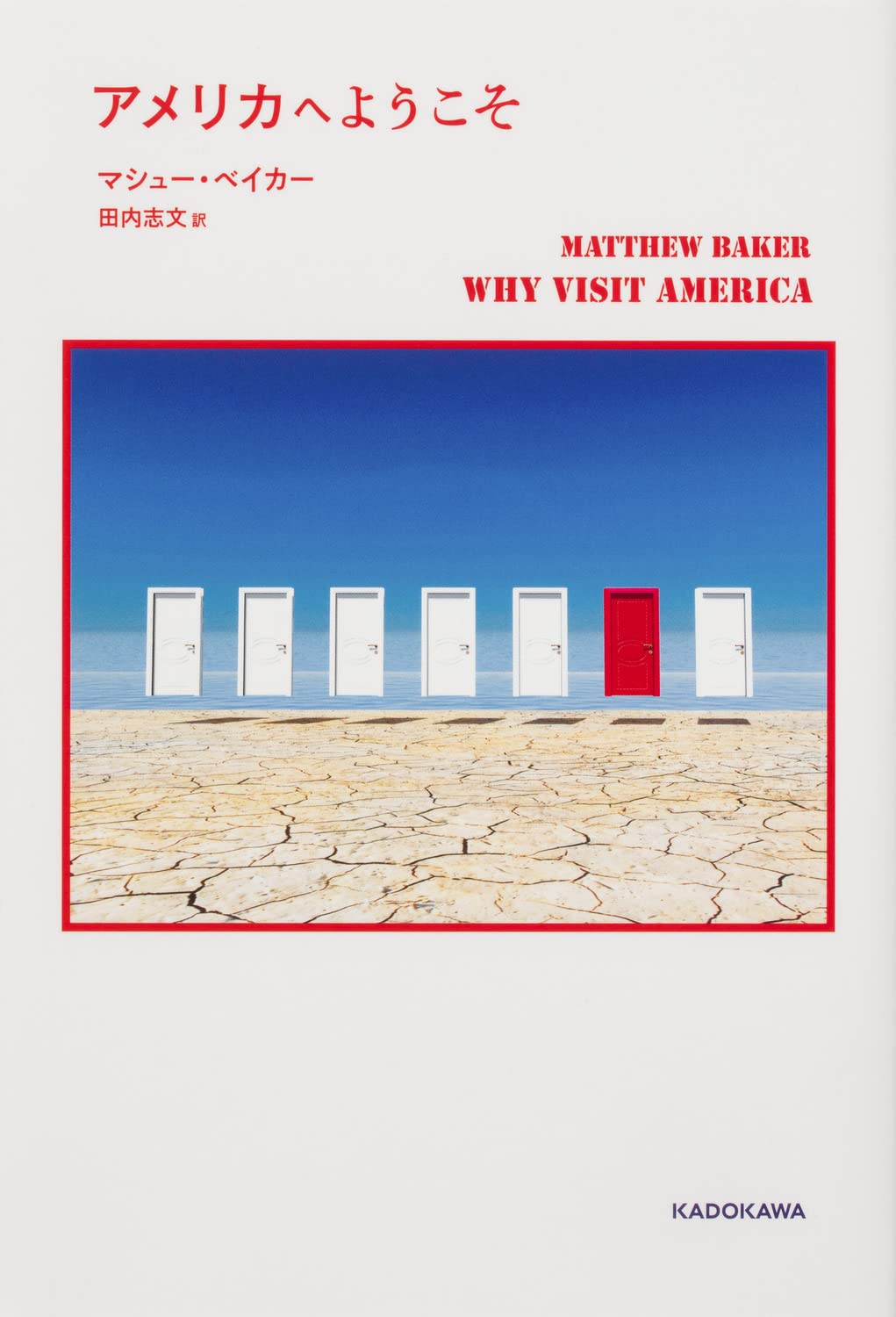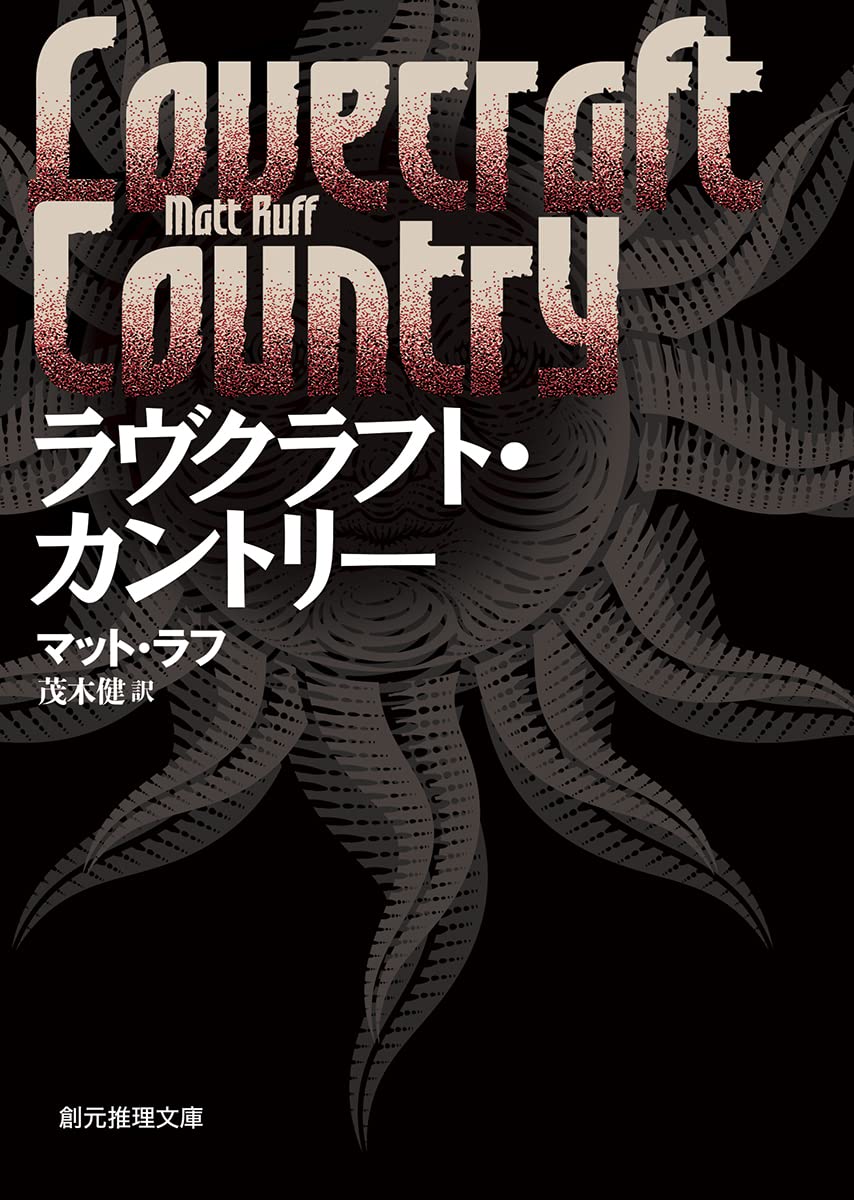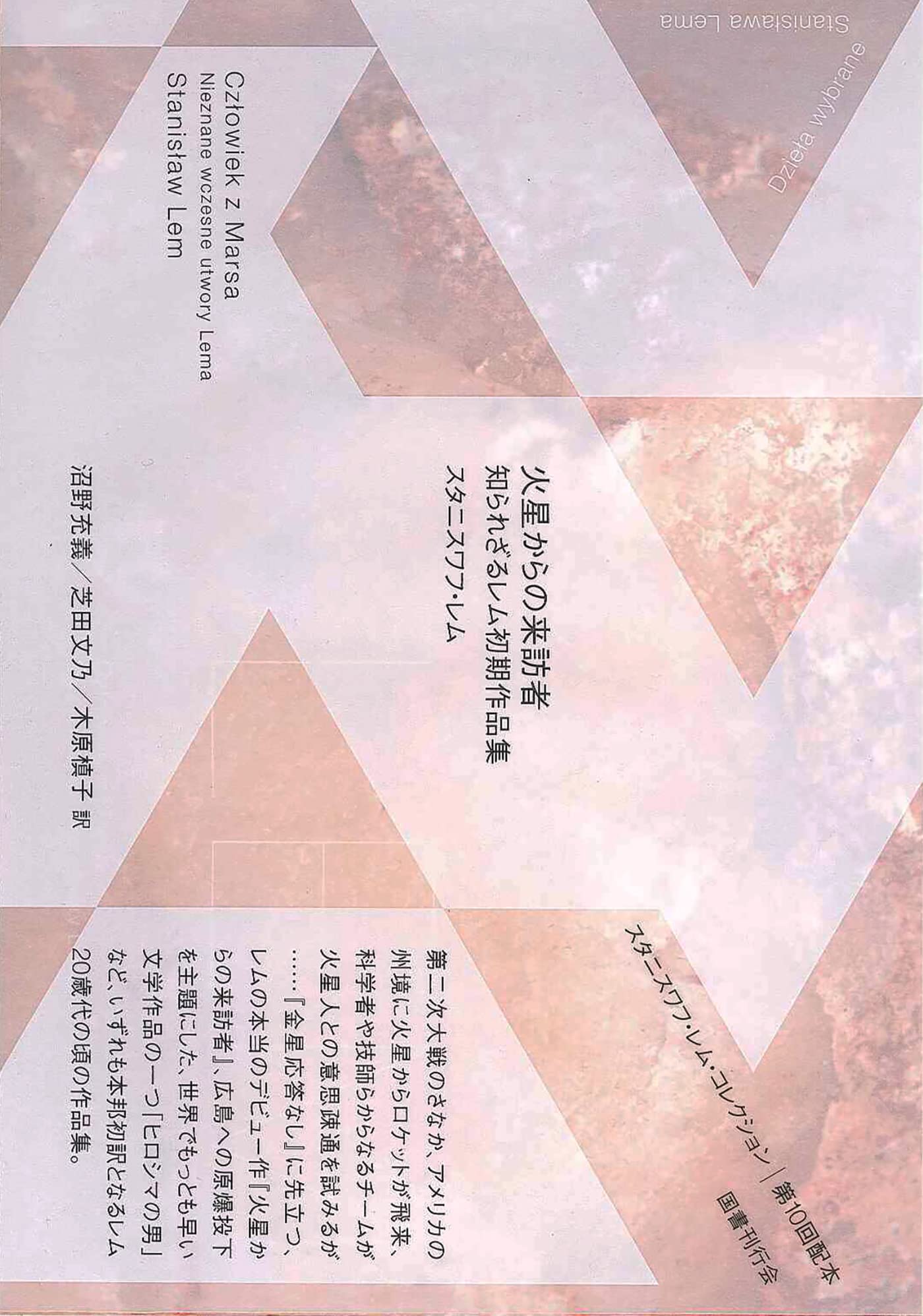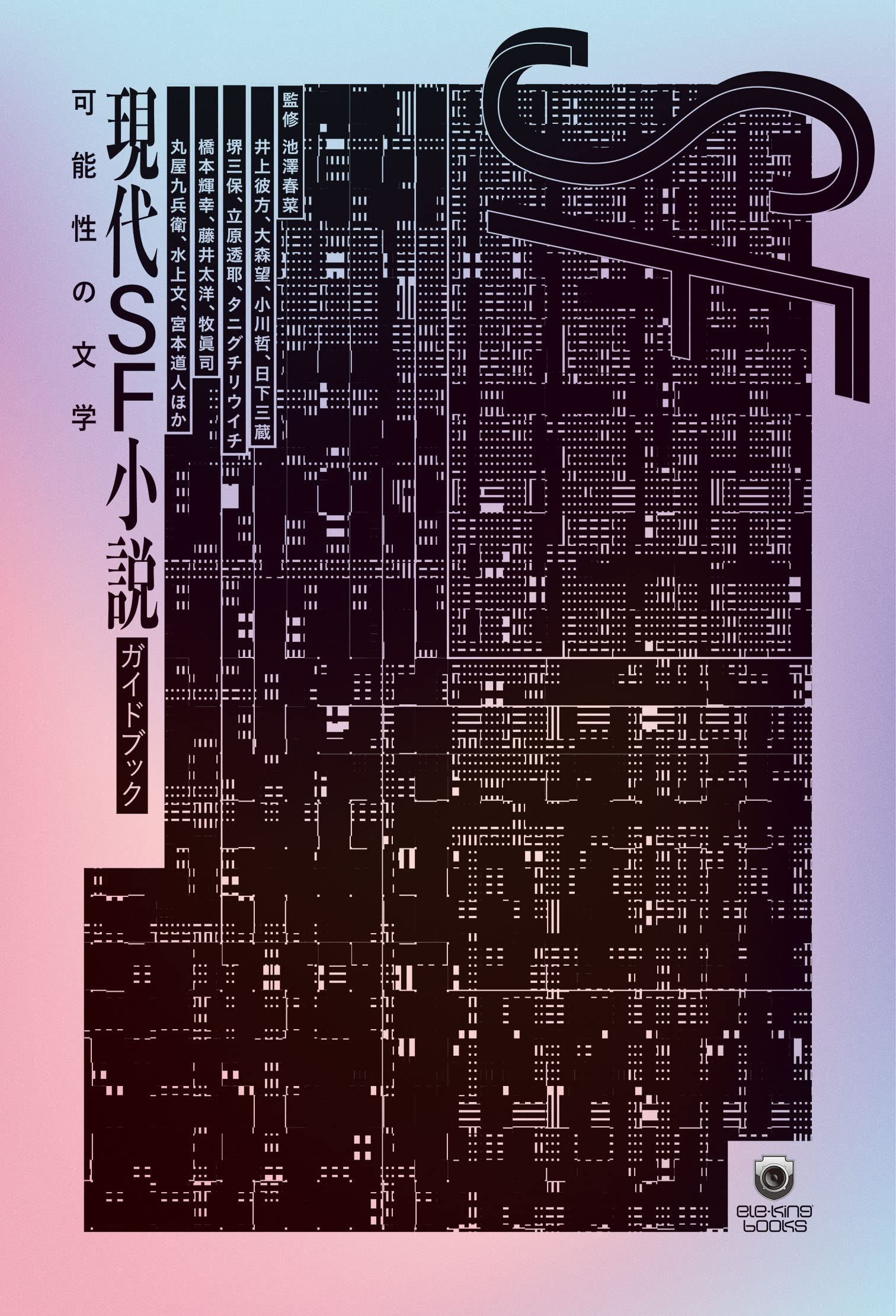2003年の第5回日本SF新人賞受賞でデビューし、2021年12月に亡くなった八杉将司の短編集。著者には多数の作品がありながら、生前に短編集が出ることはなかった。本書は、関係する作家有志により編纂された傑作選である。同じ出版社から出ている遺作長編『LOG-WORLD』はオンデマンド出版(もともとはpixiv公開)だったが、こちらはAmazonなど数社からの電子書籍のみとなる。
短編[ その一 ]
命、短し(2004)バイオハザードにより人類の寿命は極端に縮んでしまう。少年も既に人生の半分を生きた。海はあなたと(2004)生体CPUとなった主人公は海辺を車で走るのだが、外の光景はいつまでも変わらない。ハルシネーション(2006)脳の機能障害により「動き」が認識できなくなる。しかも、やがてありえないものが見えるようになった。うつろなテレポーター(2007)量子コンピュータのシミュレーションで造られた複数あるコロニーのうち、自分たちのコロニーが複製されるらしい。これは実利も伴う名誉だった。カミが眠る島(2008)瀬戸内海の小島で行われる祭りを取材するためライターが訪れる。そこでは利権をめぐる騒動が巻き起こっていた。エモーション・パーツ(2009)会社で仕事中、急に笑いが止まらなくなる。どうやら人工大脳の故障らしい。一千億次元の眠り(2011)矯正措置を受けた火星の旧支配層のうち、有力な一人が逃走する。知人だった元警官は、捜査官として行方を追うよう指示される。
『異形コレクション』掲載作
娘の望み(2006)娘は言葉が話せなかった。脳に障害があったからだ。しかしそれに代わる芸術の素養があるようだった。俺たちの冥福(2007)中古部品のブローカーで働く主人公は、点や影が顔に見える幻覚に苦しんでいた。産森(2008)宇宙での仕事にうんざりし、祖父母が住んでいた田舎の家に住むことにした。すると夜中に扉が叩かれ、赤ん坊が泣き叫ぶ声がする。夏がきた(2007)長い長い冬が終わり、降り積もった雪は溶けてしまう。やがて何年も続く夏がきた。ぼくの時間、きみの時間(2011)自分を基準に測るしかないが、主観時間は人によって違う。しかし妻とは大きな違いがあった。
短編[ その二 ]
宇宙の終わりの嘘つき少年(2012)そこは運河の世界で、人々は船を筏のように連ねて生活している。運河はどこまでも続いているが、一生の間に何回か同じところを通るらしい。それを昔の人は魂と呼んでいた(2013)魂だけが消えてしまう疾病が蔓延する。発症すると、過去の一定期間行っていた行為を延々と繰り返すのだ。
ショートショート集
ブライアン(2011)移民宇宙船が遭難、未開惑星へと脱出できたのは自分一人のようだった。そこで笑い顔の石ころを見つける。神が死んだ日(2012)授業中にアラームが鳴る、それは教師である自分宛に緊急事態を伝えるものだった。宇宙ステーションの幽霊(2013)幽霊を信じていなかった科学者の自分が、なんと幽霊になっている。むき出しの宇宙が見える以上、そう考えるほかなかった。ドンの遺産(2014)堅気で生活していた男は、マフィアだった父の跡を継げと申し渡される。座敷童子(2014)跡取りで揉める田舎の家で、中学生の主人公は見知らぬ女の子に声を掛けられる。追想(2015)人類は滅亡寸前、アンドロイドは酒を求めるばかりの困った老人を介護している。夢見るチンピラと星くずバター(2018)月で採れた石には未知のミネラルが含まれているようだ。それを混ぜたバターを食べると何かが。砲兵と子供たち(2020)第1次大戦下の西部戦線、ドイツ軍の砲兵は自軍の周辺に子供たちが群れていることに気が付く。LIVE(2021)人工知能に自我あると認められた。それは問いかけに対し「LIVE」と答えたからである。我が家の味(2021)妻に先立たれ夫は途方に暮れるが、料理の味を決める見知らぬ素材があることを知る。
短編[ その三 ]
私から見た世界(2013)見えていたものが見えなくなる。その異常は脳の手術で治るはずだった。だが、術後に別の症状が表われ次第に悪化していく。親しい人が見えず、声が聞けなくなるのだ。妻や子供を自身の認知から失い、周囲の知人も消えていく。
八杉将司作品論・三編
八杉将司作品論(町井登志夫)/いつか、白玉楼の中で――八杉将司さんの創作についての覚え書き(片理誠)/八杉将司短編群を読み解く――〈私から見た世界〉と〈世界から見た私〉(上田早夕里)
上田早夕里の作品論で詳しく述べられているが、著者は認知の問題を繰り返しテーマとしてきた。表題作「ハルシネーション」と、巻末に置かれた「私から見た世界」は、共に主人公の認知が極端に変貌していく様子を描いた対を成す作品といえる。片理誠は「ハルシネーション」をホラーだと思ったと書いている。恐怖も人の認知が生み出す感覚で、スピリチュアルなものと親和性が高いからだろう。ただ、著者は脳神経科学などの知見を取り入れることで、イーガンらが好むSF的/科学的な解釈を試みてきた。「私から見た世界」はその両者を融合したような作品だ。
他でも「海はあなたと」「エモーション・パーツ」「一千億次元の眠り」「娘の望み」「ぼくの時間、きみの時間」「それを昔の人は魂と呼んでいた」など自我と意識を主要なモチーフとしたものが多くを占める。純粋なソフトウェア知性の「うつろなテレポーター」や、機械と認知の問題に言及した「LIVE」のような作品もある。いまハルシネーションというと、AIの吐く噓(でたらめな答え)のことを指すが、八杉将司ならどう解釈するのか訊いてみたい気がする。
- 『Delivery』評者のレビュー