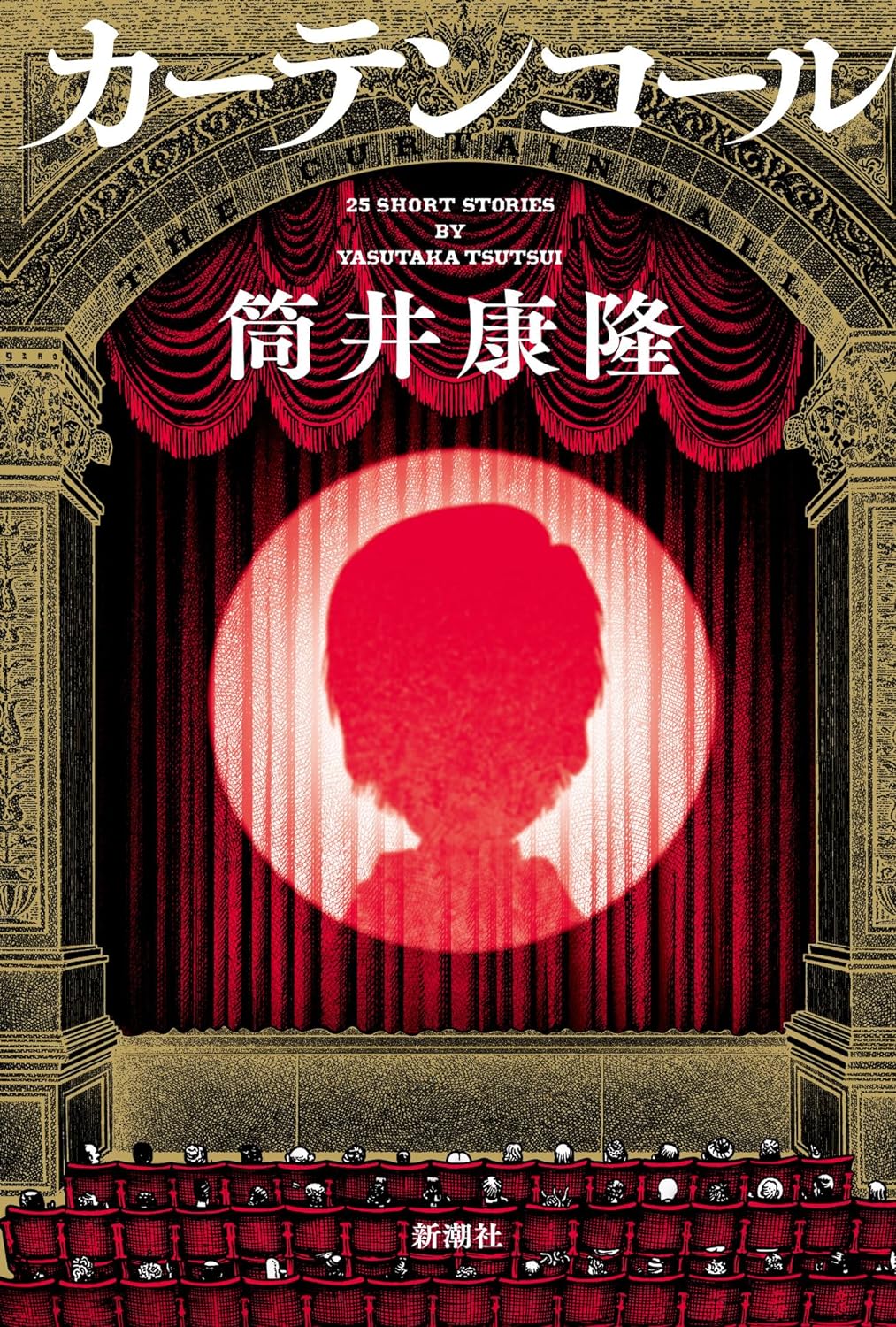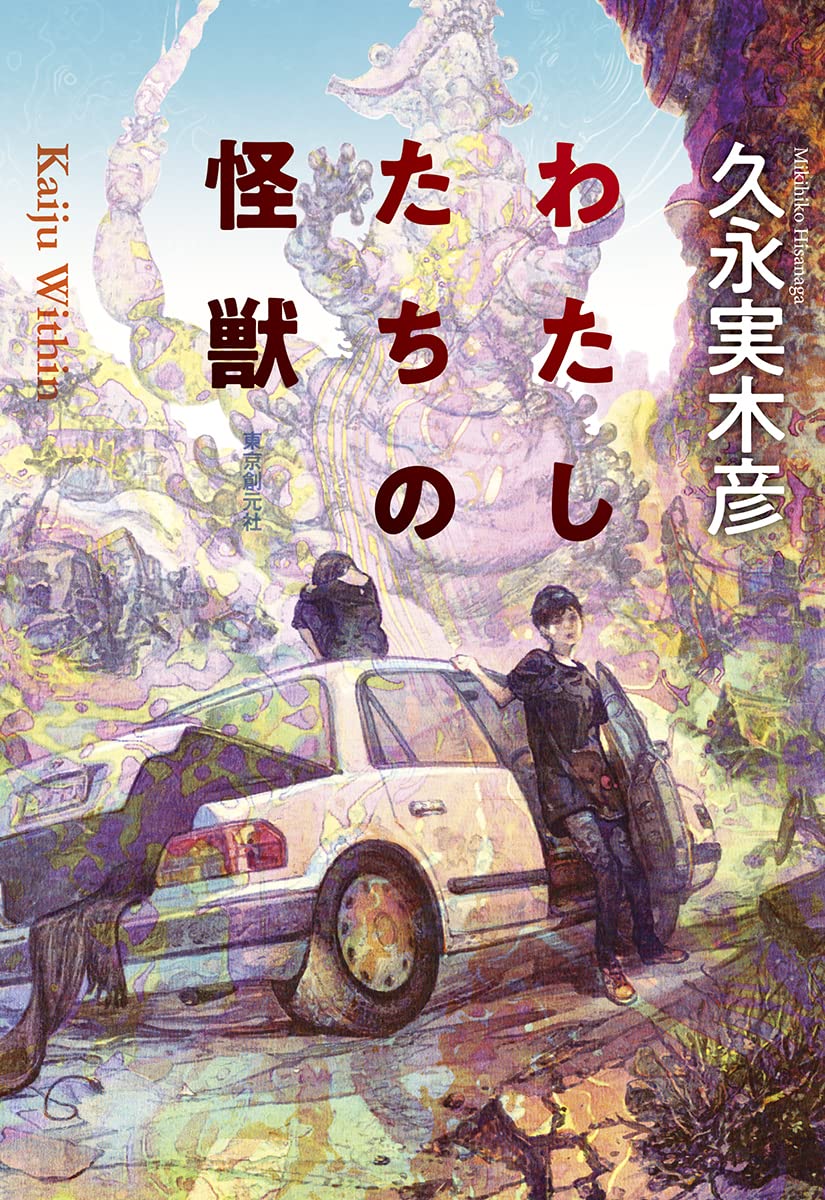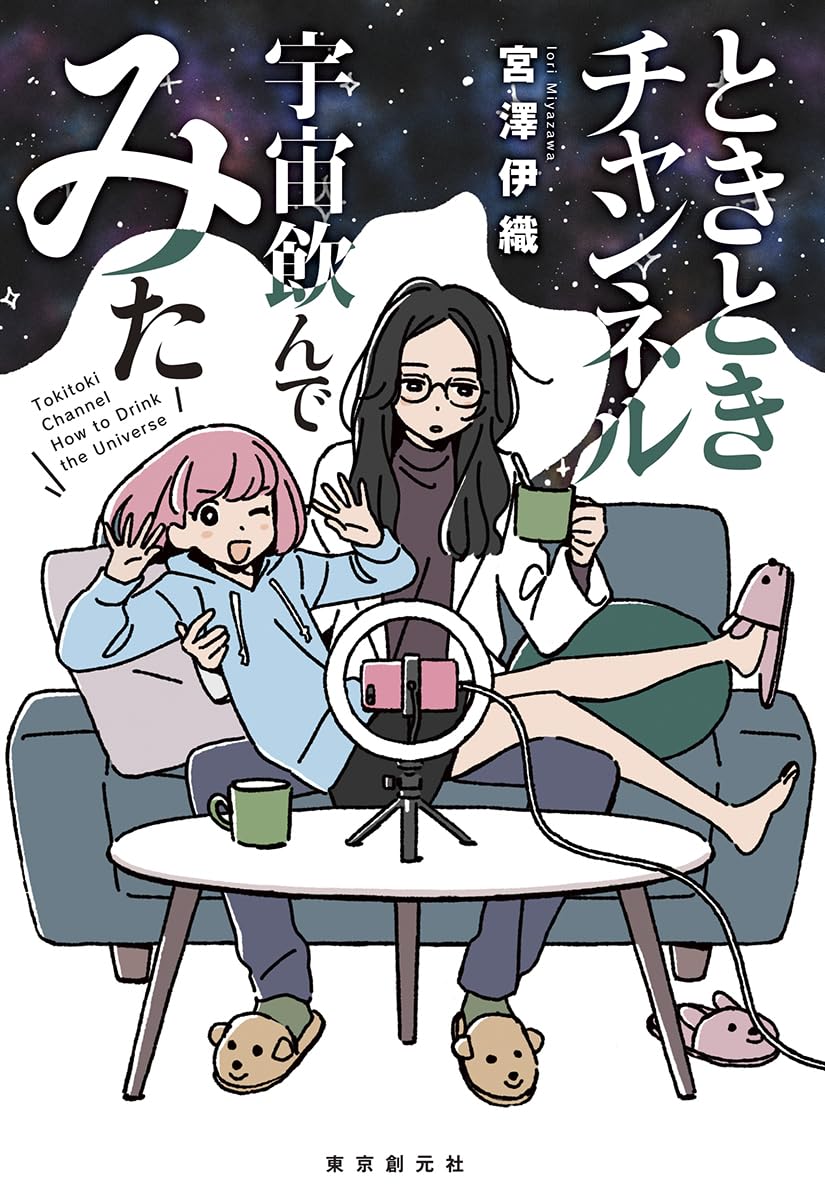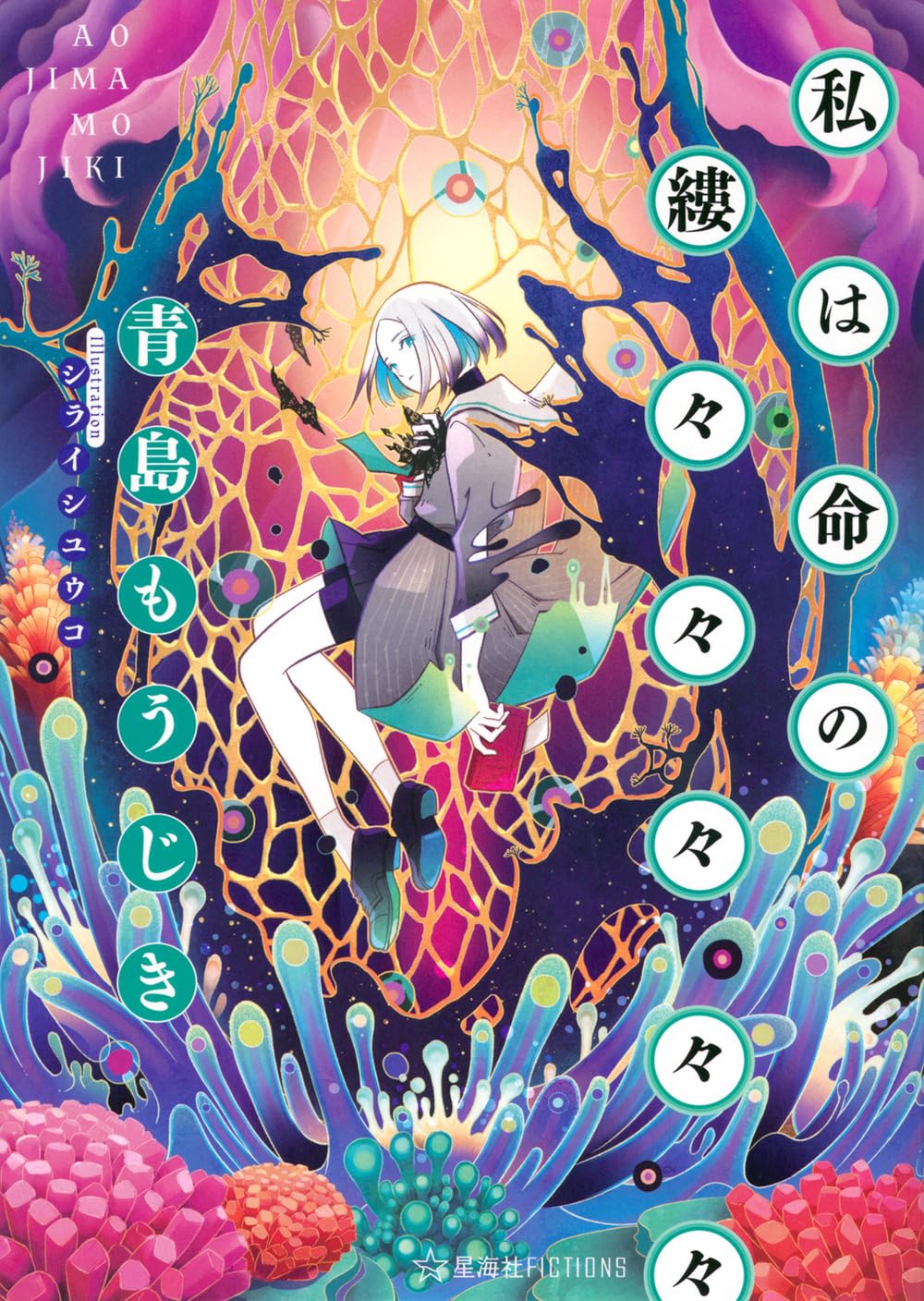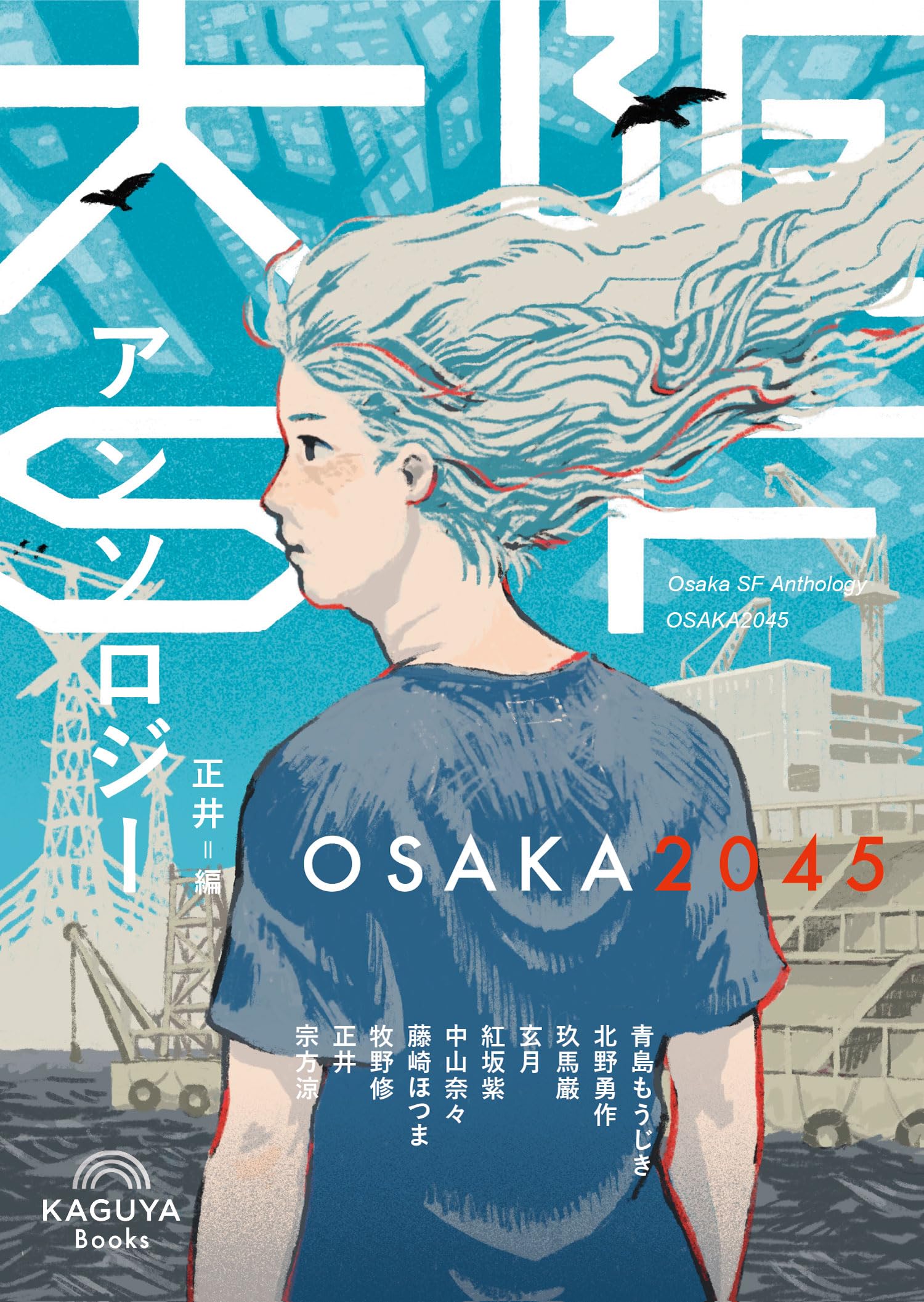『万象』(2018)、『万象ふたたび』(2021)に続く、日本ファンタジーノベル大賞受賞者によるオリジナル・アンソロジー第3弾。どの巻も1000枚前後のボリュームを誇る。今回は1200枚弱と、歴代最高を謳う。まとめ人(編者)あとがきを読むと「猫」「記憶」「怪獣」「3」「登下校」「世界」「字数」など、緩やかな縛りをお題・テーマとしているようだ。また、作品の題字と著者名は、各著者による自筆または自作(グラフィック)になっている。
小田雅久仁「旅路」目が覚めると豪華なホテルの部屋で、見知らぬ女が横に寝ている。そして手首にはボタンが付いた黒い機械が巻き付いていた。
粕谷知世「いき・かえり」田舎に住む小学1年生の女の子は、毎日集団登下校で農道を往復する。その途中で、いじめっ子が嫌がらせをするのだが。
西崎憲「影機」死のうとした私を救ったのは、詩人でもあるロボットの成功者だった。人と同じ権利を持っているのだ。
日野俊太郎「鬼街」いくさが続くと決まって鬼街が現れる。鬼の遊女がいて、戦いに疲れた男たちをもてなすのだ。そこに醜い男と身なりのいい若者がやってくる。
南條竹則「温泉叙景」宿が一つしかない秘湯、微温湯温泉を知ったのは大学院生の頃だった。そこには二匹の猫がいて、懐いた一匹にマタタビを与えたことがある。
冴崎伸「空想の現実~ミャンマーの沼/ぼくと博士の楽しい日常〔裏の目薬〕の巻」ミャンマーでのリアルな求人の旅/怪しい館に住む美麗な科学者による驚異の発明品。
北野勇作「『クラゲ怪獣クゲラ対未亡人セクシーくノ一 昼下がりの密室』未使用テイク集」 奥様はくノ一、テトラポットではなくテトラポッド、クラゲならぬ怪獣クゲラ。
石野晶「死人花」死者が埋葬された後、死人花がひそかに咲く。それには死者の幸福な記憶が凝集されているのだ。
大塚已愛「せみごゑ」浜辺で倒れていた男は、自分の名前だけしか思い出せない。しかも、出会った少女は謎めいた言葉を告げて立ち去ってしまう。
久保寺健彦「立ち入り禁止」登校班の同じ小学生たちは、よく刑事と泥棒ゲームで遊んだ。ただ、年長の女の子だけはいつも捕まらない。
森青花「ちゃとらのチャトラン」「ねこのいい」チャトランはいつもぽーっとしている。近所にいるいろいろな猫たちといつも仲良くしたいと思っている。
斉藤直子「大地は沸かした牛乳に」リモートワークが続く日常で、ネットを監視する主人公は先輩社員と掛け合いをしながらトラブルと対峙する。
三國青葉「ばっくれ大悟婆難剣 冬虹」代筆屋でかろうじて生活する浪人の主人公は、雪の降る日に仇討ちを企てる少年を止める。家族にまつわる理由があるようだった。
柿村将彦「反省文」読もうともしない教師宛の反省文で、登校時に遭遇した波乱万丈の事件を字数制限に合わせて綴る。
藤田雅矢「ブランコ」公園で猫に餌をやった帰り、くねくねした路地の奥で郵便ボックスを改造した植木置きを見つける。そこに並ぶ鉢には何か意味があるようだった。
堀川アサコ「3つの生け簀」古いアパートに越してきた主人公は、そこが「生け簀」であるという匿名の警告文を受け取る。どういう意味なのだろう。
勝山海百合「紫には灰を」地球外の荷物が届いたと知らせが入る。それは異星に赴任した小学校の同級生からの紫草なのだった。
関俊介「サナギ世界」主人公は幼体でまだ成体のように飛べなかった。それでも数えきれない仲間とともに跳躍しながら群れを追うのだ。彼らは黒いバッタだった。
登下校ものでは「いき・かえり」「ぼくと博士の楽しい日常〔裏の目薬〕の巻」「立ち入り禁止」「反省文」「紫には灰を」などがある。記憶の「旅路」「死人花」「せみごゑ」、猫だと「温泉叙景」「ちゃとらのチャトラン」「ブランコ」、世界となると「旅路」「大地は沸かした牛乳に」(ネット世界)「サナギ世界」などか。怪獣(的なものを含め)は「鬼街」「『クラゲ怪獣クゲラ対未亡人セクシーくノ一 昼下がりの密室』未使用テイク集」。3は「3つの生贄」「ばっくれ大悟婆難剣 冬虹」(霜月三日の事件)だが、「サナギ世界」(主人公は第三齢)や、猫と字数を含む「反省文」のようにお題を複合的に組み合わせたものもある。同じお題の場合、よく似たテイストになっている。
悪い意味ではないが、プロ作家の集まりであるのに同人誌的な雰囲気を感じる。同じ賞の出身者であるという仲間意識と、同じ自由な幻視者である(対象となるファンタジイの範囲が広い)という誇りがそう見せるのかもしれない。
関俊介「サナギ世界」は短い長編(350枚、ノヴェラ相当)クラスの作品で、第24回優秀賞だった『絶対服従者 ワーカー』を思わせる。同作は昆虫(アリやハチ)たちが擬人化された物語だった。今回その昆虫は、未来の人類が昆虫に似せて派生・変態した姿なのだと説明される(なので、擬人化は間違ってはいない)。彼らは大群を作って飛蝗となるバッタの性質を残している。ただ、バッタはサナギにはならない(不完全変態)。なぜこの世界がサナギと呼ばれるのかが物語の主題となる。
- 『万象』評者のレビュー