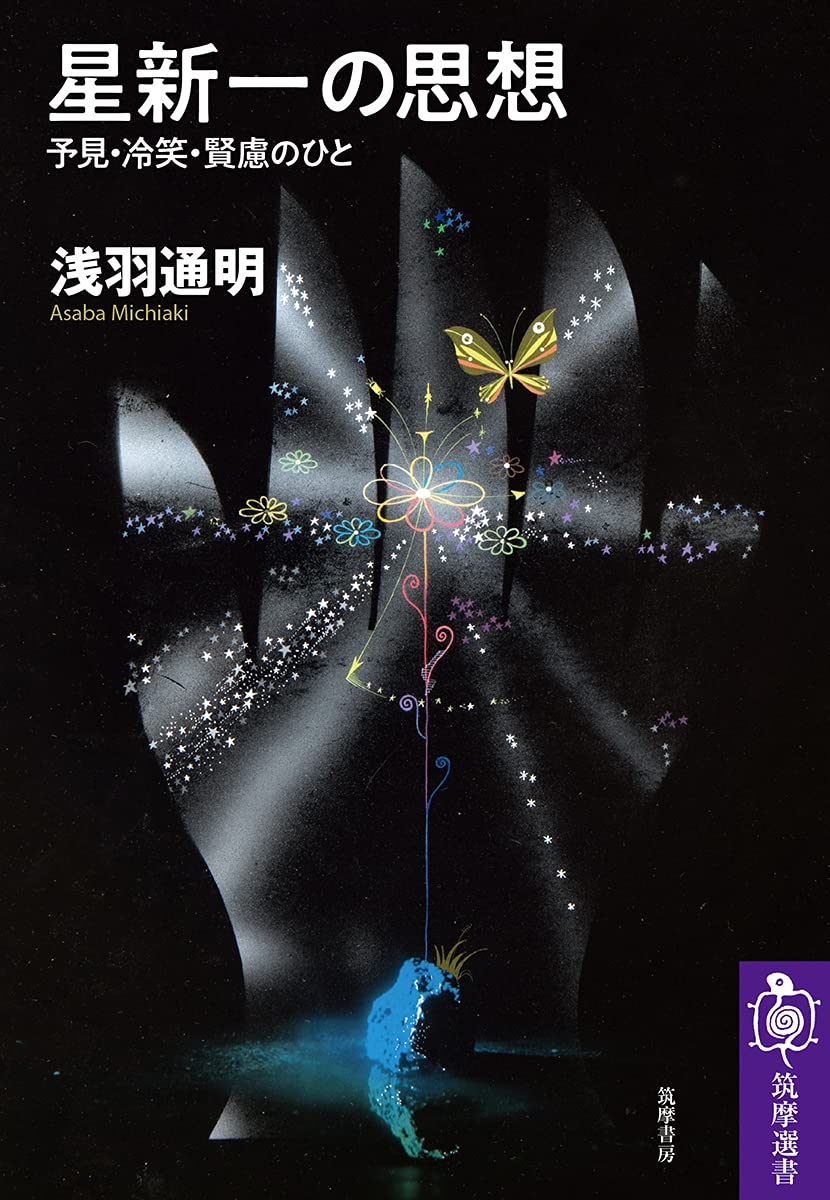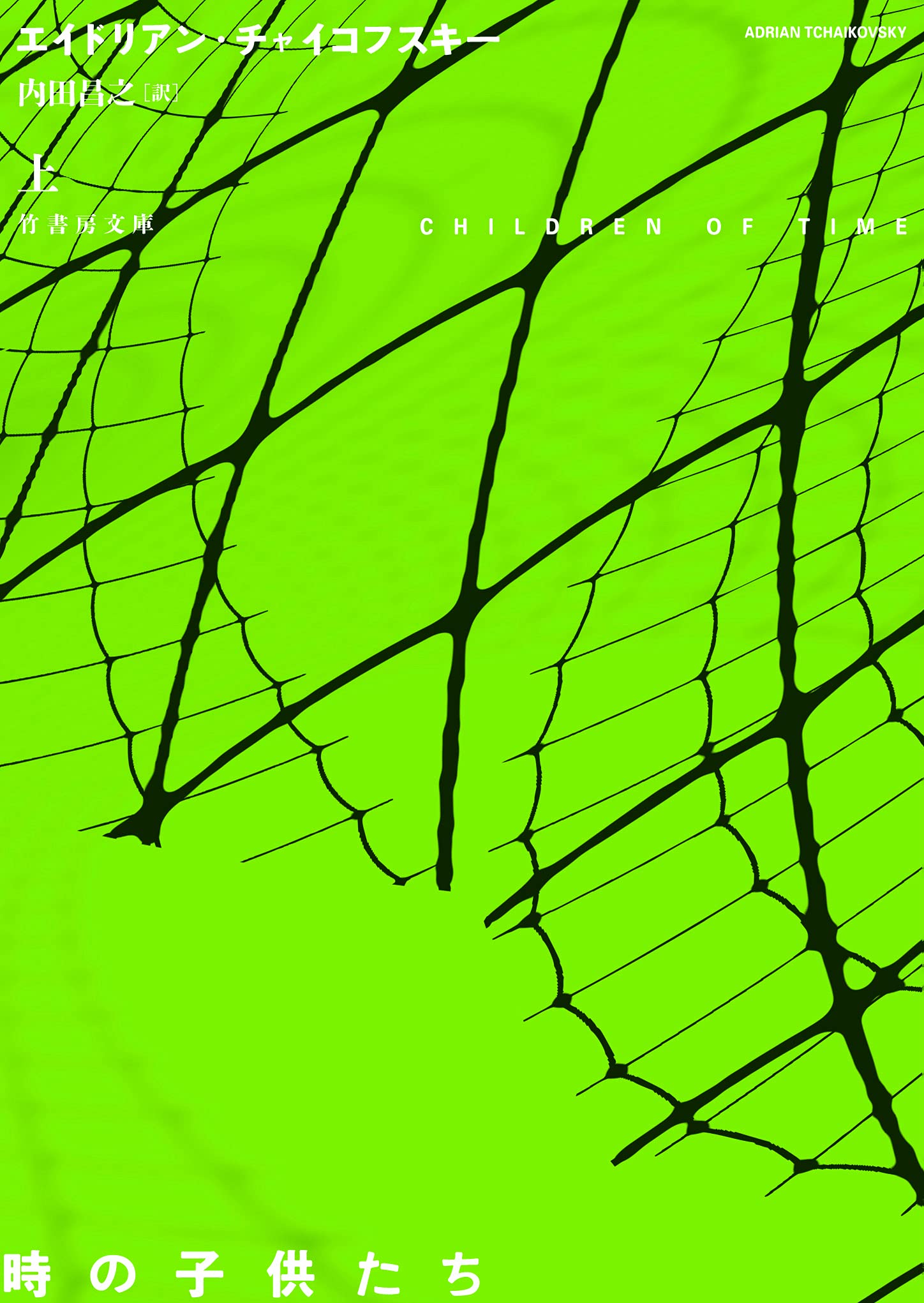装幀:小柳萌加(next door design)
《Genesis 創元日本SFアンソロジー》は1年2ヶ月ぶりの出版、これで第4集目となる。前号と同様、創元SF短編賞(第12回)の受賞作が掲載されている。
小川一水「未明のシンビオシス」中央構造線一帯で発生した「大分割」により、日本の東海地方より西は壊滅する。主人公は、たまたま出会った技師と共に北をめざす旅に出るが、その目的は判然としない。
川野芽生「いつか明ける夜を」太陽のない世界、野に放たれた馬が連れ帰ったのは、言い伝え通りの救世主とは思えない一人の少女だった。
宮内悠介「1ヘクタールのフェイク・ファー」高円寺にいたはずの主人公は、気がつくと地球の裏側のブエノスアイレスにいる。テレポーテーションしたのか。しかし言葉も通じず、金もない。
宮澤伊織「時間飼ってみた」同居人の天才科学者が、何やら得体の知れない生き物らしきものを飼っている。それは「時間」なのだというが。
小田雅久仁「ラムディアンズ・キューブ」世界中で不特定の都市が、内部から不可視の巨大キューブに飲み込まれる。閉じ込められた人々は、方舟から放たれた巨人や出現する異形の兵士によって次々と殺される。
高山羽根子「ほんとうの旅」ガラガラの列車の旅と思っていた路線は意外な混みようだった。主人公は閉口するが、見知らぬ同乗者から意外な話を聞く。
鈴木力「SFの新時代へ」創元SF短編賞のこれまでの沿革と、歴代受賞作、賞の意義についての解説記事。
溝渕久美子「神の豚」創元SF短編賞優秀賞。疫病の蔓延を阻止するために、家畜が消えてしまった近未来の台湾。主人公は田舎の兄から、長兄が豚になったと連絡を受ける。
松樹凛「射手座の香る夏」同受賞作。意識転送技術によりオルタナと呼ばれるロボットに憑依することで、自在な遠隔作業が出来るようになった未来。マグマ発電施設で働く憑依中の作業員が、休眠する肉体を奪われる事件が発生する。
今回も創元SF短編賞絡みの執筆者が多い。サバイバル小説かと思わせて一段シフトする「未明のシンビオシス」、『指輪物語』と「夢十夜」を組み合わせたという「いつか明ける夜を」、おかしな不条理を段落なしに描く「1ヘクタールのフェイク・ファー」、シリーズ2作目となる軽快な作品「時間飼ってみた」、「ほんとうの旅」はフィクションと現実の狭間を旅するお話だ。異色なのは「ラムディアンズ・キューブ」で、小田雅久仁は『万象』に中編を発表して以来の作品となる。一見SFに見えるものの中味は「霊界小説」(のようなもの)。18億年に及ぶ真世界・疑似世界が描かれているのである。
優秀賞 溝渕久美子「神の豚」は、大きな社会的事件をあえて物語の背景に遠ざけ、兄弟(仲の良かった長兄と、そうでもない次男)や台湾の田舎町、伝統行事(神猪祭)など、主人公が距離を置きたかったものとの関係修復がうまく表現されている。選考委員からは次のような講評が出ている。堀晃「現代SFの道具立てを意識的に使わず、まことに型破りな小説を作り出した」、酉島伝法「ガジェット的なSF要素は薄いが(中略)食肉という行い自体を顧みさせるSF的思弁性があり(中略)ジャンルを超えた書き手となる可能性も感じさせる」、小浜徹也(編集部)「新鮮な個性で、ほんのりした「IFの世界」性がうまく生かされた、愛される作品だ」
受賞作 松樹凛「射手座の香る夏」はサイコダイバー的な憑依もの。ホラーやファンタジーに陥ち入らず、SFで押し通した筆力に感心する。堀晃「寒冷地の描写、動物の疾駆など、いくつもの見せ場を経て、謎は次第に絞られていく。見事な語り口である」、酉島伝法「筆致は的確でリズムがあるし、構成は巧みで緩急があり(中略)SF的な仕掛けも豊富で、物語としては申し分がない」、小浜徹也「昨年の応募作が大人しい話だったのに比べ、今回は読後に若者らしい閉塞感と喪失感を残す印象的な作品である」
ちなみに溝渕久美子さんからは、評者の作品「豚の絶滅と復活について」についてコメントをいただいている。方向性が全く違う2作品ながら、前提となる設定がよく似ているからだろう。