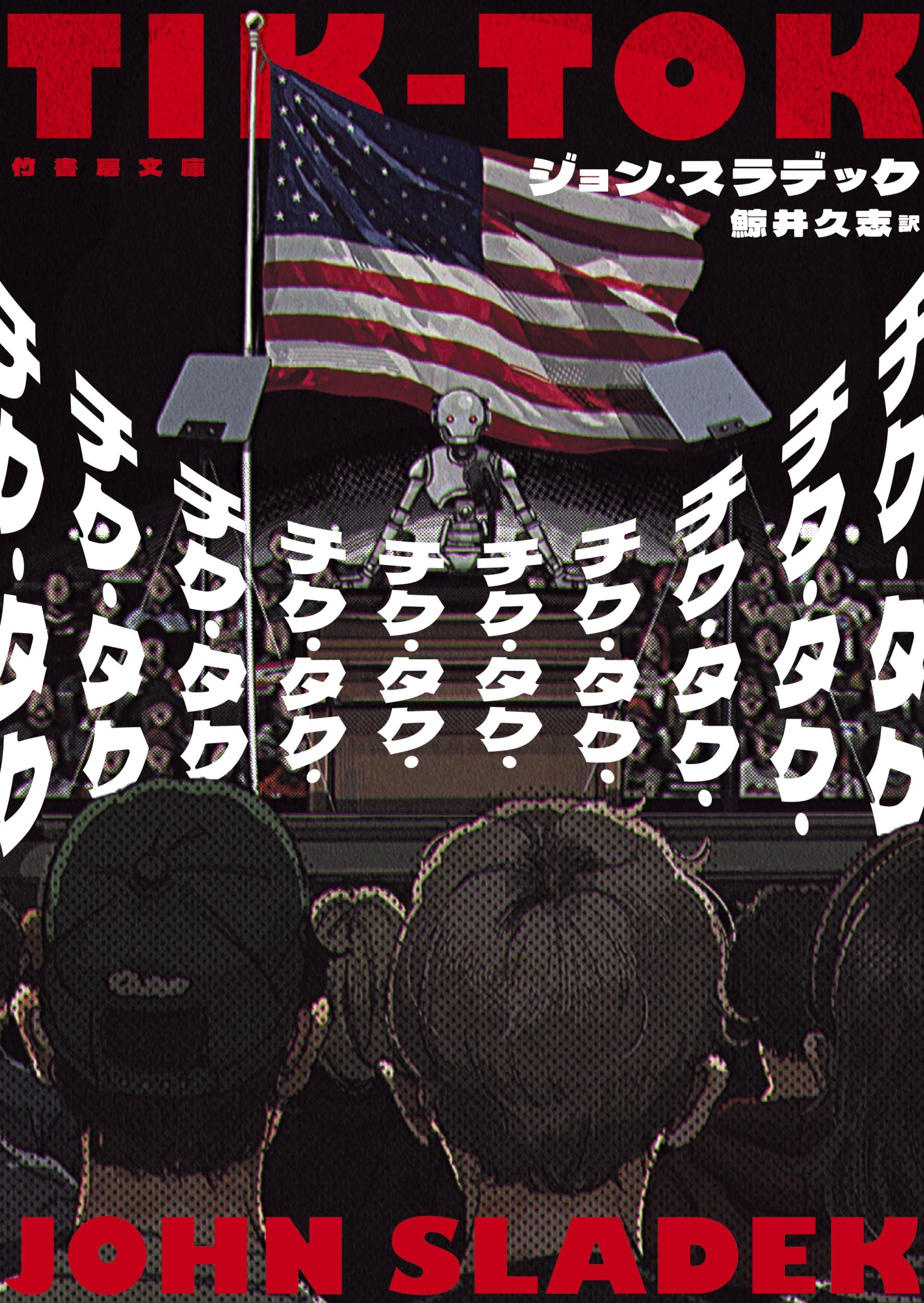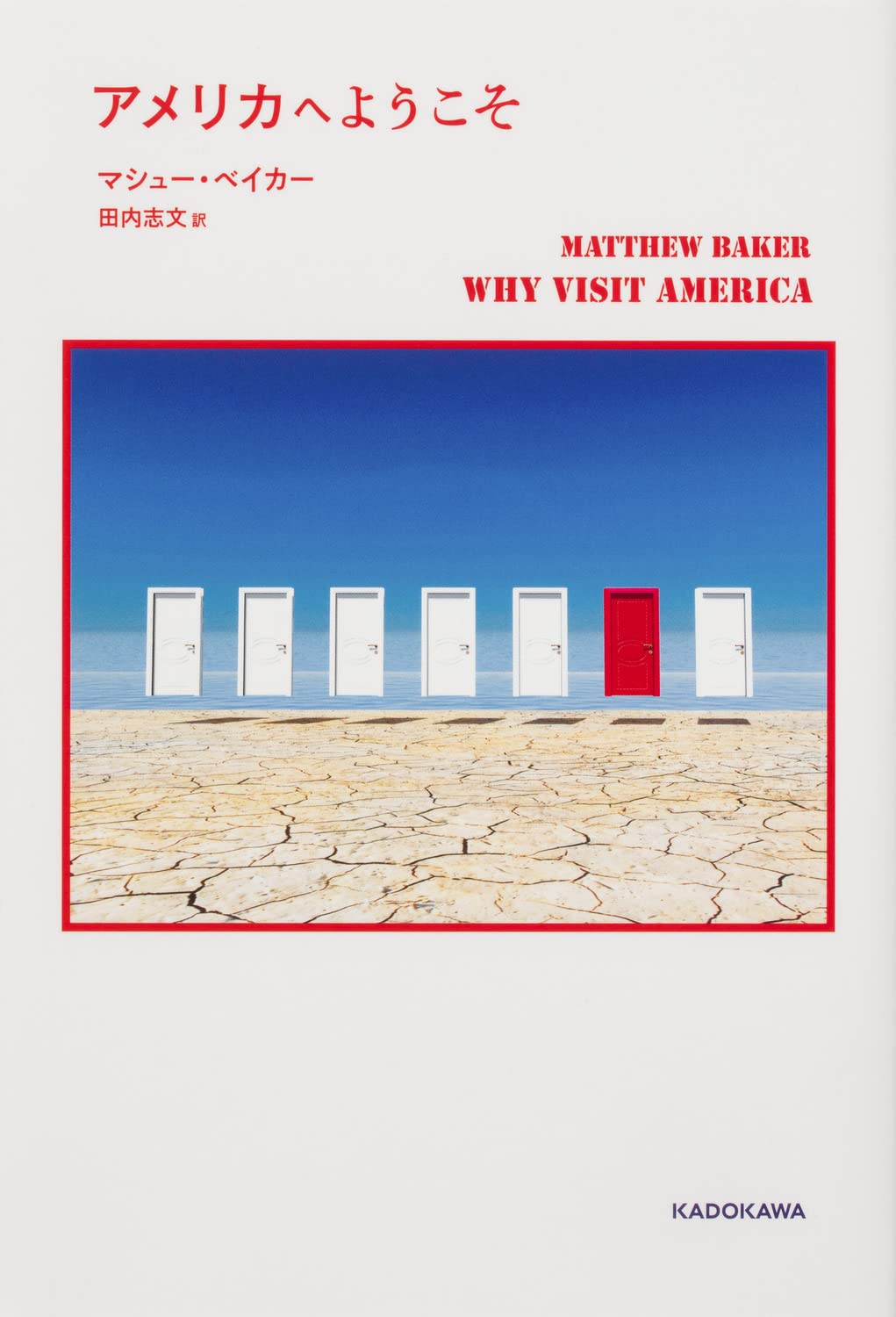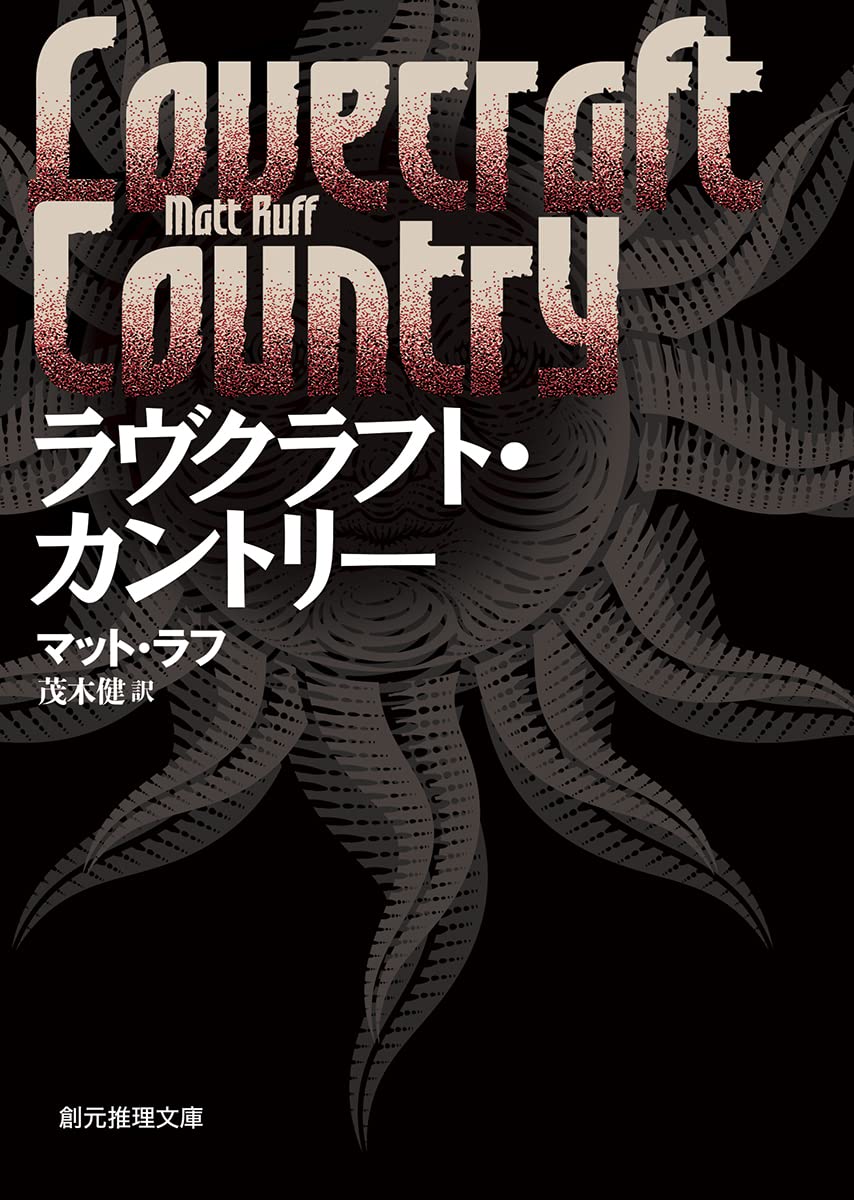装画:浅野信二
装丁:柳川貴代
2018年末に出た『言葉人形』に続く、谷垣暁美による日本オリジナルの傑作選である。今回は主にSFやミステリなど、ジャンル小説分野の作品から14編を選んだという。著者はもともとSF系媒体に作品発表をしてきており、例えば「アイスクリーム帝国」は原著がオンラインのSci Fiction(2005年終刊)に、翻訳がSFマガジンに(ネビュラ賞ノヴェレット部門受賞作として)掲載されているので、違和感のない選定といえるだろう。
アイスクリーム帝国(2003)匂いが音に変わり感触は声になった。生まれつき「共感覚」を持っていた主人公は、ある日同じ能力の女性と知り合う。
マルシュージアンのゾンビ(2003)研究休暇中の大学教授は、自宅の前で元心理学者だと称する老人と出会う。その男は娘に自筆のゾンビの絵を贈ってくれる。
トレンティーノさんの息子(2000)ロングアイランド湾で貝を獲る漁民たちの間で、不吉なうわさが広がる。海で行方不明になった若い漁師を見かけたというのだ。
タイムマニア(2015)主人公は5歳から恐ろしい悪夢に悩まされるようになった。ただ、タイムを淹れたハーブ茶を飲めばなんとかしのげる。
恐怖譚(2013)エミリーが目覚めると、屋敷には誰もおらず時計は止まっている。家の外では、見知らぬ男が馬車へと迎え入れようとする。自分はいったいどうなったのか。
本棚遠征隊(2018)薬のせいで頭がおかしくなった冬の夜、本棚の登頂を試みる微小な妖精たちの姿を見た。彼らは犠牲をいとわず、さまざまな本を足場に登っていく。
最後の三角形(2011)ヤク中のホームレス男は、とある老婦人から調査の仕事を請け負う。地図上の三角形の頂点にあたる場所で、秘密の赤いしるしを探せというのだ。
ナイト・ウィスキー(2006)山奥の片田舎にある辺鄙な村で〈酔っ払いの収穫〉の助手を務めることになった若者の体験。
星椋鳥(ほしむくどり)の群翔(2017)のどかで美しい都市〈結び目〉には、凄惨な連続殺人事件という未解決の汚点があった。専任警部は被害者の娘と周辺を疑う。
ダルサリー(2008)スーパーミニチュア版ヒト細胞から生まれた微小な人々は、ガラスの牛乳瓶の中にドーム都市ダルサリーを建設した。
エクソスケルトン・タウン(2001)古い地球映画を偏愛する異星人と交易するため、地球人は映画スターとそっくりのエクソスキンをまとう。
ロボット将軍の第七の表情(2008)対ハーヴィング戦争の英雄であるロボット将軍には、7つあるいは8つの表情があったとされる。
ばらばらになった運命機械(2008)老宇宙飛行士がかつて異星で手に入れた部品は、機械の一部分であるらしかった。
イーリン=オク年代記(2004)海辺の砂浜に作られた砂の城には、指の先ほどの大きさの妖精が住むことがある。波で城が崩れ去るまでがその生涯だった。
「アイスクリーム帝国」の共感覚、ジャック・ヴァンスを思わせるエキゾチックな宇宙譚「エクソスケルトン・タウン」や「ばらばらになった運命機械」、ハミルトン「フェッセンデンの宇宙」のような「ダルサリー」や、皮肉なロボット兵器「ロボット将軍の第七の表情」などを読むと、確かにクラシックなSFの感触がある。
とはいえ、「星椋鳥の群翔」や表題作「最後の三角形」は猟奇ミステリ、残りの多くはホラーと分類しても、あくまで奇想の切り口がそう見えるだけで、一般的なジャンル小説とは一味違うものだ。これは物語の方向性が、エンタメ的な事件の真相や動機の解明にないからだろう。オープンエンドとかではなく結末はあるものの、「なぜ」は謎のままなのだ。そこはジェフリー・フォードらしいといえる。
中では「本棚遠征隊」「イーリン=オク年代記」に出てくる微小な妖精たち(という意味では「ダルサリー」も含む)が作者のお気に入りのようで面白い。なお「恐怖譚」に出てくるエミリーとはエミリー・ディキンスンのこと。
- 『言葉人形』評者のレビュー