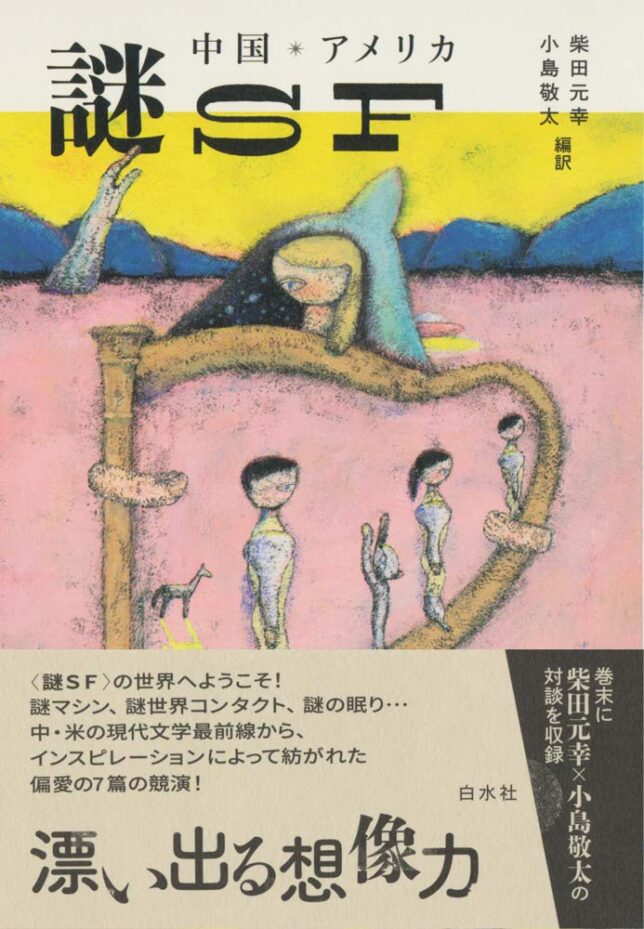装幀:早川書房デザイン室
フジテレビの地上波番組(ただし東京ローカル)で放映された全3回の「世界SF作家会議」(2020年7月/2021年1月/同2月)をまとめたもの。全員が(たとえスタジオに居ても)リモート参加で、6分割画面という今風のスタイル。カットシーンを補完した拡張バージョンは現在でもYouTube版が視聴できるが、本書は文字にする段階でさらに手を加えた決定版である。担当ディレクター黒木彰一がSFファンだったために実現した企画だという。海外の作家も参加したので(陳楸帆が同時通訳参加、劉慈欣/ケン・リュウ/キム・チョヨプらはビデオ参加)、世界SF作家会議でも大げさではないといえる内容になった。
【第1回】コロナパンデミックをどうとらえたか/パンデミックと小説/アフターコロナの第三次世界大戦(冲方丁)アフターコロナのトロッコ問題(小川哲)アフターコロナのセックス(藤井太洋)アフターコロナは・・・・・・ない(新井素子)/劉慈欣のメッセージ。
【第2回】パンデミックから一年・・・・・・SF作家たちはどう見たか?/人類はチーズケーキで滅亡する(小川哲)人類は宇宙からの災難で滅亡する(劉慈欣)人類はポスト人類で滅亡する(ケン・リュウ)人類は愛で滅亡する(高山羽根子、藤井太洋)人類は目に見えないもので滅亡する(キム・チョヨプ)人類は滅亡しない(新井素子)/地球滅亡の日に食べるなら、ご飯か麺か。
【第3回】SF作家が考えるコロナ禍の現状/100年後の企業帝国と惑星開拓(冲方丁)100年後の和諧(ハーモニー)(陳楸帆)100年後はサイボーグたちの世界(キム・チョヨプ)100年後は人間が変化する(劉慈欣)100年後は分からない(樋口恭介)100年後は予測不可能(ケン・リュウ)100年後はあまり変わっていない(新井素子)/地球脱出時に連れていくなら犬か猫か。
司会者のいとうせいこうは作家兼タレント、大森望がコメンテーター的な役割、それ以外は全員が作家である。6人で進行するのは、SF大会のパネルとしても多い方だろう。深夜帯とはいえ、非専門的な地上波TV番組として成り立つのかどうか見る前は疑っていた。評者はYouTube版で視聴したが、ネタ的な話題に偏らず(テーマはネタ的だが)、SF作家らしいキーワードを交えた分かりやすい流れで作られていた。さらに本書になると、キーワードに読み物としての重みが加わる印象だ。SF作家は予言者かと問われると誰でも違うと答えるだろうが、あらゆる可能性を(ありえないことまで含めて)考えてみるのがSF作家だという見方はできる。ハードな明日を冷めた視点で語る冲方丁、あくまで希望を失わない陳楸帆、何も変わらないとうそぶく新井素子が対照的で面白い。