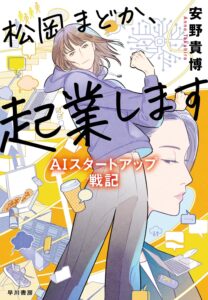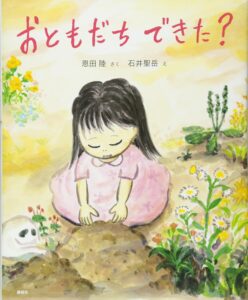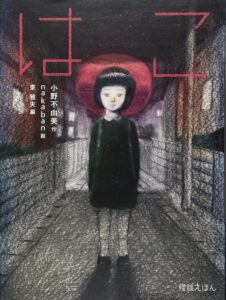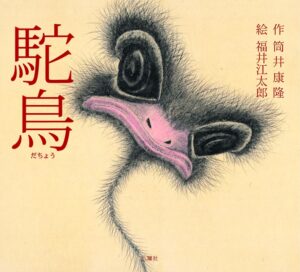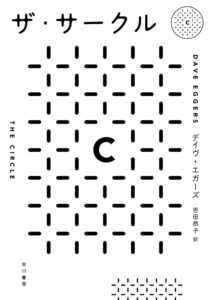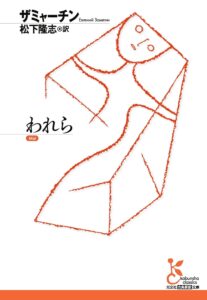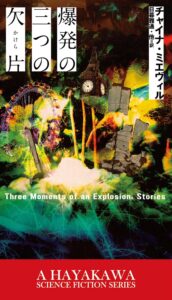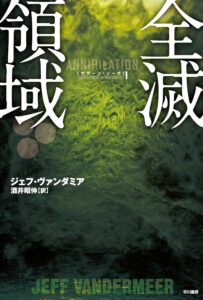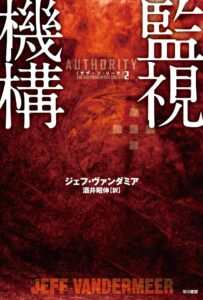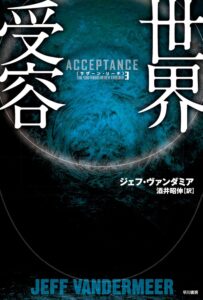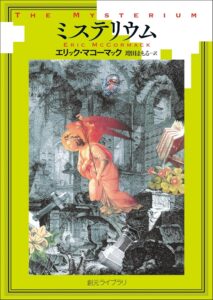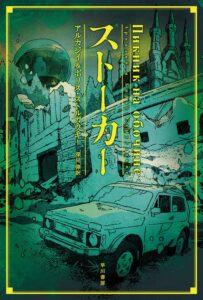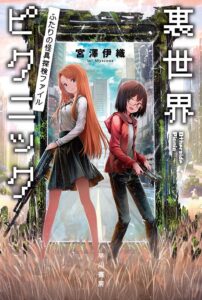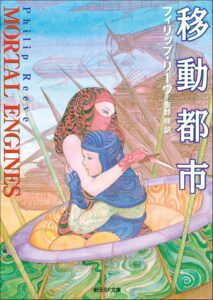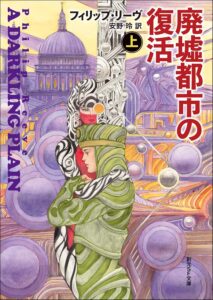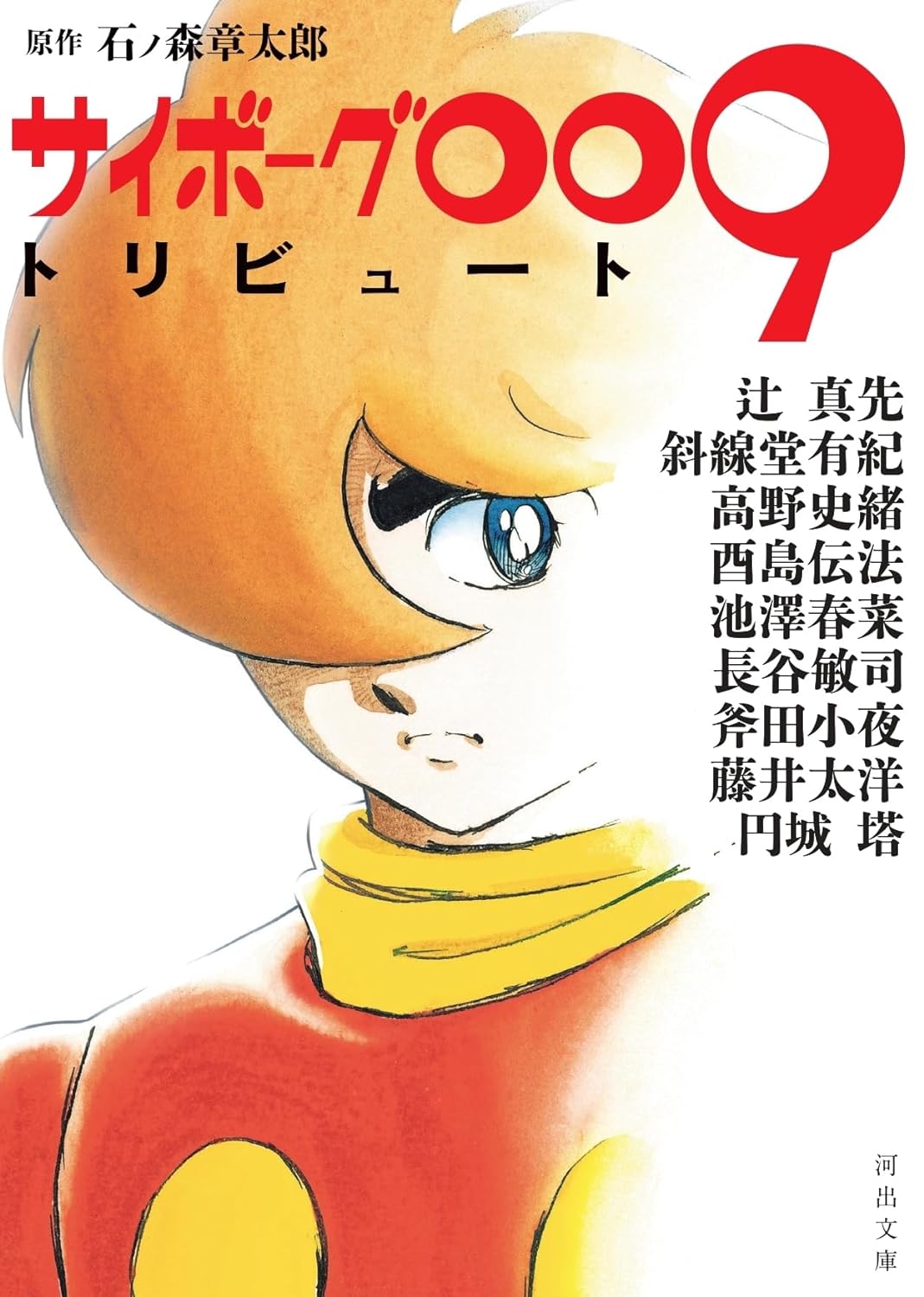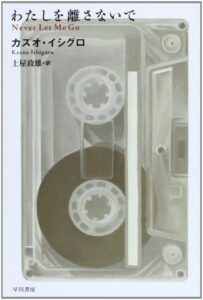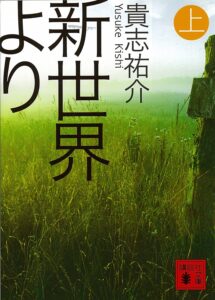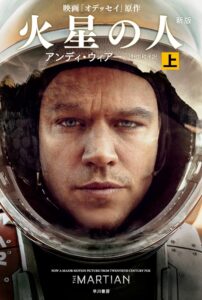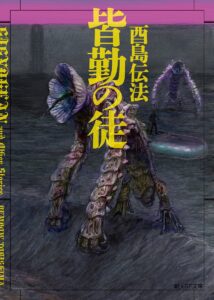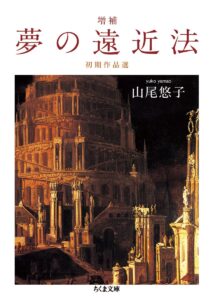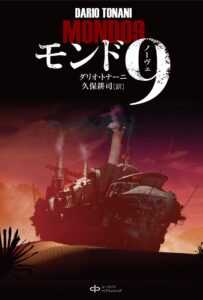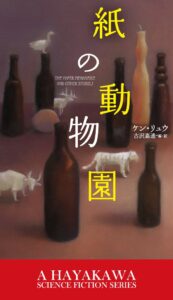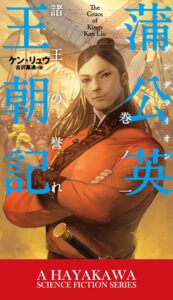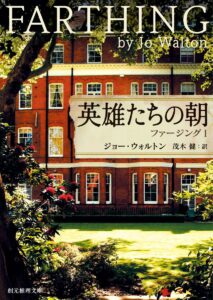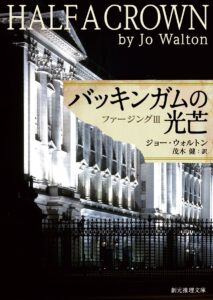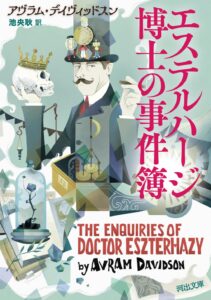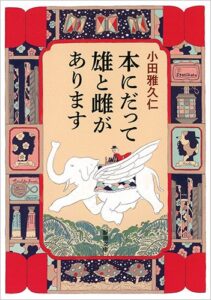シミルボン転載コラムの映画原作シリーズも今回で3回目、これで最後になりますのでよろしく。大作というより、ちょっと渋めの3作品を紹介しています。作家も渋いですが、じっくり書き込まれた読み応えのある作品ばかりです。以下本文。
映画も公開、SNSの闇に迫る『ザ・サークル』
トム・ハンクス、エマ・ワトソン主演で映画化され話題になりました。海外では公開済み、遅れていた日本でもようやく2017年11月に公開されます。IT社会を風刺した作品で、twitterやLINEなどのSNSを使っている人ならなるほどと思うエピソードの先に、全体主義社会の影が見えてくるという内容。とても怖いですね。特に今のSNS社会で困るのは、ほっといてくれないことです。黙っていれば発信しないやつだと怒られ、発言すると執拗につきまとわれ、善意であっても挙動を逐一見張られる。どうせ秘密が持てないのだから、世界中みんなが秘密を持たなければ良い、という発想の果てに本書があるわけです。
著者は、1970年米国生まれの作家、編集者、出版業、脚本家、社会活動家(移民家族のために読み書き支援を行うなど)です。本書は、架空のインターネット企業「サークル」を扱った作品。リアルの世界で苦労の多かった著者の経歴もあってか、スマートなIT会社が暗く変貌していく様子を描かれています。本書の内容について、日本のITギーク系の雑誌WIREDは高評価でしたが、米国版WIREDは内容をやや批判的に紹介していました。
「サークル」は巨大なIT企業です。主人公は旧態依然の地元に飽き飽きし、友人の紹介を伝手にサークルに入社します。そこには開放的なオフィス、先端的な仕事、自由な社風、厚い福利厚生制度があり、若い就職希望者が羨望する環境が用意されていました。彼女へは社内外SNSへの参加や、さまざまな情報発信が半ば義務付けられます。けれど、世界と繋がり合うほどに、自身のプライバシーは失われていきます……。
本書中に「秘密は嘘、分かち合いは思いやり、プライバシーは盗み」というスローガンが出てきます。これは、オーウェルが書いた『一九八四年』の「戦争は平和、自由は隷属、無知は力」に対応するように置かれています。サークルのガラス張りのオープンなオフィスも、ザミャーチン『われら』に現われるプライバシーのないガラスの建物を思わせます。とすると、本書はITがもたらす全体主義を風刺する小説のようです。
ただし、米国WIREDは、その批判は少し的外れではないかと指摘しています。SNSが持つ特性、秘密やプライバシーの排除は、裏で行われる不正や談合をなくし、過去の時代では知りえなかった真実を暴露する面もあるからです。とはいえ、見知らぬ他人からの干渉や、恣意的な誘導という暗黒面も存在します。
本書は前半でポジティブな面を強調し、後半でネガティブさを曝け出すように書いています。確かにtwitterやLINE、facebookなどでは、成り立ちが善意であっても、悪意で運用することで、窮屈な社会ができてしまう可能性があります。現実に起こった政府機関による干渉疑惑などを見ると、SNSによる大衆扇動がありえないとは言えません。一方向だけの発言が称賛されて、異論が許されず、ただ同一化が求められるなら、それは全体主義そのものとなってしまうでしょう。
(シミルボンに2017年10月5日掲載)
映画「アナイアレイション―全滅領域―」に見る、彼岸世界は徒歩圏内?
そのむかし、あの世とこの世は地続きであると考えられていました。つまり歩いてあの世に行けるわけですね。生と死が身近で、隣り合わせだった時代を反映しています。神話や伝承にある黄泉の国の入り口は、いまでは地名だけになって残されています。人が増え、宗教心が薄れ、世界が狭くなると、そういった地続きの異世界は顧みられなくなりましたが、物語の中では別のかたちで蘇っています。
その一つが、今回紹介する三部作です。パラマウント版「アナイアレイション―全滅領域―」は、誰もが生還できず「全滅する」という、何だか怖い題名になっています。「エクス・マキナ」「わたしを離さないで」のアレックス・ガーランド監督、「ブラック・スワン」のナタリー・ポートマンの主演で、2018年2月下旬から3月にかけて世界21か国で公開される作品ですが、三部作はその原作にあたります。
著者ジェフ・ヴァンダミアは1968年生まれの米国作家、アンソロジストで、チャイナ・ミエヴィルらが提唱する「ウィアード・フィクション」(気味の悪い小説)と同様の、「ニュー・ウィアード」と呼ばれる幻想ホラー小説の書き手であり編集者です。世界幻想文学大賞を3度受賞していますが、そのうち2度はアンソロジイの編者としての受賞でした。そういうジャンル小説をよく知る書き手が、今回は少し変わったアプローチで三部作を書いたのです。
『全滅領域』:自然豊かな海岸部のどこか、エリアXと呼ばれる領域に調査チームが入る。11回に及ぶ調査はことごとく失敗し、隊員は不可解な死を遂げたり正気を失っている。何が原因なのか、条件を変えるため12回目の探査では女性だけが選ばれる。メンバーはお互いを名前で呼ばず、職種名で呼ぶ。隊員は地下へと降りる〈塔〉の中で、壁面を覆いつくす文字を見つける。
『監視機構』:エリアに隣接して、〈サザーン・リーチ〉という監視研究機関が設けられている。前所長が行方不明となり、新任の所長が着任する。しかし、非協力的な副所長や言動が奇妙な科学部のメンバーなど、所内の様相は混沌としている。前所長は何をしようとしていたのか。新任所長に与えられた、本当の目的とは何か。
『世界受容』:エリアXが拡大を始める。エリアの中では、失われた隊員から変異した何者かが見え隠れる。新任所長はエリアへの潜入を試みるが、そこでは異形の生き物がうごめき、過去の記憶と偽りの未来が混交する。時間の流れさえ均一ではない。エリアの正体は、果たして明かされるのか。
最初の『全滅領域』だけを読むと、エリック・マコーマック『ミステリウム』(1993)のような印象を受けます。固有名詞を持たない登場人物と正体不明の世界、解き明かされない謎など、ある意味典型的な幻想小説のスタイルともいえるでしょう。『監視機構』では、そこに〈サザーン・リーチ〉という外形が設けられ、(得体は知れないながら)組織的な背景や、人間関係が明らかにされます。『世界受容』に至っては、今度はエリアXという世界の本質にまで踏み込んでいます。語り手の視点には、いくつかの工夫があります。第1部は一人称、第2部は三人称、第3部は一人称、二人称、三人称をパートごとに交えているのです。個人の狭い視点による歪められた世界が、三人称で客観化されたかのように見えて、最後にまた混沌へと戻っていくわけですね。謎は解明されたともされていないとも取れます。
ウェブ雑誌The Atlanticの長い記事の中で、著者はこの三部作の顛末について記しています。2012年に、まず『全滅領域』の草稿が書かれ、上記のような3つの視点から成る《サザーン・リーチ》三部作として売り込むと、SFやファンタジイなどのジャンル小説以外の出版社からオファーを得ます。文藝出版の老舗FSG社(大手出版社マクミラン・グループの一員)は、1年内で3作一挙刊行を提案してきました。条件は「読者は謎の解明を求めるだろうから、きっちりそこまで書くこと」。著者も、第1部(ある種の不条理小説)だけで終わるより、3部作を通して人智を超えるものを表現する方が重要と考えました。残りを書き上げるまで18か月、出版は2014年になってから、2月・5月・9月と連続して出ました。最近のメジャーな出版では、三部作を間髪を入れずに出せることが前提のようですね。
物語の中には、著者の体験がさまざまに取り入れられています。車の中の潰された虫、家に忍び込む体験、フロリダ北部に似せたエリアXの自然、トレッキング中に膝をひどく痛めたことや、ミミズクの生態に触れたことなどなど。それらがない交ぜとなって、まるで超現実的な旅をしているようだったといいます。
歩いて行ける異界を扱ったSFと言えば、ストルガツキー兄弟が書いた『ストーカー』が元祖でしょう。危険なものが潜む異界にはお宝もあり、密漁者(ストーカー)たちが命を懸けて忍び込みます。
その『ストーカー』のオマージュともいえるのが宮澤伊織『裏世界ピクニック』です。異世界と実話系怪談を両立させた、新しい表現が注目を集めました。ご存じのように大人気となりシリーズ化、コミック化やアニメ化もされています。
(シミルボンに2018年2月20日掲載)
荒れ果てた未来の海で、なぜ都市は移動するのか
2019年3月1日に日本公開された、クリスチャン・リヴァース監督、ピーター・ジャクスン製作・脚本の映画『移動都市/モータル・エンジン』は、未来の干上がった海の上を巨大都市がキャタピラで走り回るという迫力ある映像が話題になりました。本書はその原作です。
原著者のフィリップ・リーヴは英国の作家です。《移動都市クロニクル》は、2001年から2006年にかけて出版され、第4部『廃墟都市の復活』がガーディアン児童文学賞を受賞しました(その後、短編集なども出ました)。そうか児童文学だったのかと納得する人、意外に思う人もいるでしょう。もともとファンタジイ小説は、児童文学やヤングアダルト文学での出版が多いのです。
ただし、東京創元社などでは、大人でも問題なく読める作品として紹介されてきました。例えば、スーザン・プライス『500年のトンネル』や、パトリック・ネス《混沌の叫び三部作》などもそうです。他では、ハインラインの長編の多くも、もともとジュヴナイル(例えば、『ラモックス』、『銀河市民』、『宇宙の戦士』などなど)だったのですね。あえて区分けする必要はないのかもしれません。なお、シリーズ第1作の『移動都市』は、2007年の星雲賞海外長編部門を受賞しています。
舞台は30世紀を過ぎたいつかの時代。60分戦争で世界は滅び、生き残った人類は巨大な移動都市の上で暮らしています。無数のキャタピラや車輪で、文字通り移動する都市ロンドンでは、科学ギルドが戦争前の失われた技術の修復に成功します。激しい生存競争を繰り広げ、都市同士が喰い合うことを認める移動派、そういう海賊的な移動都市と対立する反移動都市同盟、空を自由に飛ぶ飛行船乗りたち。陰謀と隠された過去の秘密を交えながら、物語は最後の対決シーンへと進んでいきます。
発表当時から、どことなく初期の宮崎アニメを思わせる雰囲気がありました。とてもヴィジュアルな移動都市や兵器の描写、デフォルメされた小道具の数々と、戦いのむなしさに対する思想がそういう連想を誘うのでしょう。主人公は見習い士トム、悲惨な過去を背負った娘ヘスター、美貌のギルド長令嬢らを絡めた波乱万丈なお話です。戦闘シーンが豊富にあるのに、陰惨さはほとんどなく、明快な筋立てで分かりやすい。物語では主人公のトムや、対するヘスターはともに(児童文学なので)少年少女なのですが、映画ではもう少し年上の設定となっています。
本シリーズは、2010年に第3部まで翻訳された後、長い間紹介が滞っていました。映画化を機に9年ぶりに第4部完結編まで出たのは喜ばしいことです。
(シミルボンに2019年3月6日掲載)