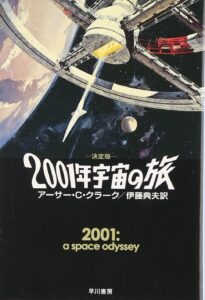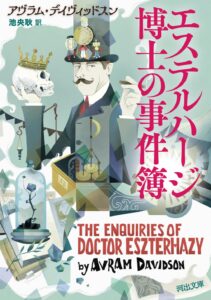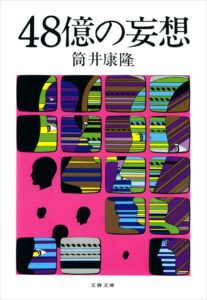シミルボン転載コラム、今週からは3回に分けて映画の原作から選んだブックレビューをお送りします(あくまでもブックレビュー、映画評ではありません)。対象となった作品はいろいろあって、大作映画からマイナーな作品、原作に忠実なものや独特すぎるものなども。原作ありきですので、メディア媒体はTV/劇場、実写/アニメを問わず取り上げています。発表年とか掲載の時期はさまざま。なお、視聴可能なものは配信先(主にAmazon Video)をリンクしています。以下本文。
映画 Arrival(メッセージ) と、あなたの人生の物語
ネビュラ賞、星雲賞を受賞したテッド・チャンの短篇「あなたの人生の物語」が、Arrivalという題名で映画化される。まるで、マグリット「ピレネーの城」のような異星人宇宙船が印象的だ。2016年11月には全米で公開されるという(邦題は「メッセージ」2017年公開)。ただ、映画は宇宙人とのコンタクトに焦点が移っているようで、小説とは(おそらく)異なるものになる。ここでは、もともとの原作を振りかえってみたい。
まず、「あなたの人生の物語」にある二人称「あなた」とは、主人公の娘のことである。しかし、それは同時に本書を読むあなたであり、人類すべてを記述する1つの記号のことでもある。すべての人生が、たった1つの文字=記号に凝集され、物語られるのである。
バビロンの塔(1990)天まで届く塔を建設し、ついに天頂の壁に達した男のたどり着いた世界とは。理解(1991)脳内の神経線維を再生する治療は、主人公に驚くべき“理解力”をもたらす。ゼロで割る(1991)数学を根底から否定する証明を導き出した、数学者である妻と夫。あなたの人生の物語(1998)異星人との接触がもたらした全く新しい文字で、表現された主人公の娘の物語。七十二文字(2000)非生物に生命を与える、ある種の呪文“名辞”の命名師に課せられた新たな使命。人類科学の進化(2000)優れた新人類の叡智を知るには、理解できるものをひたすら“解釈”する道しかなかった。地獄とは神の不在なり(2001)天使の降臨が天変地異を引き起こす世界で、その意味を追いつづける人々の命運。顔の美醜について(2002)美醜を感じ取る機能を遮断する運動は、社会の差別をなくすとされたが…。
アイデアの作家ではあるが、チャンの場合アイデアはあくまでも物語の一面にすぎない。たとえば表題作は、異星人とのコミュニケーションと、主人公の娘の一生(なぜ、主人公が娘に向かって二人称で語りかけているのかが肝要)が、異星の文字(事象を1語で認識できる)を交点にして焦点を結ぶ。お話の構造としても大変に美しい。
本書には、ファンタジイも多く含まれている。作者は、魔法は科学と違って、人の意識がより大きな位置を占めるから興味があると語る。「バビロンの塔」や「七十二文字」は、世界の謎を魔法で解き明かす物語だ。よく似た作風のイーガンは、 科学を使って人の主観と相容れない領域に切り込むが、どちらもSFの手法を使っている点は共通している。SFを知らない一般読者向けには、むしろ世界の解明を伴わない「地獄とは…」や、「ゼロで割る」の夫の心理に共感できるだろう。
「地獄とは…」は、よくキリスト教的な世界観を引き合いに出して難解さを論じられているが、そもそも作者は熱心なクリスチャンではない。これは、理不尽な自分の運命に、意味を見出そうとする人の執念の物語なのである。特異な世界/特異な事件から、人間の意識の奥底が違和感なくつながって見える。
著者は、20年間で短編集1冊といくつかの短篇しか書いていない(第2短編集が2019年の『息吹』である)。寡作と言わざるをえないだろう。インタビューで本人が述べているように、書く衝動に任せるタイプではなく、アイデアを得てからそれを練り上げるため、なかなか数が稼げないという。情熱(勢い)より様式美が際立つのには、こういう理由がある。
(シミルボンに 2016年8月19日掲載)

太陽系に広がる人類、《エクスパンス・シリーズ》
ドラマ配信が日本でもスタートし、注目度の高まった本作品だが、原作の翻訳は3年前(2013年)に出ているので紹介する。著者のジェイムズ・S・A・コーリイは、ダニエル・エイブラハムとタイ・フランクという、1969年生まれの作家の合作ペンネームだ。エイブラハムは、ガードナー・ドゾア&ジョージ・R・R・マーチン(《ゲーム・オブ・スローンズ》原作者)との合作『ハンターズ・ラン』の事実上の執筆者でもある。本書は受賞こそしなかったものの、ヒューゴー賞やローカス賞の最終候補にもなり、《エクスパンス・シリーズ》(人類世界の「拡張」という意味)として第五部(2015)まで書き継がれている(その後小説版は2021年に長編9冊まで続き、映像のAmazonオリジナル版は2022年にシーズン6で完結)。他にも複数の派生作品があるなど人気が高い。
土星から小惑星帯へ氷を運搬するタンカーが、救難信号に偽装された何者かの罠に捕えられ、船ごと爆破される。生き残った副長はこの犯罪を暴くべく証拠をネットに流すが、その結果、微妙なバランスを保っていた内惑星系と小惑星帯との関係が崩れていく。戦争の気配が忍び寄る中、背後では恐るべき犯罪が進行しようとしていた。
正義感溢れる副長は、しかし、十分な証拠もないまま戦争の火種を公表してしまう。もう一人の主人公である小惑星人の刑事は、行方不明の女性を調査するうちに精神を病み、その女性の幻影を見るようになる。彼は女性のアドバイスに従って、犯罪の真相に迫ることになる。
およそ200年後の未来、人類は地球、火星、小惑星帯、最遠の天王星までに広がっている。広大な外惑星帯には億を超える人類が住んでいるが、圧倒的な格差のある内惑星と戦っても得るものはない。ただ、政治的にはどちらの陣営も一枚岩ではない。さまざまな勢力や、コントロールできないテロリストを抱えているからだ。人口100万を超える小惑星を巻き込む事件は、そんな背景で生じるのである。近未来の太陽系が、その距離間と経済的背景/必然的に生じる政治的駆け引きなどにより、リアルに描き出されている。そこに、いささか問題のある登場人物を配して、物語に起伏を与えているのだ。
(シミルボンに2016年11月7日掲載)
さまざまな意味で古典、2001年宇宙の旅
この作品が初めて翻訳されたのは1968年10月、原題に準拠した『宇宙のオデッセイ2001』という邦題だった。映画『2001年宇宙の旅』が同年4月に日本公開され、難しすぎる結末の解釈について、大論争が巻き起こっていたころだ。見世物的な特撮映画と思って見にきた一般観客は、あ然とするか、寝るか怒るかだった。
300万年前、地球に忽然と現れたモノリスがもたらした知恵により、豹に怯える弱々しい猿だった人類は道具の存在を知り、やがて地球の覇者へと登りつめる。20世紀末、月面のクラビウス基地では、地下に埋もれたモノリスが発見される。地上に姿を現したモノリスは、月の夜明けの光を受けた瞬間、指向性を持つ電波を宇宙に向かって放射する。電波の先には木星があった。そして2001年、孤独な宇宙空間を飛行する宇宙船ディスカバリー号では、支援コンピュータのHALがなぜか人間の乗組員を裏切る。たった1人生き残った宇宙飛行士は、木星(小説版では土星)のスター・ゲートをくぐったあとに何を見たのか。
クラークとキューブリックがどういうやりとりをして映画を作ったのかは、クラークが映画の4年後に出した『失われた宇宙の旅2001』(1972)に詳しい(この本は絶版だが、その後出たノンフィクション『2001:キューブリック、クラーク』は現在でも入手可能)。2人が検討した結果、使われなかった原案の数々について書かれている。映画の落穂拾いかというとそんなことはなく、お話になっている部分が大半を占める。もちろん、部分であって完結した長編ではないが、もともとの『2001年宇宙の旅』自体のあらすじを知っていれば、さほど違和感はない。
その中で、スター・ゲートを抜けた後のエイリアンとの出会いを描いたシーンがある。映画では完全にカットされた部分だ。キューブリックとしては、神に相当する存在を描くのに、形があるものではリアリティが出ないと考えたのだろう。CG全盛の今でも、人類より間抜けなもの、異質なもの、邪悪なものならいくらでもいるが、高等と感じられる超越的エイリアンを表現した映画は(ほぼ)見ることができない。結果的に、この選択(異星人は姿を見せない)が間違っていたとはいえないわけだ。
『宇宙のオデッセイ2001』はその後1977年に文庫化される際に、映画邦題に合わせた『2001年宇宙の旅』となり、1993年には現在の改訳決定版となる。映画はディスクやネットでいつでも見ることができるが、本書も発表からほぼ半世紀を経て読み継がれる、映画とは独立したクラーク代表作のひとつになった。人類の進化、近未来の惑星間航行、人工知能の開発、宇宙人とのファーストコンタクトなど、さまざまなテーマが込められているが、そのどれにおいても本書は古典といえる。
(シミルボンに2017年2月17日掲載)