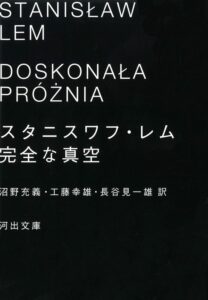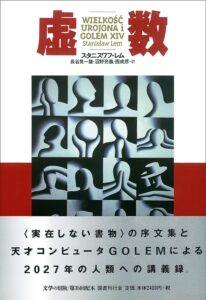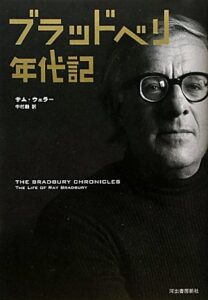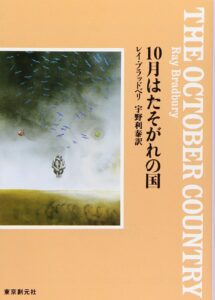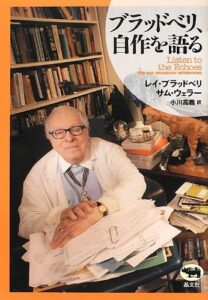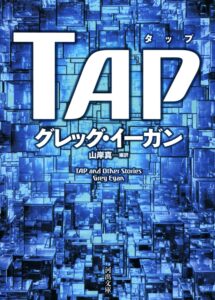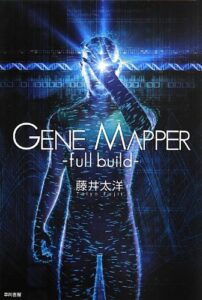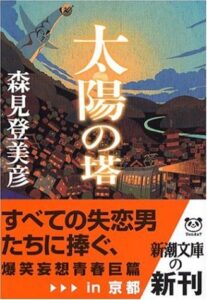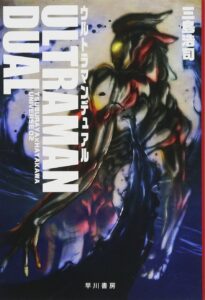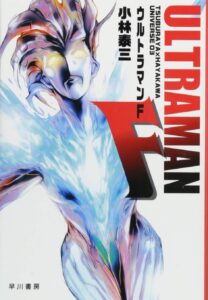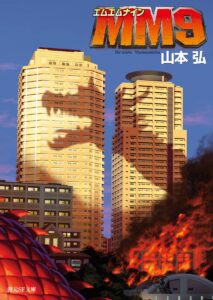シミルボン転載コラムです。ベストセラーから大ヒットドラマを産み出したマーチンですが、デビュー当時からホラー寄り・スーパーヒーロー寄りなどの顔を持っていました。そういう初期の作品を含めて紹介しています。ただ、絶版本が多く古いものは電子版もないので、コラムだけでは十分ではありません。本文中にある過去のレビューへのリンクを参考にしてください。以下本文。
1948年生。現時点でマーティンといえば、ベストセラー《氷と炎の歌》=エミー賞の最多受賞作品でもあるHBOのTVドラマ《ゲーム・オブ・スローンズ》の原作者・脚本家・製作者なので、それ以外の作品はよく知らない人も多いだろう。1971年にプロデビュー、当初は主にSFを書いていた。ヴォンダ・マッキンタイア、ジョン・ヴァーリイ、先ごろ亡くなったエド・ブライアントらとLDG(レイバー・デイ・グループ)の同世代になる。
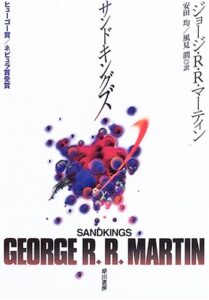
初期作を集めた短編集『サンドキングズ』(1981)では、表題作がヒューゴー賞、ネビュラ賞を受賞するなど高評価を得る。また、コミックが大好きで、日本でも第3部まで翻訳されたスーパーヒーローものの共作《ワイルド・カード》(1986-)の編纂や、ジャック・ヴァンス『宇宙探偵マグナス・リドルフ』へのオマージュでもある《タフの方舟》(1986)、ミシシッピ川を航行する蒸気船を舞台にした、吸血鬼ホラー『フィーヴァードリーム』(1982)も書いた。ホラーについては、日本で編まれた短編集『洋梨形の男』(2009)にエッセンスが収録されている。
電子書籍でも入手可能なSFとなると、初長編『星の光、いまは遠く』(1977)だろう。
辺境の放浪惑星ワーローン。銀河を巡る長大な軌道から、太陽に接近し居住に適する期間はわずか10年余り。しかし、その10年のために惑星規模の改造が行われ、外縁星域に散在するさまざまな文明が競い合うフェスティバルが開催された。宴も終わり、再び暗黒の外宇宙へと離れていく惑星に、1人の男が降り立つ。やがて、遺されたさまざまなパビリオンの廃墟を舞台に、かつての恋人を巡って、野蛮な習俗を復活させようとする一派との争いが生まれるのだ。
主人公は優柔不断な文明人、対するは、決闘や人間を狩る伝統を有するハンターの一族。描かれる“宴の後”の世界は、冬の訪れ=滅びの色を湛えながら、華麗にしてエキゾチックである。一族の法に苦しむ豪胆な男たち、次第に彼らの考えに惹かれていく主人公、行動派で妥協しない女性と、登場人物は4半世紀後に書かれる《氷と炎の歌》を思わせる。ベストセラー作家となった作者の、その後を知っているから楽しめるとも言えるが、そういった余分な情報抜きでも面白い。特に中盤を過ぎ、後半に向かってのドライブ感、終盤に至っての意外な収束が読みどころ。
さて、本命の《氷と炎の歌》シリーズは20年間にわたって書き継がれ、全7巻(各巻が2000枚から3000枚に相当する長さ)を予定するが、いまだ完結していない長大な作品だ。堅牢な世界構築が、このシリーズの魅力だろう。ファンタジイに科学的な説明は要求されないが、世界の成り立ちに矛盾があってよいわけではない。舞台となる大陸のありさま、8千年前(さらに4千年前のできごと)にさかのぼる伝説、七王国の由来と神話、宗教、各王家の人々とその性格など、世界を形作る体系=システムの緻密さ、矛盾のなさが重要なのだ。
第1部『七王国の玉座』(1996)不規則な夏と冬との季節を持ち、中世ヨーロッパを思わせる異世界が舞台。ドラゴンを旗印に300年続いたターガリエン王朝が倒されて15年、不安定な均衡状態にあった王国に暗雲が立ち込める。新王ロバートは酒におぼれ、放蕩を尽くして王国を傾ける。新規に王の片腕に任命されたスターク家は、王の后を戴くラニスター家と軋轢を深め、他の貴族(7つの名家)を巻き込み、ついに内戦の危機を迎える。冬の到来と共に甦る、はるか北辺の不気味な伝説。そして、海の彼方の騎馬民族から、ドラゴン王の血を引くものが生まれようとしていた。

第2部『王狼たちの戦旗』(1999)ロバート王亡き後、王都を押さえるラニスター家(摂政を務める后と長男、后の弟)に対して、ロバート王のバラシオン家次男と三男、王とともに殺された北の王スタークの長男は、互いに覇権をめぐって戦いを繰り広げる。戦いの混乱の中で、狼とともに育った幼いスターク家の兄弟姉妹たちにも、さまざまな困難、破壊と暴力/死が立ちふさがる。やがて、首都攻防の大会戦が陸海で勃発する。
第3部『剣嵐の大地』(2000)七王国の玉座を賭けた決戦は、湾を埋めつくした大船団の壊滅で終わる。タイレル家との婚姻による同盟により、ラニスター家の権力は頂点を極める。七王国の統治は事実上ラニスター家のものとなった。しかし、北辺では、伝説の〈異形〉におびえる野人たちが、壁を破壊する勢いで押し寄せ、フレイ家への謝罪のため赴いた北の王は、恐ろしい血の歓待を受ける。
第4部『乱鴉の饗宴』(2005)前巻が出てから5年後の刊行。北の王の死、結婚披露宴での毒殺、暗殺と、七王国全土に血塗られた闇が被さりつつある。ラニスター家の当主亡き後、玉座の実権は王母サーセイ摂政太后が握る。評議会を自らの取り巻きで固めたサーセイは、しだいに臣民の信頼を失っていく。太后は最愛の弟すら身辺から退け戦場へと追い払う。
第5部『竜との舞踏』(2011)は、さらに6年後の刊行。物語は第4部と並行して進むため、第3部の直後の時代から始まる。デナーリス女王は、3頭の巨竜を従えたターガリエン王家の正統な後継者だったが、内乱や外部の敵対勢力に苦しめられる。竜たちは巨大化し、王女でさえ抑えきれなくなってきた。そのころ、女王デナーリスが七王国へ帰還する手助けをして、自陣営に引き入れようとする勢力が現れる。一方、北を封じる〈壁〉にある黒の城では、総帥ジョンが新しい施策を打ち出し、〈壁〉を死守しようとしていた。
権謀術数の戦国時代絵巻は、全編を通じて繰り広げられる。しかし、その一方で、“冬”の到来とともに、魔法の力がしだいに増してくる。ばら戦争時代のヨーロッパ、北欧のヴァイキング、あるいは古代ギリシャなど史実を織り交ぜた七王国はリアルに、中央アジアを思わせる騎馬民族の国や、蘇るドラゴンの存在、南方の中国風の大都市は幻想/魔術的と、多彩に描き分けられる。極北からは伝説であるはずの魔法や魔物〈異形〉が七王国を侵食してくる。この物語には、マーティンが親しんできた物語や歴史、SFやホラー、コミック的要素が万遍なく込められている。加えて、脚本家時代の経験や、《ワイルド・カード》などで多数の作家と共作してきた経験も生きているようだ。
2011年についにTVシリーズがスタートし、原作が5部までなのに、2016年時点で第6シーズン(各シーズン10話)まで進んでしまっている。原作を追い越したわけだが、一応マーティンの監修のもとにオリジナルのストーリーはなぞられているようだ。ドラマと、今後出る小説とで大きな矛盾が生じることは(おそらく)ないだろう。
(シミルボンに2017年2月22日掲載)
この後、LDGの盟友マッキンタイアも亡くなり、ドラマ《ゲーム・オヴ・スローンズ》は第8シーズンで完結しました。一方、本編の原作は追い付かないまま今に至ります。その代わり(なのかどうなのか)、ドラマ《ハウス・オブ・ザ・ドラゴン》となった前日譚《炎と血》や『七王国の騎士』が出ていますね。2019年になって翻訳された初期のSF傑作選『ナイトフライヤー』も入手可能です。